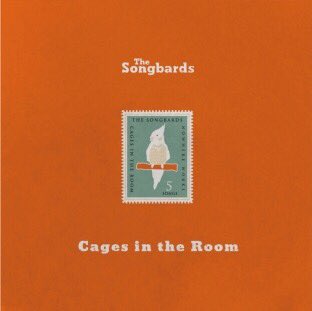神戸を拠点に活動する4人組ロック・バンド、The Songbardsがファースト・ミニ・アルバム『Cages in the Room』をリリースした。blood thirsty butchersやGLIM SPANKYなどの作品でも知られる南石聡巳をレコーディング・エンジニアに迎えて制作された本作は、ビートルズやオアシス、ストロークス、キュアーなど洋楽ロックからの影響をダイレクトに受けつつも、文学的かつ哲学的な歌詞世界や軽快なビートなどはandymoriに通じる〈等身大のポップネス〉も持ち合わせており、コアな洋楽ファンから若い邦楽リスナーまで、幅広く注目を集めること必至だ。
地元のライヴハウスにて4時間ライヴを定期的に行うなど、ハンブルグ時代のビートルズを思わせる活動も気になる彼ら。バンドの自主レーベルに〈Nowhere Works〉と名付けるセンスもまた、ビートル・マニアであればニヤリとせざるをえない。この神戸のファブ・フォーはいったいどのようにして集まり、どんな思いで音を奏でているのだろうか。メンバー全員に話を訊いた。
先人からの〈系譜〉を受け継ぐという意識が強い
──まずは、The Songbards結成の経緯を教えてください。
松原有志(ギター/ヴォーカル)「僕と(上野)皓平は、The Songbardsを始める前にAnt Lilyというバンドやっていて。ドラムスとベースは代わりつつ3年くらい活動をしていたんですけど、中学の同級生だった柴田(淳史)と、別のバンドでドラムを叩いていた岩田(栄秀)が加入した段階で〈心機一転〉したというか。今のバンド名に改名して、再出発することにしたんです」
──それぞれ、どんな音楽を聴いて育ったんですか?
松原「僕は小学校から高校の終わりまでずっと野球漬けだったんです。ただ、親の影響で小さい頃から洋楽は聴いていて。例えばビートルズやアバ、クイーン、それから洋楽じゃないけど、サザンオールスターズも家でよく流れていましたね。で、中学生のときにマイケル・ジャクソンが亡くなったんですけど、そのときに自分はマイケルと同じ誕生日(8月29日)だということに気付いて(笑)。それで、2個上の兄貴と2人でマイケル・ジャクソンを掘り下げていくようになったのが、本格的に音楽にハマったきっかけですね」
上野皓平(ヴォーカル/ギター)「僕は小さい頃から歌うのが好きだったんですけど、中学生のときにエレファントカシマシや斉藤和義、ブルーハーツなどを聴くようになって。自分でギターを弾きながら歌いたいと思ってお年玉でアコギを購入したんですね。で、中三のときにたまたまTVで観たレディオヘッドのライヴに衝撃を受けて、そこから音楽にどんどんのめり込んでいきました」
柴田淳史(ベース)「僕は最初、ギターをやるつもりで中学のときにエレキギターを買ったんですけど、高校でバンドをやろうってなったときにベーシストがいなくて。僕ともう1人ギターがいたんですけど、そいつがメチャクチャ上手かったので、仕方なくベースをやることにしたんですよね(笑)。でも、おかげでthe band apartやジャミロクワイのベースのカッコ良さが解るようになって、その辺をよく聴いていました。ビートルズを聴くようになったのは、The Songbardsに加入してからです」
岩田栄秀(ドラムス)「僕は、姉の後を追って中学生のときにブラスバンドに入ったんです。そこで3年間打楽器を練習したのがかなり大きいですね。高校へ入ってからはバンドを始めるようになって、それでポスト・ロックにハマっていきました。toeとかトータスとかドラムがメチャメチャかっこいいじゃないですか。そのバンドは6年間活動したあとに解散して、それでThe Songbardsに入ってシンプルなロックを叩くようになりました」
──地元である神戸のライヴハウス、VARITで4時間ライヴ企画〈The SongBARds〉を始めるようになった経緯は?
松原「VARITの店長が大のビートルズ好きで、そこでまず僕らと共鳴し合う部分があったんですね。で、たまたま空いていた月曜日の時間を有効活用する方法はないか?と一緒に考えていたときに、〈ビートルズがハンブルグ時代にやっていたようなことを、今やったらおもしろいんじゃないか?〉っていうアイデアが出てきて始まったんです」
──ビートルズのハンブルグ時代とは、彼らがデビュー前にドイツのハンブルグで行っていた、武者修行のような下積みライヴのことですね。実際、〈The SongBARds〉でも“Please Please Me”や“You Can't Do That”、“And Your Bird Can Sing”などビートルズのカヴァーを相当やっているようですね。
松原「はい、レパートリーはたくさんあります(笑)。通常のライヴとは差別化するため、4時間ライヴでは自分たちの曲をなるべく控えめにして、カヴァー中心でセットリストを組んでいます。ビートルズにこだわることなく、メンバーはその都度〈いいな〉と思う音楽を混ぜ込みつつ。例えばオアシスや、リバティーンズにストロークス。あと、山口百恵の“さよならの向こう側”みたいな歌謡曲もやったりしています(笑)」
──カヴァーをたくさんしていることが、自分たちの曲作りにもいい影響を与えていますか?
松原「それは絶対ありますね。今の僕らには〈まったく新しい音楽をやっている〉という意識はなくて。歴史を分断して前衛的なことをやっているわけではなく、先代のミュージシャンたちがこれまでやってきたこと、〈系譜〉を受け継ぐというか。その流れのなかに、自分たちはまだあると思っているんです。なので、音作りの面やソングライティングの部分、コーラスワークを含むアレンジの仕方など、過去の音楽から学ぶべきところはたくさんありますし、影響も受けています」
──きっと、The Songbardsがカヴァーしている曲を聴いて、そこからルーツにあたる音楽へと入っていく人もたくさんいるんでしょうね。
松原「そうだとしたら嬉しいです。実際、僕らのカヴァーを聴いたファンの子から、〈ビートルズのアルバムを借りて今聴いてます〉とか言われることもあって、それはものすごく嬉しいですね」
──ちなみにビートルズは、やはり初期が好きですか?
上野「そういうわけでもなくて、ビートルズは特に中期、アルバムでいうと『Revolver』(66年)や『Rubber Soul』(65年)あたりが好きなんです。でも、〈いちばん好きな曲は?〉と訊かれたら“Free As A Bird”って答えるかも。なんか、ジョンが生前に残したデモを素材に、残りのメンバーが集まって完成させていくというエピソード込みで好きなんです」
松原「僕のいちばん好きな曲は“Strawberry Fields Forever”なんです。もちろん初期の彼らも大好きなんですけど、後期の方が歌詞に人間味が出てくるというか。さすがに“Strawberry Fields Forever”はカヴァーしてないですけど」
──トッド・ラングレンによる“Strawberry Fields Forever”のカヴァーって聴いたことあります? 結構ギター中心のアレンジで、4人編成でも十分できそうだし参考になると思うのでぜひ聴いてみてください。
松原「へえ! ぜひ聴いてみます(笑)。僕ら結構、ビートルズのステージングとか参考にしているところはありますね。メンバーの立ち位置も、ドラムが奥に引っ込まないようにしたり、ヴォーカルを左右に配置したり、今はかなりビートルズを意識しているんですよ」
──作曲者のクレジットを上野さんと松原さんの連名にしているのも〈レノン=マッカートニー〉を意識して?
松原「それはちょっとあります(笑)。実際に今回のミニ・アルバム『Cages In The Room』の制作も、まずは僕と上野で曲のアイデアを持ち寄り、〈ここはこうしたらええんちゃう?〉みたいな感じで曲の土台を作って、それをバンドに投げてみんなでアレンジするという流れでした」
上野「基本的にThe Songbardsの場合は、曲を作ったほうがヴォーカルも取るというスタンスではあるんですけど、例えば今作の“街”という曲は、有志が作ったメロディーを僕が歌ってるんです。そこで歌い回しの細かいニュアンスの違いに気付いて〈ああ、おもしろいな〉ってなりますね」
──なるほど。自分が作った曲を他の人が歌うことで、その曲の新たな魅力に気付くということはきっとあるんでしょうね。
松原「自分で曲を作ると、どうしても自分のなかにあるイメージに凝り固まってしまいがちなんですけど、それを皓平が歌ってくれたり、他のメンバーがそれぞれの解釈で曲にアプローチしてくれることで、曲の持つ奥行きもぐっと広がるし、そうすることで僕らの曲を聴く人への届き方も変わるんじゃないかなって思います」