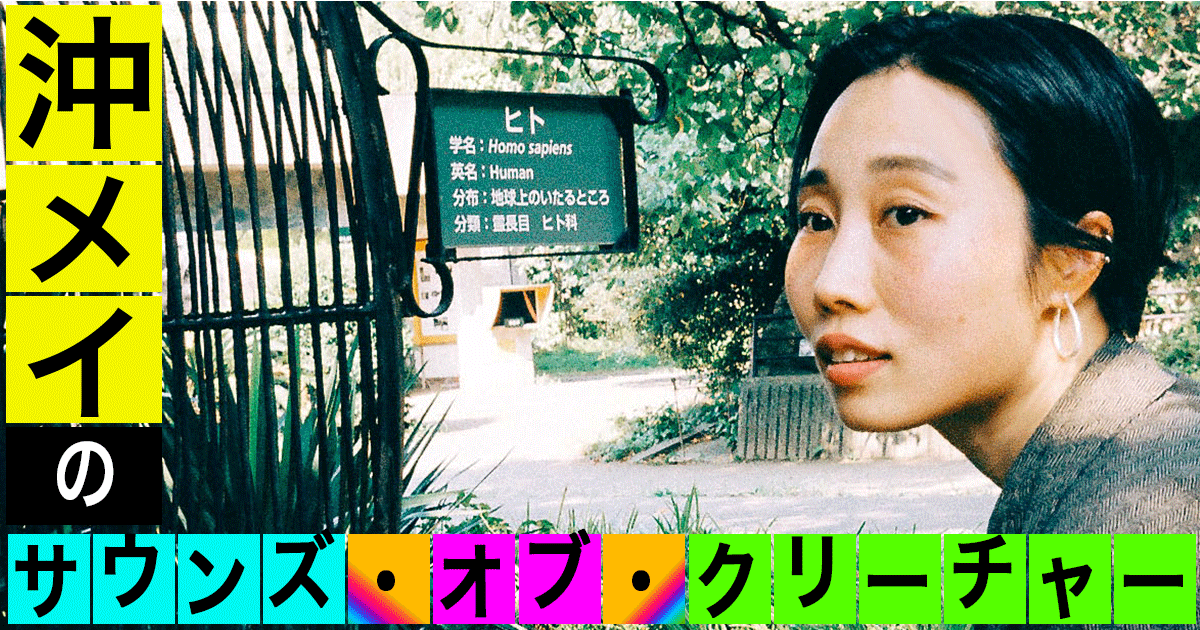沖メイ(Vocal、Synth、Effects)、Yasei Collectiveの松下マサナオ(Drums)と中西道彦(Bass、Synth)で構成されるZA FEEDOのセカンドEP『Passengers』が完成した。〈フューチャリスト・ポリリズミック・トロピカル・バッドアス・フジヤマサウンド〉を掲げ、一筋縄ではいかない変幻自在の世界観を持ち味とする彼らだが、佐瀬悠輔(Gentle Forest Jazz Band、Nao Kawamura)、小西遼(CRCK/LCKS)、吉田悠樹(NRQ)らも参加した新作では、沖の歌声を生かしたポップ・フィーリングも全面に。彼らならではのエクスペリメンタルでプログレッシヴなポップ・アルバムとなった。
同作に先駆けてリリースされたのが、沖とも交流のあるシンガー・ソングライター、Nao Kawamuraの『Kvarda』だ。過去2枚のEP(『Cue』『RESCUE』、共に2017年)ではジャズ~ネオ・ソウルのフィーリングも漂う独自の世界を展開していたが、初のフル・アルバムとなる本作では、ジャンルを楽々と越えるスケール感の大きさを遺憾なく発揮。ネイ・パームなど新時代ソウルの歌い手たちとの共通点も指摘されてきた彼女だが、初期の荒井由実作品などにも影響を受けてきたという自身の土台も透けて見える作品となった。
今回は、共にバンドを率いて自身の表現を追求するフロントウーマンである沖と、Nao Kawamuraの対談を企画。自分に深く向き合いながら、〈ポップ〉の領域を拡張し続けている彼女たちは現在何を歌おうとしているのか。互いにシンパシーを覚える2人の会話だけあって、その内容は両者の音楽観の根本に触れるディープなものとなった。
音楽に感動する時って、作り手の意図が伝わる時だと思う
――2人が初めて会ったのは?
沖メイ(ZA FEEDO)「去年の6月ぐらいだと思いますね。でも、その前からもちろんNaoちゃんのことは知ってて」
Nao Kawamura「私も知ってた(笑)。おもしろそうなことをやっている界隈をざっと調べたことがあったんですよ。それでまずものんくるのことを知って、その周りの人たちの音楽も聴くようになったんですけど、ZA FEEDOもその頃に知りました」
メイ「私がNaoちゃんのことを知ったのは『Cue』(Nao Kawamuraの2017年のEP)が出た頃だったかな。Suchmosのコーラスをやってるということがきっかけで、実際に会ってみたら共通の友人も多くて。初めて対バンした時※はビックリしましたね。この人、ステージ上でめっちゃ動くんですよ(笑)」
Nao「(爆笑)」
メイ「しかもすごく高いヒールを履いて。アー写ではスッとしたクールなイメージだったから、それを覆すような、エネルギーのほとばしるその姿がめちゃくちゃ格好良かったんです」

――Naoさんは、その時のZA FEEDOのステージを観てどうでした?
Nao「曲の展開がおもしろかったし、〈新しさ〉を感じました。あと、音源を聴いた時はクールなイメージがあったんですよ。MCもしない感じというか。そうしたら、実際のメイさんはすごく可愛いし、クールなだけじゃないなと思って」
――今回の対談はメイさんからのリクエストでしたが、Naoさんに対してシンパシーを感じていた?
メイ「そうなんです。初対面の時から何かを感じてて。先日あがっていたNaoちゃんのインタヴュー記事も読んだんですけど、音楽に対する姿勢が自分と似てると思いました。作品を作るうえで自分の既存の引き出しだけじゃなく、一回ゼロに戻してからまた新たに蓄積して生み出そうとしているところに共感しました。私も今作ではそういう作業をしたので、インタヴューを読んで〈似ておる!〉と(笑)。今風のものをただなぞるのではなく、それを自分の表現のなかに落とし込みつつ、〈Nao Kawamura〉というものを確立しようとしているところも格好良いなと思いました」
Nao「SNSで『Passengers』の制作中だったメイさんの投稿を見てて、〈今のメイさん、辛いヤツだ!〉と思ってましたよ。一度ゼロに戻ってフラットな状態になるのって……ホント辛いんだよ(笑)!」
メイ「辛いよね!」
Nao「結局、自分のなかにしか答えがないし、それを提示しないとバンド・メンバーも動けない。ZA FEEDOは曲作りもメイさんがやってるんでしょ?」
メイ「うん、自分でやってる。私がしっかり目のデモを作って、みんなとああだこうだやりながら形にする感じ。今回は6曲目の“ここから”で吉田(悠樹)さんが弾いてくださった最高の二胡が入ってるんだけど、あれはデモの段階から二胡ありきの曲だったので、どうしても本物の音を入れたくて……」
Nao「あの曲で二胡が入ったことへの共感がすごくあって。実は私の今作のいちばん最後の曲(“Outro”)もデモでは二胡を入れてたの。最終的に外しちゃったんだけど、(ZA FEEDOのアルバムに)入っててビックリしちゃって」
メイ「えっ、ホント? すごいね!」

――そのほかにお互いに共感するポイントはありますか?
メイ「Naoちゃんはソロ名義だけど、常に同じメンバーでやっているところに共感がありますね。例えばR&B~ソウル系のシンガーってバックのメンバーがどんどん変わっていくことが多いイメージなんですけど、Naoちゃんはいつもの仲間と制作して、バンドサウンドを鳴らしている。これまでのソロ・シンガーのスタイルを一新する存在だと思うんです。私、この世にあたり前のことなんてひとつもないって思ってるので、常に何にでも驚きたいんです。そういう意味でNaoちゃんに出会えたのはホントに嬉しい驚きでした」
Nao「ソロもバンドもあまり関係なくて、私の場合は〈Nao Kawamura〉という名前が前に出るし、メイさんの場合は〈ZA FEEDO〉というバンド名が出る。それだけの違いだとは思いますね。 あとは作品を作るうえで意志が誰のどこにあるのか、ということがいちばん大事かな」
――では、固定のメンバーだからこそできることとは?
メイ「前作『2772』は、それまでの活動のなかで出来た曲をまとめたものだったんですね。熟した曲を世に送り出す、活動の碑みたいなものだったんです。でも、今回は6曲中4曲はまだライヴで演奏したことがない曲で。そういうこともあって、限られた時間のなかでバンドの全員が納得できる曲を作ることがすごく辛くて、しんどさのなかにすごい楽しさがある作業でしたが。やっぱりみんなそれぞれいろんな意見があって、バンドが成り立っているから」
Nao「そうだよねえ……」
メイ「今回は、制作するうえで意見のぶつかり合いが何回かあったんですよ。でも、それって制作の現場ではすごく健康的なことだと思っていて。〈この人たちとじゃないと作れない〉という気持ちをみんなが共有して今まで活動してきたからこそ、そういうことができるんだと思います。だから、『Passengers』はこのメンバーでしかできないやり方で作った作品なんです。そこに向かって絞り出していくのはすごく楽しかったし、そういうやり方で作れて良かった」
――なるほど。では、その『Passengers』の話に移りましょうか。Naoさんは聴いてみていかがでした?
Nao「そうですね……良い意味での〈日本人らしさ〉みたいなものを感じました。メイさんの声が大きいからかな? この歌を海外の人が歌うとこんなふうにはならないと思う。二胡もそうだし、いろんな音が入っていて音作りもおもしろかったし、前のEPよりもポップになった感じがしました」
メイ「そうなの、ポップになったんです!」
――メイさんは今回の制作にあたってNaoさんのおっしゃった〈日本人らしさ〉を意識した部分はあるんですか?
メイ「意識しているわけじゃないけど、バンド全体として考えていることはあります。例えば、今格好良い音楽って国内外にたくさんあるし、自分たちもよくチェックしてるけど、それをまるまるなぞって自分の音楽とするのは違うなって。音楽に感動する時って、その音像はもちろんだけど、やっぱり作り手の意図が伝わる時だと思うんです。遊び心とか、新しさとか。時代が望む音や形式が溢れているなかで、そこにすんなりいかない魅力というか。要するにちょっとヒネくれたものが好きなんですね(笑)」
Nao「まあ、そうだよね(笑)」
メイ「格好良いと思う音楽から影響されるとしても、自分の思いをきちんと反映しないとおもしろくないと思うんです。私たちは日本人だから、日本人らしさも自然と加わるんだと思いますね。あと私は民族音楽が大好きなんですけど、そういう要素も自然に表れているのかもしれない」
Nao「それは感じた! “You will be there”の頭の不思議なフレーズとか」

――あのフレーズ、民謡の舟歌みたいですよね。〈エンヤートット〉的な。
メイ「なんであのフレーズが出てきたのかは自分でもわからないんですけど(笑)、以前、山下達郎さんの“ピンク・シャドウ”※をソロでカヴァーする機会があって、この曲はそのアレンジを持ってきたんです。だから、“ピンク・シャドウ”オマージュな歌詞もちょこちょこ入っているんです」
※オリジナルはブレッド&バター
――以前、Mikikiで行なった取材でメイさんは〈日本人だから黒人っぽい雰囲気はなかなか出せないし、声を太くしようとしても不自然になっちゃうし、どうしたらいいんだろうと思って〉という話をされてましたよね。Naoさんのおっしゃる〈日本人的な表現〉と繋がる話でもありますよね。
メイ「うん、そうですね」
Nao「海外の人とは身体の骨格も生活も違うから、違う歌になるのは当然だと思うんです。そこでせめぎ合った時に生まれる違和感が日本人なりの音楽になるし、今回の(ZA FEEDOの)EPにはそれが出てると思う。私も自分の作品を作りながら、そんなことを考えてるんですよ。英語じゃないと合わないメロディーもあるけど、そこに日本語を乗せることによって、誰もやっていない音楽になる。だから常に実験してるみたいな感じかな?」
メイ「うん、実験だね。〈音のラボ〉みたいな感じだよね。大学時代にジャズ・ヴォーカルをやっていた頃、暗黙の了解で〈声が太くて声量がある歌が良い〉とされていたように感じてたことがあって。エラ(・フィッツジェラルド)とかアレサ(・フランクリン)みたいに歌えたほうがいい、って……」
Nao「無理に決まってんじゃん(笑)」
メイ「そうなんだよね(笑)。エラもアレサも大好きなんだけど、私は彼女たちじゃないから絶対無理だし、真似しようとしてもそれは自分の歌にならないってことに気付いて。それで本当の意味で〈自分らしいスタイル〉に自信を持てるようになって、自分が続けてきたスタンスが間違ってなかったと感じられるようになっていきました。ノウアー(Knower)とかSMQ(スティーヴ・マックイーンズ)とか海外ミュージシャンと共演して仲良くなったことも大きいですね。続けるって本当に大事」
――さっきNaoさんがZA FEEDOの音作りについて話してましたが、音作りはどうやって進めているんですか?
メイ「デモの段階ではバンドでやることを想定しつつも、かなり重ねた音源を作るんです。もう〈オーケストラか?〉っていうくらいの。それをみんなで聴いて、音の取捨選択をしていくんです」
――そのプロセスのなかで、さっきお話しされたような意見のぶつかり合いがある、と。
メイ「そうですね。激しくぶつかるというか、腹を割った話し合いですね。私の場合デモの段階で作り込みすぎちゃうことによって、私のなかに確固たる世界観が出来上がってしまうので、みんなの意見をスムーズに飲み込めない葛藤があって。デモ通りにやりたいわけじゃないんですけど、〈そこ削ると変わっちゃうんだよなあ……〉とか。でも全部そのままやりたいんだったらソロでやればいいわけで。そんななか、みんなでいろいろ実験して音を作って行きました。私にとっても、みんながやりたいことを実現できないと意味がないので、本当によく話し合っていろいろ試しました」
Nao「なるほどね。そこは私とちょっと違うかも。私の場合、私か(プロデューサーである)澤近(立景)のどちらかがベーシックの部分を作って、そこからアレンジを詰めていくんだけど、あくまでも決定するのは私か澤近。澤近と2人の間ではいろんなやりとりがあるんだけど、メイさんの場合はそれを何人ともやってるんでしょ。私にはそれができなかったから、今の形態になってるんです。 より自分のやりたいことを表現するために、委ねるべき所と確固たるものの線引きをまずする。 意見は人数の分だけ当然分かれてくるものだから、着地点が見えなくなっちゃう し 。だからメイさんは大変だと思う(笑)」
メイ「うん、楽ではないかな(笑)。私とやってて、メンバーも大変だと思う(笑)!」
Nao「私の場合、澤近とのアイデアが固まったら、それを澤近が各メンバーに伝達してくれるんです」
メイ「おもしろいね。会社組織みたい」
――ZA FEEDOの場合はそこまで組織的に作られているわけじゃなくて、メンバーひとりひとりと向き合っていく、と。
メイ「そうです。ただ、話し合いで二択か三択で決めなきゃいけない時とかは〈これでよし!〉という最終判断は私がすることが多いですね。一応リーダーなので!」
――今回のEPについて〈ポップにした〉とおっしゃってましたけど、そういう意識は初めからはっきりとあった?
メイ「ポップにしようというか、ありのままにしようと思ったんです。今までは〈とにかくかっこよくしよう!〉とか音像重視だったんですけど、今回はそれプラス、自然な形で自分の経験や思想、嗜好性を表現する要素も入れたかった。それをメンバーと共有した結果、自然とポップなものになっていったんです」
――なるほど。
メイ「あと、一つ大きかったのは、ここ最近のZA FEEDOのライヴがエネルギッシュな爆音になっていて。私も大きな声で歌うようになっていたんですけど、力でねじ伏せるみたいな歌い方は本来自分が見せたいものと違うし、そういうのはなりたい自分じゃないと感じて。それで、今作のレコーディングにあたっては、自分もメンバーもそのままのものを作りたいと考えてたんです。力で押さなくても、このメンバーなら何やっても必ず格好良くなるから、とそういうことをみんなで話して、共有したうえで作っていったことが大きかった」