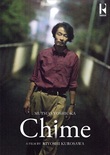黒沢清がヴェネツィア国際映画祭で銀獅子賞(監督賞)を受賞した、というニュースがこの国を駆け巡ってから数週間、〈世界のクロサワ〉という言葉をよく聞くようになった。ここ最近は、「パラサイト」のポン・ジュノや「ミッドサマー」のアリ・アスターが〈クロサワ〉のファンであることを公言している。黒沢ファンの私は〈あったりめえよ!〉なんて思うのだけれど、それと同時に、世界三大映画祭で主要賞を受けるのは初めてのことだから、〈世界がようやくクロサワに追いついたのだ〉という感慨もある。「スパイの妻」は、そんな〈世界のクロサワ〉の時代の到来を告げるにふさわしい映画であり、マスターワーク(名人の仕事)と呼びたい作品だ。
映画はおそろしい――黒沢清は、インタビューでそのように何度も何度も語っている。なぜなら、映画は人生を変えてしまうからだ。「思えば、私の人生を多少なりとも変えなかった作品などありはしないのだから、全ての映画はつまりホラー映画なのだ」(「映画はおそろしい」)。映画を観たからこそいまの黒沢清がいるのであり、つまり、いまの黒沢清というのは映画によって変えられた存在である(〈私はただの映画好きにすぎない〉というのも黒沢の常套句だ)。
「スパイの妻」は、〈映画はおそろしい〉ということを言っている映画である。正確には、そういうこともひとつのテーマとして持っている映画だ。「スパイの妻」には、9.5ミリ・フィルム(黒沢の映画監督としてのキャリアのスタートは、8ミリ・フィルムで撮った映画だ)とその映写機、さらにスクリーンに投影される映画そのものがたびたび登場する。そして、決定的なものを記録したフィルムをめぐって、個人(〈スパイ〉とその妻)と体制(国家の使いである憲兵たち)とが次第に激しく対立し、体制側による捕物が展開されていく。「スパイの妻」の登場人物たち――福原聡子(蒼井優)と優作(高橋一生)、津森泰治(東出昌大)は、そのフィルムに運命を翻弄される。ある者はフィルムにより(宮台真司が言うところの)〈覚醒〉し、またある者はフィルムが原因で物語の終盤に正気を失ってしまう(ように見える)。たった一巻のフィルムが人々の人生を、さらには国家の体制を揺さぶる。映画はおそろしい、というわけだ。
個人と体制、と書いた。「スパイの妻」は、すでに黒沢がさまざまな場所で語っているとおり(そして映画を観ればわかるとおり)、二者の対立が物語にダイナミズムをもたらしている。個人を聡子が、国家の体制を泰治が、さらに2つを止揚した存在を優作(〈コスモポリタン〉を自称する)がそれぞれ代表しており、彼らの三つ巴の、社会における公的な立場と私的な情念とが絡まり合った三角関係のドラマとして「スパイの妻」は展開する(そして、その媒介になるのがフィルムであることは言うまでもない)。
そもそも、55年生まれの黒沢は、学生運動で中心的な役割を担った団塊の世代への違和感を抱えながら映画を撮ってきた。個人と体制(あるいは、社会)との緊張関係に、常に慎重に接してきた作家なのだ。体制に吸収されるのでも、反体制というセクトに絡めとられるのでもなく、個人や、個人と個人がなすコミュニティーについての物語を黒沢は撮ってきた。いっぽうで、そのテーマは通底音のようなものであって、これまでわかりやすく示されてこなかった。今回、濱口竜介と野原位が中心になって書いた脚本によって、〈個人と体制(社会)〉というテーマがくっきりと浮かび上がっていることに、まず驚かされる。
映画は、風のざわめきとともに幕を開ける。ファースト・カットは、いかにも黒沢清的なロング・ショット。ほかにもシンメトリーな構図、思わず見惚れてしまう強烈なショット、カメラがずいずいと動きながら俳優たちの動きを追いかける緊張感あふれる長回しなど、〈ああ、黒沢清の映画だ〉という演出とディレクションが「スパイの妻」を満たしている。映画の後半、軍隊の隊列がざっざっと行進しながらセットをぐるりと周る動きを背景として捉えたシーンからは、Vシネ時代の異色作「勝手にしやがれ!! 英雄計画」(96年)の強烈な長回しを思い出さずにはいられない。
どこまでも黒沢の筆致を感じさせながら、しかし「スパイの妻」がこれまでの黒沢映画と異なる質感を持っているのは、なぜだろうか。それはやはり、濱口と野原が脚本を書いていることによるものだろう。戦時下という時代もの、舞台は神戸、さらにどろどろの三角関係の物語であることをトリガーとして、「スパイの妻」はこれまでにない黒沢映画として立ち上がっている(現代の東京を舞台に映画を撮ってきた黒沢は、強烈な愛憎や執着、性愛の関係性を描くことを苦手にしてきたと言える)。だからこそ、とにかくシリアスなのだが、そのいっぽうで〈コメディ作家〉(蓮實重彦)たる黒沢の個性も、映画の後半で頭をもたげる。ぴんと張り詰めた空気感とずっこけぐあいが、なんともおかしな塩梅なのだ。
俳優たちの演技が熱気を帯びていることにも度肝を抜かれた。早撮りで有名な黒沢は、俳優の演技がそれほど熟さないままに、ぱっぱっと撮ってしまうらしい(それには、ひとつのカットにうん百テイクも重ねていた相米慎二の演出への反発もあるようだ)。それゆえ、黒沢映画の俳優たちは独特の冷めたムードをまとっていたが、「スパイの妻」では蒼井、高橋、東出の三者による個々の演技とそのアンサンブルが、とんでもなく高度な領域に達している。彼らの俳優としての身体能力の高さ、濱口と野原の脚本、そして黒沢のディレクションの3つが理想的なかたちでかみ合った結果だろう。
くわえて、長岡亮介(ペトロールズ/東京事変)による音楽もすばらしい。黒沢映画の音楽といえば、Vシネ期や「CURE」(97年)などの時代を担ったゲイリー芦屋の、ユーモアと不穏さを両立させたスコアを思い浮かべる。ひょうひょうとした芦屋の音楽とくらべて、長岡の音楽はかなりシリアスでヘヴィーではあるが、「スパイの妻」の物語と見事に調和している。正直に言って、大友良英と江藤直子による「岸辺の旅」(2015年)の劇伴に飽き足りないものを感じていただけに、その点はとてもよかった。今後も長岡とのタッグに希望が持てる、と思った。
美しくも痛ましいラスト・シーンは、濱口が強く意識したという「CURE」へとつながっていくようにも見える(そして、「回路」との共振も)。しかし、それ以上に、「ミッドサマー」の壮絶な最後に重なったことにこそ、はっとした。その思いもよらない不思議な偶然に、〈世界のクロサワ〉の時代がようやく2020年にやってきたことを、たしかに感じるのだった。お見事です!
FILM INFORMATION
スパイの妻〈劇場版〉
監督:黒沢清
脚本:濱口竜介/野原位/黒沢清
音楽:長岡亮介
出演:蒼井優/高橋一生/坂東龍汰/恒松祐里/みのすけ/玄理/東出昌大/笹野高史
配給:ビターズ・エンド
配給協力:「スパイの妻」プロモーションパートナーズ
(2020年/日本/115分/1:1.85)
全国公開中
©2020 NHK, NEP, Incline, C&I