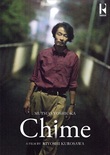往年のハリウッド映画の記憶が蘇るなか、ゼロから構築されるフィクションの魅惑。
新作「スパイの妻」は、中国との泥沼の戦争に加えアメリカとの開戦も間近に迫る1940年の日本が舞台の〈時代もの〉である点だけでも、これまでのフィルモグラフィのなかで異彩を放つ。
「ある時代を忠実に再現することの難しさもありましたが、僕だけでなくすべてのスタッフが、フィクションの世界をゼロから構築していく緊張と充実感を撮影中ずっと保てたことが楽しく、ワクワクさせられる経験でした。いつものように、現実はこうなんだから、しょうがないよな、とカメラを回すのではなく、現実を作ってしまう。皆でわいわい言いながら進む映画作りの原点に戻る感じでした。衣装についても、どう調べてもそれが正しいという保証はない。当時の服の型を使いながらも色彩などの点ではなんでもありと考え、すべて作ってしまう。ただ、僕が提案するうえでの基準は、どうしても往年のハリウッド映画になってしまいます。結局、〈映画っぽい〉が判断の決め手になる。ハリウッド映画の記憶を胸に現代においてドラマを撮る。単なる映画好きなわけですが……」
理想的な夫婦と映る男女の関係性の揺らぎや亀裂を次第に浮き彫りにする物語が、歴史・政治的な揺らぎや亀裂とそのまま重なることに息を呑む。軍事統制下の日本にあっても自由な生き方を追求する夫と、彼を愛しながらも従順な愛国主義を放棄できずにいる妻……。少なくとも近年の日本映画で歴史・政治的な背景をここまで重視するメロドラマを見たことがない。
「確かに、こんな映画、あまり日本で見たことがない、でも、ヨーロッパあたりでは定番なんだよな、と濱口竜介と野原位が書いたプロットを読んで感じました。愛し合っているのに騙し合ってもいるというプロットなんて僕自身はなかなか思いつかない。ただ、歴史的なものをベースにしている分、物語をどこで終わらせるかで悩みました。純粋なメロドラマやサスペンスであれば、しかるべき終わりが設定できますが、歴史にはまだ先があり、空襲や終戦が続く。特殊な歴史背景をもつ物語であるがゆえに、純粋なメロドラマやサスペンスでは語り尽くせない部分が出てくる。どの終わり方が正しかったのか、今でもよくわかりません」