
今年75歳を迎えるポール・サイモンが、5年ぶり通算13枚目のニュー・アルバム『Stranger To Stranger』をリリースした。現代の背景を歌い、スリリングなサウンドが響き渡る本作には、ボビー・マクファーリンやジャック・デジョネットといった大物ゲストと共に、ストレンジなベース・ミュージックを手掛けるクラップ!クラップ!や、ビョークも信頼する天才作曲家のニコ・ミューリーといった気鋭の音楽家たちも参加。そのリズミックなフィーリングと挑戦的な姿勢は、ソロとしての代表作『Graceland』(86年)を彷彿とさせる。NYを代表するソングライターが、長いキャリアを経て辿り着いた境地とは? 音楽評論家の高橋健太郎氏に、〈現在進行形のポール・サイモン〉の凄みを紹介してもらった。 *Mikiki編集部
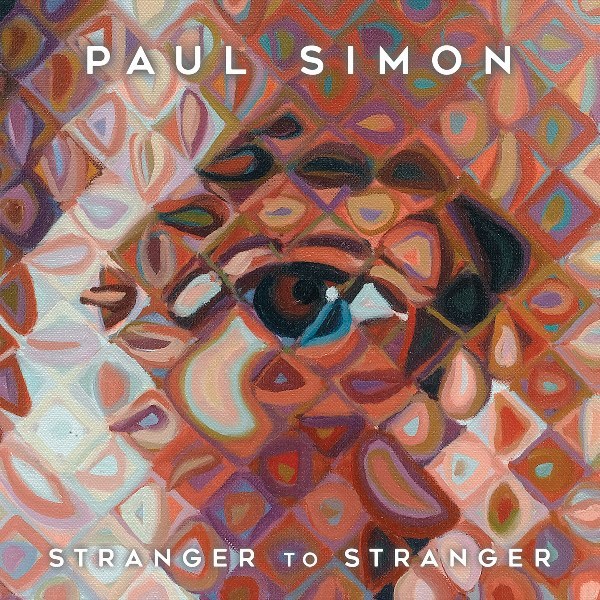
サイモン&ガーファンクル時代からの旧友、ロイ・ハリーとの再会が意味するもの
1941年10月13日生まれのポール・サイモンは74歳になっている。思えば、僕が彼の音楽に出会ったのも半世紀近く前のことだ。中学生の時に買った最初のレコードがサイモン&ガーファンクルの7インチだった。だが、そんな長い付き合いのヴェテランの作品だというのに、ソロ・アルバムとしては13枚目になる新作『Stranger To Stranger』は、僕をリラックスはさせてくれない。70代半ばにして、こんな攻めた作りのアルバムを差し出してくるポール・サイモンに僕はたじろぎ、しばらく言葉を失い、空を見上げてしまった。
もっとも70代半ばにして、などと言ったら、このアルバムを共に作り上げたポール・サイモンのパートナーに叱られるかもしれない。『Stranger To Stranger』の共同プロデューサーは、なんとロイ・ハリーである。そのクレジットを見つけた瞬間にはわが目を疑った。引退して久しいロイ・ハリーは今年で82歳になるはずだ。
と言っても、彼のことをご存じない読者もいるだろうから、簡単に説明しておこう。ロイ・ハリーは60年代からコロムビア・レコードのハウス・エンジニアとして、数々の名盤を手掛けてきた伝説的な人物だ。NYのロング・アイランド出身で、50年代終わりにCBSに入社。CBSテレビの仕事を経て、コロムビア・レコードに移り、60年代半ばからレコーディング・エンジニアとなった。エンジニアとして経験した最初のセッションがボブ・ディランの“Like A Rolling Stone”(65年)だったというから、そのキャリアは最初から伝説と共にあると言ってもいい。
ローラ・ニーロ『New York Tendaberry』(69年)やブラッド・スウェット&ティアーズ『Child Is Father To The Man』(68年)などもロイ・ハリーのコロムビアでの代表的な作品に数えられるが、もっとも関わりが深かったのは言うまでもなくサイモン&ガーファンクルだ。なにしろ、オーディション時のデモ録音を行ったのが当時はエンジニア見習いのハリーだったという。契約後、アート・ガーファンクルがオーディション時のエンジニアと仕事したいと希望し、以後ハリーはサイモン&ガーファンクルのほぼすべての作品にエンジニア/プロデューサーとして関わることになる。〈サウンド・オブ・サイレンス〉も〈ミセス・ロビンソン〉も〈明日に架ける橋〉も、もちろんハリーの仕事だ。『Stranger To Stranger』でポール・サイモンは、そんな彼のキャリアの最初期からの共同プロデューサーを呼び戻したのだった。
ハリーはポール・サイモンの最初のソロ作『Paul Simon』(72年)でも共同プロデューサーを務め、83年の『Hearts And Bones』や86年の『Graceland』、90年の『The Rhythm Of The Saints』にも貢献した。グラミー賞の最優秀アルバムに輝いた『Graceland』は、ポール・サイモンのもっとも成功したソロ・アルバムに数えられる。とはいえ、そんなポール・サイモンとハリーの蜜月期もすでに4半世紀以上前のこと。引退生活を送っていた80代のハリーを引っ張り出して、ふたたびアルバムの共同プロデューサーに迎える日が来るとは、誰が想像しただろうか。しかし、他の選択肢は考えられないほどの理由をサイモンは抱いていたに違いない。
そのことを考えるには、2011年の前作『So Beautiful Or So What』を振り返る必要がありそうだ。ポール・サイモンが創造意欲の衰えぬソングライターであることを示し、セールス的にも復活作となった『So Beautiful Or So What』は、サイモンのキャリアにおけるもう一人の重要なエンジニア/プロデューサー、フィル・ラモーンと再会を果たした作品でもあった。75年にフィル・ラモーンを共同プロデューサーに迎えて制作された『Still Crazy After All These Years』(邦題:時の流れに)は、やはりグラミー賞の最優秀アルバムを獲得している。それはポール・サイモンの生み出したもっとも完成度の高いソングブックであり、隅から隅までNYの空気を感じさせる作品でもあった。
ソングライターとしてのポール・サイモンは、20世紀初頭のアーヴィン・バーリンなどに遡るティン・パン・アレーの伝統や、49丁目のブリル・ビルディングに集うソングライターたちの技法を継いでいる。その一方で、彼は世界各地の音楽に興味を向け、新しいサウンド技法にも敏感なレコーディング・アーティストでもあるのだが、こと〈時の流れに〉に限ってはそれを封印。NYのA&Rスタジオで、NYのセッション・ミュージシャンたちと共に洗練されたソングブックを築き上げることに集中した。そういう意味では、南アフリカ共和国に赴いたチャレンジングなプロジェクトである『Graceland』とは対照的なアルバムが〈時の流れに〉だったのだ。
その〈時の流れに〉の共同プロデューサーであるフィル・ラモーンと再会して作り上げた『So Beautiful Or So What』は、アフリカやインドなどのエスニックな楽器があしらわれたり、サンプリングが使われたりはするものの、基本的にはソング・オリエンテッドなアルバムだった。サイモンはすべての曲をギターで作曲したそうで、その原点回帰なソングライティングの湛えるクォリティーが多くのリスナーを振り向かせ、ヒットに繫がったと言ってもいいだろう。
しかし、2年後の2013年にフィル・ラモーンは他界する。ポール・サイモンがもう一度ハリーと仕事することを熱望したのは、そのフィル・ラモーンの死の影響もあったのではないだろうか。互いの年齢を考えれば、一緒にスタジオに入ることのできる最後のチャンスなのは明らかだった。そして、『Graceland』の時と同じように、目の前にはハリーの手を借りたいチャレンジングなプロジェクトがあった。そうして生まれたのが、この『Stranger To Stranger』ではないかと思える。

古の現代音楽と最先端のトラックメイクが同居したニュー・アルバムの音世界
アルバムは冒頭の“The Werewolf”から聴き慣れないサウンドが飛び出してくる。イントロに聴こえる大きくピッチベンドする楽器音は、インドのゴピチャードという楽器だという。以後、アルバムには数え切れないほどの風変わりな楽器音が散りばめられていく。そのインスピレーションの源となったのは、2013年にハリー・パーチのオリジナル楽器に触れたことだったらしい。ハリー・パーチは20世紀のアメリカの現代音楽家で、平均律の12音階の限界を打ち破るべく、マイクロトーナルと呼ばれる43微分音階を提唱したことで知られる。1930年代にマイクロトーナルを使用した作曲を始めたパーチは、それを演奏するためにさまざまなオリジナル楽器も製作した。
『Stranger To Stranger』のための作曲に取り掛かったポール・サイモンは、最初の1曲(11曲目に収録された“Isomaniac Lulaby”)の作曲中に、ハリー・パーチのマイクトーナルの可能性に興味を惹かれ、ニュージャージーのモントクレア州立大学に研究者のディーン・ドラモンドを訪ねたのだという。大学にはパーチの製作したクロームロデオン、ハーモニック・キャノン、クラウド・ボウルズといった楽器があり、サイモンはドラモンドの協力を得て、持ち込んだ録音機材にそのサウンドをサンプルした。このセッションは2013年2月に行われ、ドラモンドによる楽器演奏も収録されたが、その2か月後(フィル・ラモーンの死の3週間後)、ディーン・ドラモンドは他界した。
ちなみに、ハリー・パーチについては、ベックが2010年に彼に捧げる“Harry Partch”という曲を発表。この曲はマイクロトーナルな(何も知らずに聴けば、ピッチが狂っているとしか思わないような)サウンド・コラージュで構成されていて、ジョー・ミークを思い起こさせるようなレトロ・フューチャーな雰囲気のサウンドでもある。2009年にはレディオヘッドが“Harry Patch (In Memory Of)”という曲を発表しているが、こちらは音楽家のハリー・パーチとはまったく関係がない。
また、現代のミュージシャンでマイクロトーナルに積極的に取り組んでいるミュージシャンには、上原ひろみのHiromi’s SonicBloomにも参加しているNY在住のギタリスト、デヴィッド・フュージンスキーがいる。フュージンスキーはレギュラー・チューニングのギターを使いながら、細かなグリッサンドやベンドを織り交ぜて、アジアや中近東の楽器が奏でるような微分音階を生み出している。今年発表された新作『Flam! Blam! Pan-Asian MicroJam!』もタイトル通り、マイクロトーナルな奏法を縦横に使った内容だ。ギタリストであるポール・サイモンがマイクロトーナルに興味を惹かれたきっかけに、フュージンスキーの演奏があっても不思議はないように思われる。
“The Werewolf”に話を戻すと、そのリズムはハンドクラップとさまざまなパーカッションが折り重なったポリリズミックなビートで構成されている。これはサイモンのグループのパーカッショニスト、ジャメイ・ハダドとボストン在住のフラメンコ・グループのセッションから生まれたものだという。が、同時にこの曲にはイタリアのトラックメイカー、クラップ!クラップ!も参加している。
クラップ!クラップ!は2014年のアルバム『Tayi Bebba』で注目された、本名をクリスティアーノ・クリッシというソロ・アーティストで、アフリカ音楽などのリズム・テイストを入れたドープなトラックが日本でも人気を呼んだ。ポール・サイモンは23歳の息子のエイドリアンから、彼のことを教えられたそうだ。“The Werewolf”のサウンドから判断すると、セッション演奏からリズム・トラックを抽出し、エレクトニック・ドラムなどを加えつつ、全体を構成したのが、ここでのクラップ!クラップ!の仕事と思われる。フラメンコ・グループのハンドクラップに心惹かれていたポール・サイモンは、それを息子の聴いていたクラップ!クラップ!のエレクトロニクスと組み合わせたらおもしろいと、直感的に思ったのかもしれない。
後半にはギターやオルガンも聴こえるものの、歌を支えるコード楽器のようなものは見当たらず、“The Werewolf”のサウンドは無骨と言ってもいい。これは2曲目以降の多くの曲にも共通する。その点だけを取っても、ギターがもっとも重要な楽器だった前作と本作はまったく違った志向性が感じ取れる。ポール・サイモンは〈サウンド自体がこのアルバムのテーマだ〉と語っているが、この〈サウンド〉は多分に音響的、あるいは非器楽的なものを指すと考えて良いだろう。通常の楽器の音階に囚われない、パーカッシヴで時にはノイジーなサウンドにサイモンの興味が向いていたのは間違いない。
フラメンコ・グループの演奏が使われたのは4曲、クラップ!クラップ!の参加は3曲に過ぎないが、冒頭の2曲が彼らとのコラボレーションなので、そのリズミックなフィーリングがアルバム全体を支配しているようでもある。例えば、6曲目の“In A Parade”には両者は参加していないが、パーカッション主体のサウンドは冒頭2曲のそれを継承している。一方で、2曲のアコースティック・ギター・インストゥルメンタルはあるものの、サウンドに占めるギターの比重は明らかに低い。7曲目の“Proof Of Love”は2014年のブラジル滞在経験をもとに書かれたという曲で、6/8拍子のギター・アルペジオに乗って歌うポール・サイモンの姿を見ることができるが、それはアルバム中では稀な光景だ。ギターのまったく聴こえない曲やギターらしからぬギター・サウンドが聴こえてくる曲のほうが多い。こんなポール・サイモンのアルバムを手にしたのは初めてだ。
サイモンがロイ・ハリーを引っ張り出した最大の理由は、彼の頭の中で沸騰していたそんなサウンドのアイデアを整理してくれる人間が必要だったからに思われる。90年のアルバム『The Rhythm Of The Saints』で、ハリーがパーカッシヴなサウンドに洗練された空間処理を与えていたことも思い出されたのだろう。現代のスタジオから遠ざかっていたハリーはプロトゥールスを操作できないため、実際のエンジニアリング作業はアンディ・スミスの助けを借りて行われた。しかし、ミックスのクレジットはハリー一人だ。ハリーなら何とかしてくれる。そう信じて、サイモンはインポッシヴルなサウンド・アイデアをハリーに手渡し、そこからシンガー・ソングライターに立ち戻って、アルバムを完成させることができたのかもしれない。
というのも、このアルバムで改めて思い知るポール・サイモンの凄みは、かくも実験的なサウンドに振れても、まったく揺るぎないソングライティングの完成度にあるからだ。その点においては、前作『So Beautiful Or So What』と同様に隙がない。あるいは、サウンドからインスパイアされて、手慣れたレヴェルには終らない言葉とメロディーがどっと湧き出てきたのかもしれない。〈ミルウォーキーの男は普通に暮らしていた。普通の妻がいた。彼女は彼を寿司包丁で殺した〉と歌い出される“The Werewolf”(=狼男)の始まりからして、彼の短編小説的なソングライティングの真骨頂を感じさせる。
タイトル曲“Strenger To Strenger”では〈words and melody〉という言葉が何度も繰り返される。その響きの中には、古典的なアメリカン・ソングライターとしての矜持が満ちているかのようだ。世界各地の音楽に興味を向け、新しいサウンド技法にも挑戦し続けるレコーディング・アーティストでありながら、その古典性は決して譲らないのがポール・サイモンなのだ、というのはいまさらな気付きかもしれないが。
どこまで踏み込んでもアメリカを見つけてしまう、ソングライターとしての宿命
そういえば、アルバム『Graceland』に関わることで、最近になって知ったことが一つあった。『Graceland』のプロジェクトは85年にポール・サイモンとロイ・ハリーが南アフリカ共和国のヨハネスブルグに赴き、現地のミュージシャンとレコーディング・セッションを行ったところから始まっている。なかでも重要な存在だったのはコーラス・グループのレディスミス・ブラック・マンバーゾで、ムブーベと呼ばれる彼らのコーラス・スタイルがアルバムの印象を決定付ける役割を果たした。そのムブーベは南アフリカ独特の伝統的なコーラス・スタイルであり、アメリカのミュージシャンがそれを採り入れたのだと、僕を含めた世界中のほとんどの人々が信じていたはずだ。
ところが、近年の研究書などを読むと、驚くべきことがわかってしまう。南アフリカのムブーベは19世紀の終わりに生まれたスタイルで、その誕生に決定的な影響を与えたのは、オルフェウス・マクドゥーというミュージシャンだったというのだ。マクドゥーは1858年にアメリカのノース・キャロライナ州に生まれたアフロ・アメリカンで、1890年にヴァージニア・ジュビリー・シンガーズという黒人のミンストレル・ショーを率いて、南アフリカに巡業。翌年まで滞在した。このオルフェウス・マクドゥーのグループが聴かせたコーラス・ハーモニーに触発されて、南アフリカではコーラス・グループが次々に生まれ、それがムブーベと呼ばれるムーヴメントになった。そこから登場したグループの一つがレディスミス・ブラック・マンバーゾだという。
ムブーベの中には、現在の私たちがアフロ・アメリカン的と考えるようなブルージーな要素はほとんどないのだが、それも1890年という時期を考えれば頷ける。オルフェウス・マクドゥーは有名なフィスク・ジュビリー・シンガーズに在籍していたこともあったそうだが、フィスク・ジュビリー・シンガーズの古い録音にもブルージーな要素はない。ブルースという音楽がアメリカの黒人層に浸透していくのは1910年代より後のことだからだ。19世紀のアメリカではバーバーショップ・ハーモニーと呼ばれるアカペラ・コーラスがポピュラーだったが、そのスタイルがムブーベの中では保存されている。
『Stranger To Stranger』の“The Werewolf”でも、ポール・サイモンは一人で多重録音したムブーベ的なコーラスを聴かせている。オルフェウス・マクドゥーに関する史実をサイモンが知っているかどうかはわからないが、いまにして思えば、彼が南アフリカまで行って見つけたそのコーラス・スタイルは、19世紀のアメリカ文化の影響下にあるものだったのだ。皮肉なことだが、しかし、それは『Graceland』の発表時に多くの人が抱いた疑問に答えを与えるものになるかもしれない。アルバム・タイトルの『Graceland』はエルヴィス・プレスリーの生家を指す言葉だった。アフリカ音楽に傾倒した内容のアルバムになぜ、『Graceland』というタイトルを?と発表当時、多くの人が囁いた。だが、実はポール・サイモンは遠いアフリカでアメリカを見つけたのだ、そう考えれば……。
現在行われているアメリカ大統領選の予備選挙において、民主党のバーニー・サンダース候補は、サイモン&ガーファンクルの〈アメリカ〉をキャンペーン・ソングに使っている。その曲の有名なサビ〈I’ve come to look for America〉(僕はアメリカを探すためにやってきた)そのままに、どこへ行っても、どこまで踏み込んでも、アメリカを探し、アメリカを見つけてしまうのが、ポール・サイモンというソングライターの宿命なのかもしれない。そして、『Stranger To Stranger』というアルバムもまた、そんな彼の半世紀以上に渡る旅の果てに生まれた作品であることを強く、深く、感じさせるのである。
































