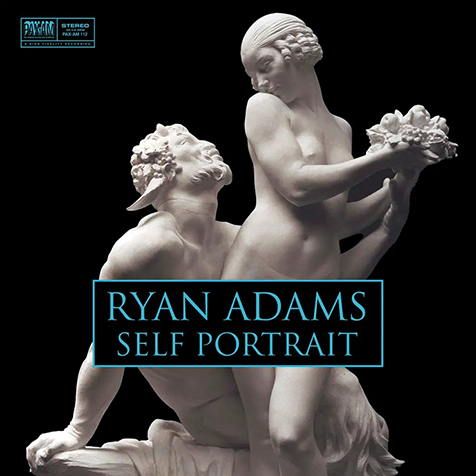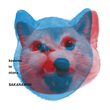現在はパリを拠点に活動するサウンド・クリエイター、三宅純が11月9日(水)~10日(木)にブルーノート東京でライヴを行う。高校時代にジャズ・トランペッターとして頭角を現すと、日野皓正の推薦で76年にバークリー音楽大学に入学し、ボストンやNYで演奏活動を行っている。81年の帰国後は作曲家としてCMや映画、アニメ、コンテンポラリー・ダンスなど多くの作品を手掛けるように。ハル・ウィルナーやピーター・シェラー、アート・リンゼイ、エヴァン・ルーリーなど多くの海外アーティストと交流を育み、アカデミー賞にノミネートされたヴィム・ヴェンダース監督の映画「Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち」(2011年)に主要楽曲を提供するなど、国際的にも高く評価されている。最近では、リオ五輪の閉会式で“君が代”のアレンジを手掛けたことも大きな話題となった。
ジャズやクラシック、シャンソン/キャバレー・ミュージック、エレクトロニカ、南米音楽からブルガリアン・ヴォイスまで――三宅純のサウンドは国境やジャンルはおろか、時間という概念すらも超越したものだ。今回の公演では『Stolen from strangers』(2008年)から、〈記憶を喚起するような音楽〉をテーマにした『Lost Memory Theatre - act-1』(2013年)、〈同 act-2〉(2014年)へと連なる近年の3作を中心に、サウンドトラックを含む代表作からの人気曲も披露される。コスミック・ヴォイセズ合唱団、リサ・パピノー、勝沼恭子といったシンガー陣を擁するほか、(出演予定だった宮本大路が今年10月に惜しくも亡くなってしまったが)付き合いの長い実力派スタジオ・ミュージシャンがバックを務めており、刺激的なパフォーマンスが繰り広げられるのは間違いないだろう。
今回はライヴを目前に控えるタイミングで、三宅純の越境的なバックグラウンドと、ミュージシャンとしてのエレガントな矜持を改めて掘り下げるべく、音楽評論家の渡辺亨氏によるインタヴューを実施。世界的ミュージシャンの魅力と公演の展望に迫った。 *Mikiki編集部
トータルの世界観を構築することに興味がある
――今年はオリンピックの件もあって、ご活躍の年ですよね。あの閉会式での“君が代”が実現したのも、(音楽監督を務めた)椎名林檎さんがパリで三宅さんのコンサートをご覧になったのがきっかけだとか?
「ええ、2年前に。当時はまだ面識がなかったんですけど、たまたまそのコンサートの数日後に舞台の仕事で日本に帰る予定があって、そのときに羽田空港のバゲージクレームで呼び止められたんです。それで、〈コンサート素晴らしかったです〉と名刺をくださったんですけど、僕は彼女のことを知らなかったんですよ。その場でパートナーが〈(小声で)有名な方よ!〉と教えてくれて」
――今回のライヴで、編成とレパートリーというのは密接な関係があると思うんですけど、こちら(近年の3作)は現時点での三宅さんの代表的なレパートリーというふうに捉えていいですか?
「そうですね。あくまで軸足は作曲活動にあるので、例年はライヴをするのも年に1~2回くらいなんですよ。そういうなかで自分の世界観を提示することを前提に編成とレパートリーを考えたら、歌手陣が(ゲストも合わせて)9名になっちゃった」
――バート・バカラックもオーケストラと共演することがありますが、それと同じように作曲家によるコンサートということですよね。やっぱりご自分としては、パフォーマーよりも作曲家としての意識のほうが強いですか?
「意識という点ではそうです。それこそ、20代後半までは演奏家だけでやっていましたけど、それ以降はトータルの世界観を構築することのほうに興味がありますし。演奏するときも、自分が前に出ることはあまり考えていない」
――もっと言うと、アルバム作りに関してはコンポーザー兼プロデューサーという意識も強そうな印象を受けていて。〈Lost Memory Theatre〉シリーズの2枚も、いまどき珍しいコンセプチュアルな作品ですよね。
「珍しいんですか?」
――そうだと思いますよ。プリンスも昨年のグラミー賞のスピーチで言ってましたよね、〈みんな、アルバムって覚えてる?〉と。
「ああ、そういう意味では古い人間ですよ。『Stolen from strangers』にも〈Lost Memory Theatre〉へのプロローグ的な意識がありますし」
――そういう三宅さんの原点を振り返るために『星ノ玉ノ緒』(93年)の話をしますけど、ここではハル・ウィルナーがプロデューサーとして参加したことで、アルバムの世界観にさらなる魅力をもたらしていましたよね。彼と知り合ったのは、ピーター・シェラー※が仲立ちしてくれたのがきっかけだったとか。
※スイス出身のキーボード奏者。デジタル楽器の扱いに長けており、アート・リンゼイと組んだアンビシャス・ラヴァーズとしての活動が特に有名
「そうですね」
――ハル・ウィルナーに興味を抱いたきっかけは?
「やはりクルト・ワイルやセロニアス・モンク、ニーノ・ロータといった一連のトリビュート・アルバムですね。ちょうど時期的には(チャールズ・)ミンガスも出ていたかな※」
※『Lost In The Stars: The Music Of Kurt Weill』(85年)、『That's The Way I Feel Now: A Tribute To Thelonious Monk』(84年)、『Amarcord Nino Rota: Interpretations Of Nino Rota's Music From The Films Of Federico Fellini』(81年)、『Weird Nightmare: Meditations On Mingus』(92年)のこと。各作品でルー・リード、トム・ウェイツ、トッド・ラングレンなど大物ミュージシャンが多数参加している
――三宅さんの音楽にも、クルト・ワイルやキャバレー・ミュージック、あるいは映画で言うと(ニーノ・ロータが作曲を手掛けた)フェデリコ・フェリーニやルキノ・ヴィスコンティにも通じる、シアトリカルというかオーディオ・ムーヴィー的な要素が一貫してありましたよね。そういう意味でも原点だと思うんですけど、クルト・ワイルやキャバレー・ミュージックにはいつ頃から興味がおありだったんですか?
「僕はもともと、自分の音楽をジャズだけで純粋培養したい意識が強かったんですけど、81年にマイルス・デイヴィスのカムバック・コンサートがリンカーン・センターであって、それを観たときに〈ジャズは終わった〉と感じたんですよ。それで一気に耳が開いて。それ以前はジャズしか聴かないようにしていたのが、全方位的に聴くようになったんです」
――ジャズに一度失望してから、いろんな音楽を聴くようになって世界が広がっていったと。
「そうですね。クルト・ワイルはジャズのレパートリーとしてもかなり取り上げられているので、もともと親しみはあったんですけど、アプローチの仕方やアレンジの手法にしても、いわゆるジャズ的なものとは全然違う。前に一度、(クルト・ワイルが作曲を手掛けた)〈三文オペラ〉の舞台で音楽監督をしたことがあって、そのときにスコアを細かく見てみたんですけど、あまりにも構造が素晴らしくて。最小限の音で、あのハーモニーや世界観を表現しているところに驚愕した覚えがあります」
――ライザ・ミネリが(主演した映画)「キャバレー」でアカデミー賞を獲ったのが73年。それから70年代後半にデヴィッド・ボウイがベルリンでレコーディングして、同じころに日本では加藤和彦さんが70年代末期から80年代初頭にかけて、ベル・エポックのパリや1920年代のベルリンをテーマにした〈ヨーロッパ3部作〉を発表した。また、その頃には東京ではヴィスコンティの映画が流行していて……というふうに、70年代の終わり頃になると、〈1920年代〉や〈世紀末〉というキーワードが浮上してきた。そういう東京のムードは間接的にでも届いていましたか?
「いや、アメリカ留学中は一度も帰国しなかったので、あまりそのムードは感じていませんでした。ただし、これは20年代のキャバレーではなく、日本独自のキャバレーの話ですけど(笑)、こんなことがありました。僕は高校時代に日野皓正さんにトランペットを教わっていたのですが、日野さんが一足先にNYへ渡ったときに、ご自分の先生を紹介してくれたんです。それが赤坂ミカドのボスだった方で、〈詰襟を着て勉強に来い〉と言われて、ストリッパーがいっぱいいる社員食堂を眺めながら演奏したりしました」
――あの伝説のキャバレーで、演奏なさったことがあるんですか。それは貴重な経験ですね。ちなみに先ほど出た81年というのは、NYに住まわれて何年くらい経った頃ですか?
「5年目ですね。ちょうど日本に帰ってこようと思っていた時期で」
――NYに住んでいたからこそ得られた刺激というのはありますか?
「刺激……街そのものの危険度がすでに刺激でしたね(笑)」
――時期的には、(NYが舞台の映画)「タクシードライバー」(76年)が公開されたちょっと後ですよね。
「渡米したのがちょうど76年でした、いやはや本当に怖かったです。あとは人種の坩堝で、文化や宗教、あらゆるところが入り乱れている感じには、いまでも影響を受けているかもしれないです。それに、キース・ヘリングが街で落書きしているのも見ましたし、アンディ・ウォーホルもまだ生きていた頃だったから」
――そういう80年前後に〈ジャズは終わった〉と感じたのは、時代の趨勢でもありますよね。平岡正明は、黄金時代のジャズの一つの表現として、サックスだったかスピーカーだったかうろ覚えですが、〈ドル紙幣が吹き出してくるような演奏〉と書いています。1950年代はアメリカが経済的なヘゲモニーを完全に握っていて、世界でもっとも豊かな国で、その豊かな国の音楽がジャズだった。それを否定したのがロックで、その時代になるとアメリカの社会秩序も良い意味でだんだん乱れていって。だから、81年頃にジャズに見切りを付けたというのは、すごく自然な感じがするんですよね。
「同世代のミュージシャンに対しても、そんなことを言ったら殺されそうな雰囲気がまだありましたけどね。でも、意識としては完璧に終わっちゃった」
――NYにいたからこそ、そう感じたんでしょうかね。
「どうなんでしょう。アート・リンゼイも同じコンサートに行ってたと言ってましたし」
――アート・リンゼイと初めて面識を持ったのはいつ頃ですか?
「ちょうどピーター・シェラーと知り合った頃だから、87、88年くらいですかね」
――じゃあ、もう2人がアンビシャス・ラヴァーズとして活動していた頃ですね。アート・リンゼイにも〈NYのなかの異邦人〉みたいなところがあると思いますが。
「まあ、不思議な人物ですよね。天使と悪魔が同居しているようなキャラで。インテリだし、センスもいい。それに声も世界観も好きだけど、一緒に仕事をするのは簡単ではないです」
――それは人間的なところもあるんでしょうけど、音楽的に素人であることも関係ありますか?
「大きいです(笑)。なかなか歌詞も書いてくれないんですよね。〈書いてくる〉と言って、最初に出てきたのが2言だけだったとか。その数か月後に集合しても一行増えただけで。毎回頼むときは、何年越しでやるんだろうと覚悟しながらやらないと」

――ハル・ウィルナーに話を戻すと、一番共感したところというのは?
「彼の嗜好性、センス、美観かな。彼自身はプロデューサーであって、ミュージシャンではない。だから大雑把に言ってしまえば(参加する)人を選んで、そのミュージシャンに丸投げしているんだけなんですけど。その人選がいつもおもしろいのかな」
――でも映画の監督にしたって、人選だけでも大きな仕事ですよね。ちなみに、キップ・ハンラハンはジャン=リュック・ゴダール監督の映画で助監督をやっていたことがあるそうですけど、彼も同じく人選の人ですよね。そういう立ち位置の人が当時は新鮮だった。その方法論を日本で最初に具現化させたのが三宅さんなのかなと。
「本当ですか(笑)。僕はもう少し音楽そのものに関与するかもしれないけど、ハルの世界観に影響を受けた部分はあるでしょうね」
――そういう意味でも、三宅さんの音楽は映画的ですよね。ある映画のためにいつものメンバーが集まって、また離れていく。黒澤組ならぬ三宅組というか。映画はお好きでしたか?
「映画はもう大好きです。最近は見る時間が簡単に作れないという状況ですが、一時はかなり観ていたと思います」
――話を訊いていても、やっぱり映画が好きな方なんだなと。自分は主役ではなくディレクターやプロデューサーであって、三宅組という一つのプロジェクトを作っていくことを強く意識している。そういう方法論は、誰かを参考にしたりしたんですか?
「いや、なんとなく自然に辿り着いただけです。フォーカスがだんだん演奏家から変わっていくなかで、コンピューターの発達もあって、自分で全体をコントロールしやすくなった。そういう経緯と共に、いまのポジションがあると思います」
――とはいえ、三宅さんはテクノロジーに頼り切っているわけでもないですよね。それよりもビッグバンドというかラージ・アンサンブル的で、参加しているミュージシャンの人数もすごく多い。それについては、ご自分ではどのように分析していますか?
「曲を書くときは塊で降りてくるので、zipファイルを解凍するのに近い感覚なんですよ。それから、ヴァイオリンが何人入っているかなど、現実的な解析をしながら作っていく。例えば 録音現場でも 音場を変えるために、一人のヴァイオリニストを自宅のスタジオに呼んで、(座っている)椅子の位置を少しずつずらしながら録音したり、そういう地味なことはいっぱいやってますよ」
――機械とだけ向き合うのとはまったく違いますよね、三宅さんの世界は。
「編集の時期に入ると、トラックボールで腱鞘炎になるくらい何週間も向き合うこともありますけどね」