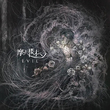様式美を現代的に更新してきた摩天楼オペラの歩み
〈摩天楼〉に象徴される現代的なセンスと、〈オペラ〉のような伝統的様式美。彼らのバンド名は、理想とする音楽性を抽象するものでもあり、活動初期から確立していた摩天楼オペラのパーソナリティーは、同時にメンバー個々のプレイヤーとしてのポテンシャルの高さも伝えていた。早くから実力派として注目された所以は、当時の楽曲をコンパイルした『INDIES BEST COLLECTION』を耳にすればすぐにわかるだろう。事実、結成から約3年でメジャーへ進出。まさに名刺代わりとなるデビュー・ミニ・アルバム『Abyss』(2010年)は、SIAM SHADEやJanne Da Arcなどを手掛けた明石昌夫をプロデューサーに迎え、すべての面において完成度が高まった一枚だった。特にオープニング曲“INDEPENDENT”が放つ勢いに、新たな世界に意気揚々と飛び込んでいく気概が見て取れる。
続くフル作品となった『Justice』(2011年)は、持ち前のシンフォニックなアレンジを施したハード&ヘヴィーなサウンドでまとめながら、よりドラマティックに進化。自身の音楽性の本質をより深く見つめた成果が、着実に表れていた。そうした〈核〉を再確認した彼らは、さらなる一歩を踏み出す。その結果として生まれたのが、『喝采と激情のグロリア』(2013年)だった。表題に冠された言葉は制作に向けて掲げられていたテーマでもあったが、以降の特徴にもなっていく〈合唱〉を大幅に採り入れたことで、力強さも美麗さも併せ持つ、摩天楼オペラたる壮大な世界が際立って描かれている。そして『AVALON』(2014年)では、前作を受けての〈シンフォニック・モダン・ロック・オペラ〉を提唱。特に終曲の“天国の在る場所”は、荘厳な光景が瞬時に思い浮かぶ象徴的なマテリアルだろう。
加えて、それまでの歩みを高次元で形にしたのが『地球』(2016年)だった。より追究されたドラマ性と、幻想的な物語。地球を構成する五大元素(土、水、火、風、エーテル)を中心的なテーマに据えて書き下ろされた楽曲群は、コンセプト作ならではの性格が色濃く表出している。彼らが辿ってきた音楽的旅路の最初の終着点とも言える傑作だ。同作の発表後に〈ギタリストの脱退〉という予想だにしなかった事態を迎えたバンドは、その危機的状況を爽快に打破した『PHOENIX RISING』(2016年)をリリース。彼らの基盤であるヘヴィー・メタル色を前面に押し出したアプローチは、文字通りに不死鳥の如き新たな飛躍を予感させた。その信念は最新作『PANTHEON –PART 1-』にもそのまま継承されている。 *土屋京輔
摩天楼オペラの作品。