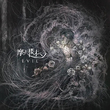不測の事態を乗り越え、改めて確認した自身の武器。〈この4人で行くしかない〉という決意は、バンド史上もっともヘヴィー・メタルなサウンドのなかで美しく輝く!
自分たちなりのヘヴィー・メタル
「メンバーが4人になって〈俺らのいちばんの武器はなんだっけ?〉と振り返ったときに、〈ヘヴィー・メタル〉という言葉が出てきたんですよ」(苑、ヴォーカル)。
今年でバンドの結成から10周年を迎えた摩天楼オペラ。彼らがニュー・アルバム『PANTHEON -PART 1-』を完成させた。昨年7月のライヴをもって、ギタリストが脱退。それを受け、残る4人体制で10月に発表した前作『PHOENIX RISING』に続く今作は、冒頭の苑の言葉にあるように真正面からヘヴィー・メタルと向き合った、激しい一枚に仕上がっている。
「『地球』(5人体制での最終作となる2016年のフル・アルバム)は変化球を意識した曲作りだったけど、その頃から〈次はストレートな作風にしたい〉という話は出てました。その意味で、今回のアルバムは前作の流れも汲んでますね」(彩雨、キーボード)。
「前作もストレートだけど、まだ〈いろんな表情を見せなきゃいけない〉と思ってたんですよ。その点、今回のほうがよりヘヴィー・メタルを突き詰めた作品になったなと」(悠、ドラムス)。
摩天楼オペラが本作で掲げた〈ヘヴィー・メタル〉とは、どのような音を指すのか。〈メタル〉と一口に言ってもさまざまなサブ・ジャンルがあり、100人いれば100人それぞれの思うサウンドがある。
「偏ってるかもしれないけど、僕のなかのヘヴィー・メタルは〈メロディック・スピード・メタル〉なんです。とにかくメロディーが良くて、テンポが速い。ツーバスをドコドコ踏んでるイメージですね」(苑)。
例えばハロウィーンやX JAPANなど、アグレッシヴさとメロディアスさの両方を研ぎ澄ませたメタル・サウンドは、確かに摩天楼オペラのルーツのひとつ。今回に関しては、そこを〈自分たちが向かうべき方向性〉として定めたわけだ。その象徴となる楽曲を訊ねてみると……。
「“PANTHEON”ですね。まず、ちゃんとヘヴィー・メタルしているし、摩天楼オペラがやるからこその大仰さもある。あと、メロディーもいちばん説得力がありますからね。この曲にタイトル曲としてのパワーがあるからこそ、ほかの曲も活きてくると思うんですよ」(苑)。
そう苑が語るように、本作にはメロスピを柱にしつつもさまざまなヴァリエーションのメタル・サウンドが収められている。苑が作詞/作曲を手掛けた“Couse Of Blood”は、今作中でもとりわけエッジーな疾走ナンバー。メタル特有の邪悪な香りもプンプン漂ってくる。
「メロスピは美しいから、ガツガツ、ゴリゴリした部分に欠けるので、ライヴを意識して激しい曲を作りたいなと。じゃあ、スラッシュ・メタルをやってみようと思って、この曲はギターで作りました。16分をすごく刻みましたもん(笑)。ただ、僕の引き出しにはスラッシュがなかったので、悠にどういうものか訊いたんですよ」(苑)。
「メタリカの“Battery”、アンスラックスの“Caught In A Mosh”、スレイヤーの“Angel Of Death”。参考になればと思い、王道のスラッシュ・メタルの曲を聴かせました(笑)」(悠)。
「〈ああ、これがスラッシュ・メタルか〉って。〈でも、俺は(メタルと言えば)メロスピだし……〉と思いながら(笑)、そのせめぎ合いのなかで作りました」(苑)。
より過激な音色、演奏を追い求めるなか、本作ではこれまでと違うプレイ・スタイルにもトライしている。キャリアを積み重ねながら、新しい領域にチャレンジする姿勢も忘れていない。
「音源を出すたびに、いままでやらなかったことに取り組もうと。今回は速い曲が多いので、ピック弾きを練習しました。自分としては、そこがこの10年間でいちばん変わったところかもしれない。〈俺は絶対に指弾きなんだ!〉と思ってましたからね。さっき話に出た“Curse Of Blood”は全部ピックで弾いてるんですよ。指とピックでは全然ニュアンスが違うし、疾走感を出すためにはピック弾きだなと」(耀、ベース)。
また、今作は昨年からライヴでサポートを務めているLIGHT BRINGERのJaYがギターで参加しているのもトピックだろう。
「JaY君は前に出て行くような性格でありつつ、音楽的に空気を読むのも上手いんですよ。アレンジも僕のシンセを聴き込んだうえでしてくれて、結果的にシンセも前に出やすくなりましたね。ギターもキーボードも上手く絡み合ってると思います。曲のコンセプトがしっかりしていたから、シンセも入れやすかったですね」(彩雨)。
この4人で行くしかない
さらにアルバムの後半には、摩天楼オペラらしさを重んじたアプローチや、逆に従来のバンド像に縛られないテイストの楽曲も収録されている。メタルと言えば、インストゥルメンタルも魅力のひとつ。“SYMPOSION”は初めて耀、彩雨、悠の3人で作り上げたインスト曲だ。
「インストはこれまで前のギタリストが作っていたけど、今回は耀が〈インストをやる〉と言い出したんですよ。みんなでアイデアを出しつつ、聴きどころの多い曲になったと思います。ベーシックは耀が作って、それに僕がメロディーを付けた感じです。ちょっといままでのインストとは毛色が違うかなと」(彩雨)。
「いままでのフル・アルバムには必ずインストが入っていたから、4人になってそういうアプローチがなくなるのは寂しいなと思って、今のメンバーで作り上げられたらいいなと。このインストを経て、次の曲に繋がる流れも考えました」(耀)。
笛のように聴こえる神秘的なシンセを用いたインストから、次の“何度目かのプロローグ”へバトンを繋ぐ。この流れはほかのメタル・ナンバーとは別の表情を垣間見せ、作品にいいフックをもたらしている。
「全体的に疾走感のある曲が多いので、1曲ぐらいハード・ロックっぽい曲があってもいいかなと思って作ったのが“何度目かのプロローグ”。サビ以降の構成は苑が考えてくれたんですよ。いままでも8ビートの曲はあったけど、また新しい感じに仕上がったなと。どっしりしてるし、これぐらいのビート感で明るいメロディーの曲は意外となかったから」(耀)。
「その曲は仮タイトルが〈俺なりのボン・ジョヴィ〉でしたからね(笑)。今作にはいつものしっとり聴かせるバラードはないけど、“何度目かのプロローグ”はある意味バラードのようにも聴こえるし、こういう広がりのある曲も好きですね」(彩雨)。
現在の4人のメンバーの個性を一曲一曲に凝縮し、ソリッドにしてストレートなメタルで攻めた『PANTHEON -PART 1-』。そんな本作は、歌詞においても「〈この4人で行くしかない、自分たちを信じて前に進もう!〉という内容ばかり」(苑)だという。摩天楼オペラの覚悟と決意に満ちた渾身のメタル・アルバムを、ぜひ聴いてみてほしい。
摩天楼オペラのベスト盤。