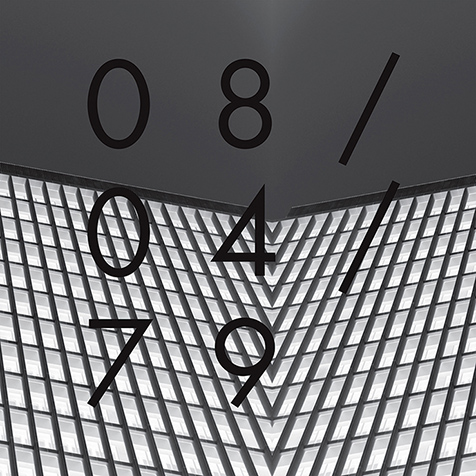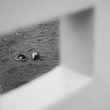ジュリアン・ラージというギタリストは、何から何まで規格外だ。10代の頃からミュージシャンとして活動し、ブルースやブルーグラス、カントリーのシーンに足を突っ込んできたかと思えば、パット・メセニーやカート・ローゼンウィンケルなど一流ギタリストが参加してきたゲイリー・バートンのバンドに15歳の若さで加入。さらに20歳のときに録音した初リーダー作『Sounding Point』(2009年)をエマーシーから発表してメジャー・デビューを果たし、ジャズの世界でも天才少年ギタリストとしてその名を轟かせた。
その後もフレッド・ハーシュと共演したかと思えば、ジャズ・ピアニストのテイラー・アイグスティがシンガー・ソングライター的な感性を光らせた傑作『Daylight At Midnight』(2010年)ではニック・ドレイクの名曲“Pink Moon”を奏で、ブルーグラス新世代を代表するパンチ・ブラザーズのクリス・エルドリッジや、ウィルコのメンバーでもあるネルス・クラインといった個性派ギタリストたちとのデュオで活動を行うなど、アメリカの音楽シーンを縦横無尽に駆け巡っている。そして、自身のトリオで録音した2015年の最新作『Arclight』ではジェシー・ハリスをプロデューサーに迎え、さらに進化した姿を見せてくれた。
まだ弱冠29歳にもかかわらず、戦前のジャズにブルーグラスやカントリーといった伝統音楽から現行のインディー・ロックまでギター・ミュージックの豊かな歴史を咀嚼しながら、ジュリアン・ラージはまったく未知のスタイルに到達している。(一見、近いものだと映りそうな)ビル・フリゼールやパット・メセニーとも異なる、モダン・ジャズの枠に留まらない唯一無二の感性――同世代のジャズ・ギタリストがカート・ローゼンウィンケルやピーター・バーンスタインに追随するなか、彼だけはずっと孤高の道を歩んできたのだ。だから、1月31日(火)~2月3日(金)に東京・丸の内コットンクラブで行われる来日公演も、きっと特別なものになるだろう。これまでの歩みとミュージシャンたちとの出会い、独自の音楽観とライヴの展望について話を訊いた。
――10代の頃は、リスナーとしてどんな音楽を聴いていましたか?
「その頃の僕はジャズに夢中だったし、ポップ・ミュージックやインド音楽も聴くようになっていた。ビョークやラヴィ・シャンカール、ジェイムズ・テイラーが特に大好きだったよ」
――ギタリストとしての出発点は、ジム・ホール※だったそうですね。彼からはどのような影響を受けたのでしょう?
※音数の少ない静寂なプレイ・スタイルと奔放なインプロヴィゼーションで知られ、今日的なジャズ・ギター奏法の原点となった1930年生まれのギタリスト
「ジャズに入れ込むようになったとき、ジム・ホールは僕のヒーローになったんだ。彼の音楽は豊かなニュアンスとユーモア、生命力に満ちている。ジム自身もそういう人物だから本当に尊敬しているし、どのように演奏や作曲をするべきか、バンド・リーダーとしてどうあるべきか、その他あらゆることに関してジムから学び続けている。僕にとって、彼は〈世界〉そのものなんだ」
――かなり若い頃に、デヴィッド・グリスマン※と共演していますよね。それはどういう経緯から実現したのでしょうか?
※1945年生まれのマンドリン奏者。ブルーグラスとジャズ、カントリーやラテン音楽などを融合させた〈ドーグ・ミュージック〉を提唱した
「デヴィッド・グリスマンと初めて会ったのは、僕が10歳のときだった。デヴィッドの息子は、僕の家族が通っていたミュージック・ストアの店員をしていて、以前から友人だった。それで、父と一緒にカリフォルニアで開催されたヴィンテージ・ギターの展示会に行ったとき、彼にデヴィッドを紹介してもらったんだよ。デヴィッドは穏やかで寛大な人で、僕の人生をすっかり変えてくれた。レコーディング・デビューの機会も与えてもらったし、彼と一緒に過ごすことで、僕はブルーグラスやアメリカのトラディショナル・ミュージックを発見することができたんだ。もっとも、そういう音楽を本格的に掘り下げたり、自分でも演奏/作曲したりするようになるのは何年もあとの話だけどね」
――さらに、ベラ・フレック※とも共演していますよね。ギタリストとして、バンジョーから何かインスパイアされたことはありますか?
※ブルーグラスにジャズやファンク、クラシックなどの要素を採り入れた、技巧的かつプログレッシヴな演奏で知られる58年生まれのバンジョー奏者
「ベラ・フレックとはデヴィッド・グリスマンを通じて知り合った。僕が育った街、カリフォルニアのサンタローザでベラがライヴしたときに、デヴィッドが〈ベラと一緒に演奏しよう〉と僕と父を誘ってくれたんだ。ベラの演奏には吹っ飛ばされたよ。そのとき、僕はバンジョーが持つ力にすっかり魅了されたんだ。ここ数年は、テノール・バンジョーを通じて、ジャズ・ギター(の演奏)を進化させようと一生懸命に取り組んでいる。バンジョーの演奏を習うことで、そのテクニックをテレキャスターに応用しようとしているんだ。ダニー・ガットンを筆頭に、偉大なるテレキャスター奏者の多くがかつてバンジョーを演奏していたようにね」

――ブルーグラスといえば、デビュー作の『Sounding Point』にクリス・シーリを起用したり、2014年にはクリス・エルドリッジとの共演作『Avalon』をリリースしたりと、パンチ・ブラザーズとの繋がりも強いですよね。
「彼らと知り合ったのは6年前。僕が『Sounding Point』の制作へ向けた準備をしているときに、クリス・シーリと会うためにパンチ・ブラザーズのライヴに行って、バックステージで挨拶したんだ。そこからすぐにクリス・エルドリッジと演奏するようになって、それはもう圧倒されたな。あっという間に仲良くなれたし、彼らのコミュニティーと繋がることができて光栄だね」
――あなたの奏法はクラシック・ギターやフラメンコからも影響を受けているように思ったのですが、いかがでしょう?
「僕はクラシック・ギターが大好きで、アンドレス・セゴビアやジュリアン・ブリーム、アグスティン・バリオス、デヴィッド・タネンバウムといった偉大なる奏者からいまも学び続けている。でも、クラシック・ギターについてはそこまで深く勉強してきたわけでもなくて、それよりもエレキ・ギターやスティール・ギターの練習に多くの時間を割いてきた。フラメンコも同様だね、音楽そのものは大好きだけど」
――ヴィブラフォン奏者のゲイリー・バートンとの出会いは、あなたのキャリアにおいても大きなトピックだったのではないでしょうか。彼はジャズをロックやフォーク、カントリーと融合させたようなサウンドで知られていますが、そういった音楽観はあなたにも通じるものがあるように思います。
「その通り! ゲイリーはこれまで会ったなかでも、もっとも影響を受けたミュージシャンのひとりだ。プレイ面で影響を受けたのはもちろんだし、作曲家/アレンジャーとしてのコンセプト設計も衝撃的だった。彼はキャリアを通じて、さまざまなスタイルを結合させながらフレッシュで新しい音楽を生み出してきた。何年間も彼と一緒に演奏できたのは、本当にラッキーだったし感謝しているよ」
――ゲイリー・バートンといえば、ラリー・コリエル、パット・メセニー、ビル・フリゼールやカート・ローゼンウィンケルなど伝説的なギタリストと共演してきたことでも有名ですよね。
「どのギタリストもみんな素晴らしいよね。それぞれの個性はまったく違うのに、ゲイリーは誰とやっても上手くいくんだ。それはきっと彼の特別な能力なんだと思う」
――ビル・フリゼールやパット・メセニー、ブライアン・ブレイド、ジミー・ジェフリーのように、フォーキーなサウンドを取り入れたジャズを生み出したミュージシャンの作品から学んだ部分もありますか?
「伝統音楽とコンテンポラリーなサウンドをどうやって結び付けるのか、ということについてかな。影響源は似ているのかもしれないけど、それぞれがユニークで美しい表現を見せている。みんな大好きなプレイヤーだし、大きく影響されているよ」
――あなたはテイラー・アイグスティのバンドに参加して、ニック・ドレイクの楽曲を一緒に演奏していましたよね。ご自分のリーダー作でもエリオット・スミスの“Alameda”をカヴァーしていましたが、それらはどこか共振しているように感じました。そういった内省的でフォーキーな音楽は、自分のなかでどのような位置づけなのでしょう?
「僕はロックやポップ・ミュージックが大好きだし、それらをジャズやトラディショナル・ミュージックと区別しながら聴いているわけではない。特定のジャンルやスタイルに忠実でありながら、ずば抜けた強度を持つ曲が好きなんだ」
――ジャズ以外のジャンルで、共感を覚えるアーティストは誰ですか?
「マーガレット・グラスピーだね。彼女は最高のギタリストにしてシンガー・ソングライターで、僕のパートナーでもある。強く尊敬しているし、そのクリエイティヴィティーには強く影響を受けているよ。それに、本田ゆか(チボ・マット)も好きだよ」
――あなたはビバップ以前のジャズや、20世紀初頭のアメリカン・ミュージックへの関心をたびたび語っています。なぜ、それらの音楽を新鮮なものだと感じたのでしょうか?
「そういう音楽からは世界中の……特にアメリカの音楽がもっとエクスペリメンタルだった時代の空気を感じるんだよね。もちろん、音楽はいつだって進化を重ねて変わり続けていると思うけど、20世紀初頭の音楽はラジオと現代的な録音技術が同時に発展していたこともあって、カントリーやジャズ、ヴォードヴィルにブルース、クラシックといったさまざまな音楽が影響を与え合うことで、想像力を膨らませていたんだと思う。ビバップ期に入るとそれも収束して、すべては過去の話になるわけだけど。あと、あの時代の音楽はギターとの結びつきも強かったね。ギターの開発は当時爆発的に進んでいったんだ。バンジョーからギターへと発展して、さらにハワイアン・スライド・ギターの影響も受けていた」
――最新作『Arclight』でジェシー・ハリスにプロデュースを依頼した経緯と、彼がどんな部分で作品に貢献してくれたのかを教えてください。
「ジェシーは親友のひとりで、最高のミュージシャンだ。『Arclight』を制作するにあたって、どんな曲を収録するべきなのか、どのように録音するのがベストなのかをジェシーに相談したときに、このプロジェクトにもっとも相応しいプロデューサーであることを瞬時に悟ったんだ。レコーディングの技術や楽曲のアレンジ、収録曲のセレクトやアルバムの曲順をどのように決めるかなど、彼のガイダンスはあらゆる面で有意義だったよ」
――来日公演は『Arclight』と同じトリオ編成で出演するんですよね。ジョージ・ローダー(ベース)、エリック・ドゥーブ(ドラムス)というリズム・セクションを日本のファンに向けて紹介してもらえますか。
「ジョージとデュークはNYのシーンでも最上級のミュージシャンだし、国際的に見てもトップクラスだと思う。ジョージとは僕のバンドであるジュリアン・ラージ・グループや、ゲイリー・バートン・クァルテットを通じて長年一緒に演奏してきた。エリックのことを初めて知ったのは何年も前の話だけど、僕はすぐファンになったし、テイラー・アイグスティやミゲル・ゼノンと共演する彼のことをずっと追いかけてきたんだ。だからトリオで一緒に演奏できるようになったとき、僕は素晴らしい一体感を覚えたよ。そのときの興奮を日本に持って行くからね!」
ジュリアン・ラージ・トリオ
日時/会場:1月31日(火)~2月3日(金) 東京・丸の内コットンクラブ
開場/開演:
・1stショウ:17:00/18:30
・2ndショウ:20:00/21:00
料金:自由席/6,800円
※指定席の料金は下記リンク先を参照
★予約はこちら