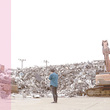アメリカーナ、ブリティッシュ・ロック、サイケ、クラウトロック…etc。東京・下北沢を拠点に活動する6人組バンド、JAPPERSの音楽にはさまざまな要素が散りばめられている。ミツメやシャムキャッツといったバンドからリスペクトされ、ベーシストの上野恒星は今年の1月よりYogee New Wavesに加入するなど、東京インディー・シーンでの注目度が上がるなか、セカンド・アルバムとなる新作『formulas and libra』が完成した。LEARNERSやNOT WONKが所属するKiliKiliVillaからのリリースとなった本作は、2014年のファースト『Imaginary Friend』に比べて、より開放的なサウンドへと変化。曲ごとに変幻自在のバンド・アンサンブルを聴かせるなか、そこには〈ロックンロールの形式〉が息づいている。そんな新作が生まれた背景について、作詞作曲を担当するヴォーカリストの榊原聖也に話を訊いた。
負け犬の音楽が好きなんです
――今回、KiliKiliVillaで制作したことがレコーディングを含めてアルバムに影響を与えているところはありますか?
「前作『Imaginary Friend』のレコーディングは、ほとんど無制限に時間があるなかで音をこねくり回したりしたので、宅録っぽくて密室感のあるサウンドになったんです。当時の自分達の好みの音ではあったんですけどね。今回はちゃんとしたスタジオを使って、レコーディングの期限を決めてやったので、録り音が変わって外向きの音になりましたね」
――外向きの音というと?
「パッキリと立体感のある音になって、そこに自分達のラフな感じも混ぜることができました。ビートルズでいうと〈ホワイト・アルバム〉みたいな音になった気がします。あと、個人的にエリオット・スミスの『Figure 8』が好きで。ラフだけど叙情的な感じとか、(他の音と)混ざり合いつつもクッキリと聴こえるコーラスとか、今回はそういう『Figure 8』みたいな感じを出したいと思っていました」
――そういうのは事前にメンバー間でイメージを擦り合わせておくんですか?
「前作には明確なイメージがわりとあったんですけど、今回はお互いを信用して、それぞれがやりたいようにやったうえで作り上げていきました。良い意味でのロックンロール的な形式を出したかったんですよね」
――〈ロックンロール的な形式〉というのは?
「これって、すごく説明しがたい部分で、何でもありだけど何でもありじゃないスタイルというか。幼稚な言葉で言うと、自分が音楽を聴いて〈グッとくる〉部分なんですけど、ちゃんと言葉にするのが結構難しくて……」
――エイトビートとか、そういうサウンド面のことではなくて感覚的なものなんですね。
「そうなんです。(心を)えぐってくる部分というか。例えばビッグ・スターのアレックス・チルトン※に自分はどうしようもなくロックンロールを感じるところがあって。ロールしていようがしていまいが関係ないというか、踊れなくてもロックな感じ」
※ビッグ・スターで知られ、カルト的な人気を誇るロック・スター。2010年没
――そういう感覚的なものを他人と共有するのは難しいと思いますが、メンバー感では共有できているんですね。
「できていると思います。というのも、この6人で8年ぐらい一緒にやってきたんですけど、ウチはいつも一緒に遊んでいるようなバンドじゃなくて、〈音楽をする!〉という感じで集まったバンドだから、いつも感覚的なことを話しているんです。〈こういう曲ってグッとくるよね〉とか。そういう部分をある程度共有できていると思うし、それぞれ好きな音楽は違っても、みんな土台はビートルズなんですよ」

――根本は繋がっているんですね。レコーディングの時に大切にしていることはありますか?
「綺麗に整いすぎた音、死んだみたいな音があんまり好きじゃなくて、生で録ったときのラフさとか空気感を大事にしています。ベーシックはちゃんと録ったし、パートで分かれての録音もしたんですけど、自然なズレや事故的な部分は結構生まれたと思います」
――ちゃんとしたスタジオで録ったぶん、そういうところを意識した?
「いや、もともとそういうバンドというか、ちゃんとできないバンドなんですよ(笑)。勝手にそうなっちゃうというか、そこを重視しちゃう部分があって。それが逃げに発展することもあるんですけど、今回のアルバムに関しては、そのあたりをエンジニアの柏井日向さんが上手く拾い上げてくれました。これまでは自分達で空気感みたいなものを作っていたんですけど、今回はライヴみたいな感じで素直に録ることができたと思います。そして、そこで録った音を、どういうふうにヘンにしていくか、どう違和感を出していくかという作業についてはKiliKiliVillaがかなり後押ししてくれたんです。〈どんどんやれ!〉みたいな感じで」
――ちなみに録り音を汚していく作業を特にやった曲というと……。
「“War”ですね。ベーシックを録るつもりで一発録りした音を、ディストーションをかけたり、BPMを落としたり加工してみたら、充分ヘンな感じになったので、これでもうOKかなって」
――グシャグシャな音になっていて、かなりの戦争状態ですね(笑)。
「もともとドロドロな曲なんですよ。そのドロドロ感を大事にしたかったので、良い具合に泥まみれになりました」
――その前の“Rock’n’ Roll Music”も良い感じに汚れていて。
「そうですね。あのあたりの流れはロックンロール的というか。ファジーで汚れていて……」
――それに比べると1曲目 “In Proper Place”は、クリアなサウンドのなかにジャム・バンドっぽいラフさもあって、本作の雰囲気を伝えている気がします。
「いま僕は明大前に住んでいるんですけど、その前に蒲田に住んでいて、そのときに“Rock’n’ Roll Music”とかうるさい曲を作ったんです。蒲田は工業地帯だったりして、ちょっとマッチョでロックンロールな感じがあったんですよね。“In Proper Place”は明大前に越してから作った曲だから、街っぽい感じの曲なんです」
――生活環境から影響を受けているんですね。
「そうですね。そのほうがしっくりくるというか、〈曲を作るぞ!〉って意識して作るということがあまりないんです。適当にギターを弾いていると気づかないうちに曲が出来て、それをあとで聴いて、〈こういうことだったのか〉と腑に落ちることが多い。そのときの自分の状況とか、もしくは過去や未来が知らない間に曲に反映されているという感じですね」
――曲作りに関しては、自分のなかから自然に溢れ出るものを大切にしているんですね。サウンド面に関してはどうですか? 例えば、本作ではギター・サウンドが多彩でいろんな音色を織り交ぜています。
「そこはメンバーそれぞれが個人レヴェルで作り上げていった部分が大きいと思います。例えばギターの(竹川)天志郎は、前作でも録音したものに自分でノイズを乗せていたし、そういうところにこだわるメンバーが多いんですよ。今回は12弦とスティール・ギターがウワモノで入っているんですけど、トレモロをかけて音を変えてみたりして、ひとつひとつの楽器の音色を変えることで音色の幅はこれまでより増えた気がします」
――その結果、サウンドにダイナミクスが生まれていますね。ノイズにしても膨らみがあるというか。
「ウワーッってノイズを鳴らしているとき、そこに意味がなくなるとダレてきちゃうことがある。そうならないように、ハイの部分とロウの部分の間にどんなふうに音を入れるかをメンバーで考えました。グルーヴに関しても同じですけど」
――グルーヴの面で意識したことはありました? アルバム全体に心地良い揺れがありますね。
「もともとウチは良いリズム隊がいるので、グルーヴの基盤のところをベースとドラムできっちり作ってもらって、そこにギターをどう入れて行くかというのを考えました。あと、旋律にもグルーヴがあると思うので、それをどうリズム隊と組み合わせていくかってところですよね。とにかく、ゆっくりな曲も長い尺の曲も、グルーヴィーであることは大切にしました」
――そこに乗る榊原さんのヴォーカルは甘くてルーズで、アレックス・チルトン感がありますね。
「アレックス・チルトンやチェット・ベイカー、エリオット・スミスとかそういうダメ人間の甘さみたいなものが好きなんですよ(笑)。尊敬するシンガーはいっぱいいるんですけど、自分に寄り添ってくれるのはそういう人たちだったりするので」
――親近感を感じる?
「自分と近いんだと思います。ちょっと、嫌なんですけどね(笑)。映画の『ハイ・フィデリティ』で、〈自分が惨めだからロックが好きなのか、ロックが好きだから惨めになったのか〉という話が出てきますけど、そういう感じですね」
――痛いほどわかります(笑)。個人的にはロックンロールって夢を掴む音楽じゃないと思うし。
「そうなんですよ。負け犬の音楽ですから。僕は負け犬が好きなんです(笑)」