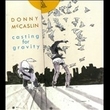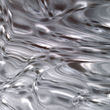『★』でめざしたサウンドの意図
――しかし、凄く変なアルバムですよね(笑)。先行発表されていた1曲目“★”から10分近くあるし。この曲もどのくらい書かれて(作曲されて)いるんですかね。展開はあるけど、即興で弾いてるような気がする箇所もかなり見受けられるし。
「基本的にはそうだと思いますよ。最初に思ったのは、書かれている感じがあまりないってことかな。書き譜だったり、(プロデューサーの)ヴィスコンティの細かい指示があったようには聴こえない。コード・チャートはあって、それをミュージシャン達に演奏させて、例えばダニーが吹いたフレーズを気に入ったら、そこにハーモニーを付けてセクションにするような手順。スコアで最初から最後まで配置した音楽ではないね。フルートのほかにストリングスの音も入っているけど、〈シンセかな?〉と思う曲もあったな」
――ヴィスコンティはこの1曲だけストリングス・アレンジを手掛けていて、あとの曲はシンセですね。
「ということは、ストリングスっぽい音はジェイソンがダビングで残って〈今の高い方のフレーズで入って、そのあと下がった方がよくない?〉とか、そういうやり取りをボウイかヴィスコンティとやって、ヘッド・アレンジを重ねていったものに聴こえるね。コード・チャートと、基本的な歌のメロディーは決まっていたと思うんだけど、あらかじめ綿密に作り込んでいた感じではないよね。だからジャズメンをフィーチャーしながら各自のキャラクターが死んでないし、プレイヤビリティーが発揮されているとも言えるね」
――そういえば、マークはMikikiのインタヴューで〈デヴィッドは全部の曲のデモを制作してきて、そこにはドラム・パートも含まれていたので、なるべくそれと同じ演奏になるように努力した〉と語っていましたね。実際、アルバム中で一番カッチリしていたのはドラムとベースだったし。でも、その後に〈もし彼が僕なりのドラム・パートを求めたらできるだけクリエイティヴな演奏になるようにベストを尽くした〉とも答えているから、その辺は曲によってなのかな。
「その記事を読んで、この人はマジメなんだなと思った(笑)。これも推測だけど、ボウイのデモは、そんなに細かい部分までこだわって作っていないと思う。だけど、ビッグネームだし、いい人らしいし、やりやすい環境だったと話しているし、そういう人が作ったデモテープだからね。そこには本人の意図があるんだろうと思って、がんばってその通り演奏したんじゃないかな。〈ドドン、タン、ドドン〉(“★”冒頭のリズム)となってたら、それをきちんと叩くわけですよ。もしデモがなくて、コード・チャートだけだったとしたら、また全然違ったと思うの。あくまでもデモを尊重して崩しすぎないマークのマジメさ。そこにいちばんニッコリしたね」
――実際にマジメでいい奴ですよ(笑)。このメンツで、こんなにわかりやすいリズムのロック・サウンドをやっているのはびっくりしましたね。でも、あのドラムの硬質な音色を聴くと、やっぱりマークの叩く音だなと。
「そう、どこを聴いてもマーク・ジュリアナらしいんだよね。だけど、リズム・フィギュアとしてはそんなに複雑ではない。そこがいいバランスなんだよね。ボウイはプログレ的なサウンドもやったことある人だから、今回のメンツを知ったときにデコラティヴ(装飾的)なアルバムも想像していたけど、実際には派手さよりも、芯の部分だけずっと見せるアルバムだなって」
――ベースもそうですよね。ティム・ルフェーヴルはドナルド・フェイゲンのサイドマンを務めたり、ウェイン・クランツとプログレッシヴなジャズを演奏したりしている超絶技巧の持ち主なんですけど、ここでは彼も割とシンプルな演奏をしていますし。
――その一方で、冨田さんもお気に入りのジェイソン・リンドナーは好き勝手やってましたね。ウーリッツァーやシンセでエレクトロニックなウワモノを作るように演奏するのも得意な人ですけど、その個性も反映されていて。
「そうだね。最初の“★”でもキックに合わせてシンセを鳴らしたり、そういうサウンド構築の部分に尽力している感じがありましたよね」
――リズムは決まったものを忠実に叩いていて、ミックスで前に出ているからマークが目立つんですけど、サウンドの比重はかなりジェイソンにありそう。
「要所要所でいい働きを見せている気がするよね。ジェイソンはプレイヤーとしても立派ですけど、どちらかというとサウンドメイキングに頭が行く人だから、ソロを派手に弾いたり目立つタイプではない。だけど、全体のバランスを作り出しているのはジェイソンという気はしたかな。でもキーボード・オリエンテッドな音像ではないんだよね。弾きすぎたりもしない、その辺のさじ加減が絶妙ですよね」
――たくさん演奏している感じはしないけど、全体のムードを作っているというか。
「そのバランス感覚は今回のアルバムでいい方向に働いているよね。やっぱり目立つのはマークのドラムだし、ダニーのサックス・ソロも凄く多いし、ベン・モンダーも歪み過ぎくらいの音でたっぷり弾く場面もある。それはボウイがジャズ・ミュージシャンにロックをやらせたいと思ったから。ここでキーボード・オリエンテッドにしてしまうと、もっとポップス寄りになっちゃったかもしれない」
――録音やミックスに関してはどうでしたか?
「彼ら(ジャズ・ミュージシャンたち)のアルバムよりも、プロフェッショナルなエンジニアリングが施された音像になっているよね。だから良く出来ているというか、〈ジャズ〉としてリリースされるものと、〈ロック/ポップス〉として作るものの肌触りの違いも感じたね。後者の感じで彼らの演奏を聴けるのは嬉しかった。マークの演奏もジャズの生々しい感じとは違って、上手くトリートメントされているし。曲によってはスネアにエフェクトが掛かっていたりして」
――ダニーのサックスが凄く引っ込んでいたりしますよね。
「そういう(音量の)上げ下げもかなりしていると思うね。ジャズのミックスだとあまりないことだけど、ポップスは上げ下げだけで何時間も費やすから。あと、ボウイの歌は一番最後に乗せたような感じだよね。ずっとハモる箇所でディスコードしていても、さほど気にならないバランスにもなってる。たぶんエディットもしていると思うんだ」
――ですよね。ヴォーカルだけセッション感がなくて、出来上がったトラックに取って付けたような感じ。ボウイの歌と今日のジャズをリンクさせるとしたら、テオ・ブレックマンが参照できるかなと。ECMからアルバムを出したり、ケイト・ブッシュの作品集を発表したりしている白人ヴォーカリストで、ベン・モンダーともよく共演しています。オペラチックというかクラシック的な歌唱をする人で、グリッドがないというか、上ものっぽく聴こえるんですよね。
「そういえば、昔ボウイがパット・メセニーと一緒にやった“This Is Not America”という曲があったじゃない。『コードネームはファルコン』(85年)という映画のサントラに入ってた曲で。あれ好きだったんだよね(笑)。僕が聴いたのは大学時代で、そのときに音楽仲間と〈ボウイの声の威力が凄い〉という話になって。〈This Is Not America, Nooooooo!〉ってフレーズがあるんですけど、その〈Nooooooo!〉という一発が凄くて、異常に耳に残っていたわけ」
――〈Sueeeeee!〉(“Sue”の出だしのヴォーカル)もそうじゃないですか?
「あ、そうだね(笑)。そういう一発というか、説得力のある声の持ち主だよね。当時はまだ学生だから、自分で楽器を弾いてたりすると音楽の構造にばかり耳がいきがちじゃない? そのときに先輩方から〈歌ものにおいてはそういうことじゃないんだよ、そんなものはこの声一発にもっていかれるんだよ〉と言われたのを思い出したりね。ボウイとジャズの接点ということで聴き直したら結構良くて、YouTubeに2000年のライヴ映像もあってさ。〈これはずっと封印していた曲だけど、演奏するよ〉みたいにMCしてから歌ってました」
――その時期のバックバンドは、少し雰囲気がジャズっぽいですよね。ボウイとは付き合いの古いピアノのマイク・ガーソン※も参加しているけど、彼の出自もジャズだし。
※73年作『Aladdin Sane』から2003年作『Reality』まで、8枚のアルバムに参加
「ボウイのキャリア初期に、ヴィスコンティがスタジオでメンバーを揃えたなかにジョン・マクラフリンを入れてたりとかね。ヴィスコンティもNY出身のジャズをやっていた人で、埒が明かないからイギリスに渡って成功したんだと何かの本で読んだことがあるな。あと、ジャズ・ミュージシャンが全面参加しているというので、思い出すのがスティングの作品におけるブランフォード・マルサリスやケニー・カークランド、オマー・ハキムだよね。時代もミュージシャンも違うし、同じイギリス人ながらボウイとスティングの音楽性の違いは顕著だけど、方法論はどちらも同じだよね。スティングはリアルタイムだったけど、あれはワクワクしたもんね。隅から隅までジャズの人が参加して、ミュージック・ビデオでも彼らの演奏がフィーチャーされていた。しかも、格好良かったんだよね」
――ロック/ポップスにおけるジャズメン全面参加作といえば、ジャコ・パストリアスやマイケル・ブレッカー、パット・メセニーらが集ったジョニ・ミッチェル『Shadows And Light』(80年)があって、そのあとにスティング『The Dream Of The Blue Turtles』(85年、邦題:ブルー・タートルの夢)という感じですよね。
「〈ブルー・タートルの夢〉は自由だったよね。リハの演奏をそのまま使った感じもあって。『Shadows And Light』もジャズ・ミュージシャンが勝手にやってる感じが凄い。オフィシャルの録音はきちんとしているけど、ほかの音源だとグチャグチャなテイクもあってさ。でもジョニ・ミッチェルの場合は、ジャズっぽい要素が自分のなかに入ってきて、それがだんだん濃くなって、『Mingus』(79年)を出して――という音楽の流れがわかるよね。でも、ボウイはそのときの興味で変えてる。だからボウイは音楽家っぽくはないんだよね。シンガーというか、そのときに自分がバックにして歌ったらカッコイイと思う音楽をやらせているというか」
――コンセプトメーカーというか。あと『★』には、LCDサウンドシステムのジェイムズ・マーフィーがパーカッションで参加していますよね。当初はプロデュースの依頼もあったそうですけど、彼はボウイに強く影響を受けていて、ボウイも彼にリミックスを依頼している。『The Next Day』のリリース後にボウイが客演した、アーケイド・ファイアの“Reflektor”という曲のプロデューサーもジェイムズで。
――今回ボウイがジェイムズに声をかけたのは、LCDが2000年代に更新したロック/ダンス・ミュージックの可能性を採り入れつつ、生演奏でさらにアップデートしたかったのかな、とも思います。だから『★』での演奏も妙にシンプルなのかなって。ジャズ・ミュージシャンが参加しているから、アルバム全体がジャズっぽいかというとそうではない。ジャズもそうだし、ブラック・ミュージックのフィーリングもまったくないですよね。
「ないね、まったくもってボウイの音楽だよね」
――ジャズ・ミュージシャンの音色とサウンド感が入っただけで、いままでと変わらない部分も多いですよね。
「無理やりルーツを探しても、強いて言えばフォークっぽいと言われれば〈そういうところもあるかな〉というくらい。白人の音楽だよね。だから、ケンドリック・ラマーの『To Pimp A Butterfly』(2015年)を聴いていたという話もあるけど、〈黒人の彼らがブラック・ミュージックとしてあれをやるなら、黒人でない僕らはどう行こうか〉と考えた可能性はある」
――以前からボウイのキャリアはそこに意識的だったとも言えますよね。『Young Americans』でも、白人である自分が歌っているから〈プラスティック・ソウル〉なんだと話していたり。
「マーク・ジュリアナが、どこかのインタヴューでロバート・グラスパーに言及していて。そのときに〈彼らがソウルをやるのは当たり前で、僕がソウルを取り上げたいと思ったとしても、自分はそういうルーツを持っているわけではない。だからテクノとか、そういう方向に行くんだ〉みたいな発言をしていましたね。黒っぽい要素を採り入れるのは違うというのは、彼にもあったみたい」
――マークもそうだし、ダニーやジェイソンも自身の作品で、ブラック・ミュージックとは異なる形の新しいグルーヴ・ミュージックを作ろうとしていますしね。ジャズに限らず、最近はヨーロッパも含めて、クラシックやフォーク、聖歌といった〈白い〉ルーツに接近している白人ミュージシャンの活躍が目立ちますね。『★』の最後の曲“I Can't Give Everything Away”にもフォークやトラッド、聖歌に通じるものを感じる。
「そうだね、フォークっぽい。『★』は黒さを意識的になくした可能性はありますね。9.11以降に、多くのミュージシャンがルーツと密接になっている……という話はよく聞くし。でも、それでタイトルが〈ブラックスター〉というのは凄いね(笑)。イギリス人がアメリカ人を起用してやり遂げようというのも、またひねくれてますし」
――“I Can't Give Everything Away”は唯一キーボードが強調された曲ですけど、それを弾くジェイソンも含めて、演奏に黒っぽさがないんですよ。特にベースはあれだけ前に出ているのに、全くファンキーじゃない。
「そうだね、ファンキーさがひとつもないね」
――あのベースでまったくファンキーにならないのは、凄いことだと思うんですよ。ティムはダニーのバンドや、マークの『Beat Music』でもプログラミング・ビートを人力に置き換えたようなグルーヴをマークとのコンビで生み出しているんですけど、そこでも全然ファンキーじゃないんですよね。ヴィスコンティが〈ロックにならないようにした〉と語ってましたけど、フュージョンにならないように意識しているのも感じますね。
「そう、フュージョンになっていないことも評価すべきだよね。こういう(ジャズメンを起用する)アプローチはフュージョンになりがちだから。あとは、ボウイの曲作りも大きいと思う。フュージョンになりえない曲で、骨組みは完全なロックというか。スティングの場合は、〈これはジャズ・ミュージシャンに演奏させたくなるだろう〉という曲だったけど、ボウイに関してはハッキリ言って、この曲をなぜジャズ・ミュージシャンに演奏させたかったのかわからないよね(笑)。いままで自分がやってきたロックとは決別したい、けど作風は変えない、だからジャズ・ミュージシャンを使ってみる、という発想かな。ジャズのイディオムが必要な曲では全然ないし、そういったミュージシャンのテクニックも特別必要な気もしないし」
――アルバム全編でインタープレイ、みたいな感じもないですもんね。
「ドラムンベースっぽいパターンだとしても、シンプルにすればシェイクになるわけで、ロックの人でもそのリズム・パターンは叩けるんだよね。では何が違うのかと言えば、リズムの精度とか、その高い精度によって受ける温度感が違うというのはあるよね。僕らはマークやダニーが作る音楽を以前から知っていて、その効果を知っているから、それが欲しくてジャズメンを呼ぶという発想に直結するかもしれないけど、一般的に考えると、ジャズ・ミュージシャンを必要とする効果ではないよね」
――ケンドリック・ラマーの『To Pimp A Butterfly』は、ロバート・グラスパーやカマシ・ワシントン、サンダーキャットなどの演奏がスウィングしていて、ジャズのど真ん中なプレイを披露しているから、ジャズ・ミュージシャンにしかできないというのが理解できますけどね。
「あれは彼らを呼ばないとできないもんね。ボウイがケンドリック・ラマーのアルバムを聴いていると知って、最初は〈おお!〉って思うじゃん。それで(ボウイが)ジャズメンを呼ぶというのも合致するじゃん。よく考えたら、作曲の部分でケンドリックにインスパイアされているはずもないんだけど。とはいえ、ジャズ・ミュージシャンを呼んで作ろうぜとなって、〈To Pimp~〉も聴いて、それで出来上がった曲がこれでしょ。なんか、いろいろおかしいところがあると思うんだよね(笑)」
――少なくともサウンド面では、若い世代のジャズ・ミュージシャンが参加しているところしか共通点が思いつかないですよね。
「でもだからこその、この温度感でもあって。どこまで計算していたのかは、さすがにわからないけど。だって、前のアルバム(『The Next Day』)のアレンジで全部できそうじゃない?」
――逆に言えば、前のアルバムの曲をこのメンバーでやっても大丈夫そうというか。でも、冨田さんがいま仰った〈温度感〉が重要なんですよね。演奏のテンション自体はすごく高いのに、温度感はクールにできる能力。
「それはマークのドラミングやジェイソンのサウンド構築に因るところが大きいかもね。ダニーやベンがいろいろ演奏しても、適材適所できちんと抑えてやっている部分でしょうね。ジャズ・ミュージシャンと言っても、世代的にはロックをやろうと思えばできちゃう人たちだから」
――だから僕の『★』への印象は、〈まだ名前の付いていない、新しい音楽を奏でるジャズ・ミュージシャン〉と、〈ロックから自覚的に離れたい、偉大なロック・ミュージシャン〉が一緒に作ったことで、これまでジャズ・ミュージシャンをフィーチャーしてきた作品と比べても、群を抜いて謎すぎるアルバムが出来上がってしまったという感じ。でも、いいアルバムなんですよ。内容がいいから余計にわからない(笑)。
「ジャズ・イディオムがほとんどゼロに等しいというのが、やっぱり胆じゃないかな。こういうケースだったら、普通はジャズっぽい瞬間がひとつくらいあるから。ジェイソンに〈どんどんリハーモナイゼーションしちゃっていいから〉と言えばその場でできるし、また全然違う感じになったと思うけど、そういうのも全然ないもんね」
――キーボードもジャズっぽいコードを弾かないし、サックスも力強いソロはあっても、スピリチュアルっぽく吹いたりはしない。
「ジャズっぽいハーモニーとか、ほぼゼロじゃないかな。普通の人が前情報なしで聴いたら、ジャズに関係があるとは思わないよね」
――だから、とんでもないスタジオ・ミュージシャンを集めたのと同じように受け止められかねないリスクもありそうですけど。
「彼らはアメリカの芸能界では、まだ実質的に無名だもんね。でも、あのデヴィッド・ボウイが目を付けたということで、ここから注目度が一気に、とか思うとワクワクするじゃないですか」
――このアルバムをきっかけに、ジャズ・ミュージシャンを使いたがる人が増えたらいいですよね。
「最近のジャズの傾向としては、〈グラスパー以降〉のJ・ディラとか黒っぽいサウンドにスポットが当たっているもんね。だから、そうじゃないほうの新しいジャズ・ミュージシャンによるサウンドということで、ここから広がることはあるかもしれない。黒くて訛ったリズムとは別の、いまっぽいリズムのおもしろさが伝わるといいね。〈ドラムがマークじゃなかったら全然違うじゃん〉みたいに」
――それぞれの参加ミュージシャンが持っている〈いまっぽさ〉を感じられると、アルバムの聴こえ方がまた変わってくる。
「絶対そうですよ。誰がどれだけ貢献しているのかがわかるというか。だから、『★』を聴いた後には、参加しているジャズ・ミュージシャンのアルバムも聴いてみてほしいですね」
PROFILE
冨田ラボ(冨田恵一)
音楽家、プロデューサー、作曲家、編曲家、ミックス・エンジニア、マルチプレイヤー。多数のアーティストにそれぞれの新境地となるような楽曲を提供する音楽プロデューサー。セルフ・プロジェクト〈冨田ラボ〉としても、これまでに4枚のアルバムを発売。著書に音楽書「ナイトフライ -録音芸術の作法と鑑賞法-」がある。直近のプロデュース作品はbirdの10枚目オリジナル・アルバム「Lush」。
★「birdと冨田ラボが新章突入! リズムへの好奇心&ポップスの哲学が凝縮した新作『Lush』を語るロング・インタヴュー」はこちら
柳樂光隆
79年島根県出雲生まれ。ジャズとその周りにある音楽について書いている音楽評論家。「Jazz The New Chapter」監修者。CDジャーナル、JAZZJapan、intoxicate、ミュージック・マガジンなどに執筆。カマシ・ワシントン『The Epic』、スナーキー・パピー『Sylva』、ホセ・ジェイムズ『Yesterday I Had The Blues』ほか、ライナーノーツも多数執筆。