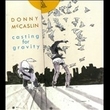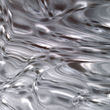2016年1月8日に69回目の誕生日を迎えたデヴィッド・ボウイが、ニュー・アルバム『★』をリリースした。史上空前のカムバックとなった2013年作『The Next Day』に引き続き、ボウイ自身と盟友トニー・ヴィスコンティがプロデュースを務めた本作では、NYの新世代ジャズ・ミュージシャンの全面参加が一大トピックとして注目を集めていた。近年はボウイのスポークスマン的な役割も担うヴィスコンティが〈彼らの音楽へのアプローチはとても新鮮だった〉と語る通り、ダニー・マッキャスリン(サックス)、ジェイソン・リンドナー(ピアノ/キーボード)、ティム・ルフェーヴル(ベース)、マーク・ジュリアナ(ドラムス)、ベン・モンダー(ギター)の5人はダークで刺激的なサウンドに大きく貢献。前作よりも遥かにスリリングな内容となっている。
それでは、なぜボウイはこのタイミングでジャズを選んだのか? 本人が一切のインタヴューに応じず沈黙を貫いている以上、真実は明かされぬままだ。しかし、2015年を代表する一枚となったケンドリック・ラマー『To Pimp A Butterfly』もそうであった通り、エレクトロニック・ミュージックやヒップホップなど様々なサウンドを貪欲に吸収し、まったく新しい可能性を模索し続けている21世紀の最先端ジャズ・シーンにアプローチしたことは、ロックという芸術様式を何度もアップデートしてきたボウイが、トレンドセッターとして未だ健在であることを作品のクオリティーでもって証明しているとも言えるだろう。
そこで今回は、ジェイソン・リンドナーやマーク・ジュリアナを通じて現代ジャズの独創性に魅了された音楽家/プロデューサーの冨田ラボ(冨田恵一)氏に、今日のジャズを紹介する音楽ガイド〈Jazz The New Chapter〉シリーズ監修の柳樂光隆氏がインタヴューする形で、『★』の参加ミュージシャンや作品の魅力、ボウイの制作意図などについて語ってもらった。約13,000字のヴォリュームで、ミステリアスな輝きを放つ黒い巨星の謎に迫る。 *Mikiki編集部

ボウイが5人のジャズ・ミュージシャンを選ぶまでの経緯
――冨田さんはデヴィッド・ボウイってお好きでしたか?
「そもそも(リスナーとして)熱心にロックと接してきたとは言えないけど、ブライアン・イーノにはずっと興味があって。〈ベルリン三部作〉と呼ばれている作品もその観点で聴いてますね。自分で最初に買ったのは『Young Americans』(75年)。僕はソウルも含めアメリカの音楽が好きだから、イギリス人のボウイがそういう音楽に接近したことに興味を持ちました。で、リアルタイムでは『Let's Dance』(83年)。だからボウイには、自分でトレンドを見つけたら〈いまはそっち!〉とガバッと振り切る人というイメージを持っています。今回は、やっぱりマーク・ジュリアナとか最近のジャズにおけるムーヴメントが、ロックスターである彼の眼にも興味深く映ったんだなって、そういうワクワク感があるね」
――確かに、フットワークの軽い人ですよね。
「だってさ、ベルリン三部作と『Let's Dance』って別の音楽じゃない? あとは90年代に『Earthling』(97年)でドラムンベースを採り入れてるでしょ。リズムは思い切りそうなってるんだけど、コード進行は以前からのストレートな3コードっぽくて〈あれれ?〉って感じもあったり(笑)。ちょっとちぐはぐだけどね」
――ある時期のU2もそうだった気がしますね。ロックの人がリズムだけダンス・ミュージックと入れ替えたら、ぎこちなくなったという。
「そう、U2の場合は『Zooropa』(94年)で整合性が取れたけどね。ボウイは『Earthling』の後にドラムンベースはやってないよね。あれは〈いま、ドラムンいいね〉というノリでリズムは本物に近付けたんだけど、リズムにのみ意識がいって、曲調までは対応できなかったんじゃないかな。でも、〈いまはこれなんだ〉とそのときに動ける。今回もそういうわけだけど、制作の経緯としてはダニー・マッキャスリンのバンドが気に入ったのがきっかけ……ということでいいのかな?」
――そうですね。もう少し遡ると、ボウイのコンピレーション『Nothing Has Changed』(2014年)に新規収録された“Sue (Or In A Season Of Crime)”を、マリア・シュナイダー・オーケストラと一緒にレコーディングしたのが『★』のスタートでもあったのかなと。マリアはジャズとクラシックの両ジャンルでグラミーを受賞し、ジャズのラージ・アンサンブルに革新を起こした作曲家で、ダニー・マッキャスリンは彼女のアルバム『Concert In The Garden』(2004年)でグラミー賞ベスト・ソリストに輝き、マーク・ジュリアナやベン・モンダーと共に“Sue”にも参加しています。
――その後にマリアが、NYの55バーというライヴハウスに、ダニー・マッキャスリンのライヴを観に行くことをボウイに薦めたそうです。ダニーは自身の率いるバンドでは、マーク・ジュリアナの人力テクノ的とも言えるビートや、ジェイソン・リンドナーのエフェクティヴなシンセ/エレピを積極的に活かして、ジャズとエレクトロニック・ミュージックを融合したようなバンドをやっている。リーダー作の『Casting For Gravity』(2012年)にはボーズ・オブ・カナダ、『Fast Future』(2015年)にはエイフェックス・ツインのカヴァーも収録していたりと、先鋭的なアプローチを見せていますね。
「『★』のバンドは、ダニーのバンド・メンバーである4人(ダニー、マーク、ジェイソン、ティム)全員にベン・モンダーを加えたものですよね。やっぱりボウイは、何かと何かを組み合わせるのではなく、バンド全員をそっくりそのまま持ってくるんだよね。その方法論がおもしろいよね。個人的には、『★』にも数曲マリアのオーケストラが入っているかなと期待したんだけど」
――“Sue”に話を戻すと、ドラムスを叩いていたのがマリアのオーケストラのメンバーであるクラレンス・ペンではなく、マーク・ジュリアナだったというのが重要なポイントですよね。ちなみにマーク本人は、ダニーがマリアに紹介してくれたんだと語ってました。
「ここからは予想だけどさ、ボウイはジャズ・オーケストラ的な感じでやりたくてマリアに頼んだんだよね。そこでクラレンスのバック・ビートだとソウルっぽすぎるというか。もうちょっとロックっぽいフィーリングを出せる人が適任だと考えたんじゃないかな」
――ですよね。
「最初はクラレンスでやってみて、ボウイが〈バックビートに違う感じが欲しいんだよね〉とか言って、マリアが〈えー! いや、いいんだけど……〉みたいなやり取りがあって。それでマリアがダニーに相談して……みたいなさ。あと、ベン・モンダーもマリアのオーケストラにもともと参加していたんですよね?」
――そうです。現在のギタリストはラーゲ・ルンドで、その前がベン・モンダー。『★』にもそのプレイスタイルは反映されていますけど、マリア・シュナイダー・オーケストラ初期の代表作とされる『Evanescence』(92年)の頃は、いわゆるジミヘン的なディストーションの掛かったエレクトリックなギター・ソロが入っているんですよね。その後にベンが抜けてラーゲ・ルンドになってからは、ブラジル音楽の要素が強くなってマイルドな音楽性に変わっていきました。そこを踏まえると、ボウイは初期マリア・シュナイダー・オーケストラの音が欲しかったのかなという気がしますね。“Sue”は近年のマリアの音ではないので。ダニーのサックスもアンサンブルの調和に囚われすぎず、〈ブギャー!〉と勢いよくソロを吹いてますし。管楽器のユニゾンでわかりやすい音が入ったりするのも、いまのマリアっぽくない。
「“Sue”や『★』にはまったくブラジルの要素ないもんね。だから気になるのは、ボウイがマリアに何を求めていたのか、レコーディングのときにマリアへどんなことを伝えていたのか、ですよね。それについて、マリアやトニー・ヴィスコンティは何か言ってないのかな?」
――マリアとのコラボに至った本当の理由は、まだ誰も明かしていないみたいで。だから推測するしかない。
「でも、そういう推測するのはおもしろいよね(笑)。語らないということは、出来上がりに満足していないというのもあり得るからね。近年のマリアの綿密なアプローチとは違うし、もしかしたら彼女としては本意の仕上がりではなかったのかもしれない。『★』にマリアがいないのも謎」
――マリアは完璧主義者なので、それはあり得ますよね。そもそもクラレンス・ペンはマリアのバンドの要だし、その一番大事なポジションが入れ替えられているのがすごく不思議で。
「それでむしろ、ボウイはマリアのオーケストレーションよりもリズムの方をおもしろがっちゃったのかもね。これも100%推測ですけど。〈もうちょっとロックのフィーリングを入れたい〉とか」
――ラーゲ・ルンドも名手だけど、オーセンティックなジャズ・ギタリストのスタイルで、そのなかでも特に繊細なプレイヤーなんですよ。〈あのギタリストはちょっと物足りない〉みたいな感じで替えられた可能性はありますよね。一方でベン・モンダーは、ただノイジーに弾くだけじゃないし、自分のリーダー作でもいろんなことに挑戦しているんですよ。『Hydra』(2013年)はアコギのアルペジオを多重録音してシューゲイザーみたいな音像を生み出しているし、ECMからリリースされた『Amorphae』(2015年)は浮遊感のあるサウンドで音響系みたいにも聴ける。どちらが『★』に必要なのかは明白ですよね」
「〈既存のメンバーを起用しても従来のサウンドと同じになってしまうから、ジャズ・ミュージシャンにロックを演奏させた〉みたいにヴィスコンティが語っていたけど、実際に演奏するのはロックだし、ボウイにとってロックのフィーリングは大事なものだと思うんだよね。マークやベンはそれを持っているけど、クラレンス・ペンはグルーヴィーには叩けても、ロックっぽいとは言えないもんね。簡単に言うと黒っぽいし、ソウルフルなものになってしまう」
――マークはロックにおいても同時代的なセンスを持ってますもんね。『★』を聴くと、“Sue”でマークのドラムを聴いてから、ボウイのなかでアルバムの全体像が出来たんだろうと思わせる部分があって。先ほど話に出たダニーの『Fast Future』、マークのリーダー作『Beat Music: The Los Angels Improvisations』(2014年)、ジェイソン・リンドナーが率いるナウVSナウの『Earth Analog』(2013年)は、いずれもマークがドラムを叩いていて、機械のように正確で体温の低いビートが作品の胆なんですけど、『★』はその3作と共通するサウンドという感じがしますね。
「そういう気がする。『★』では“Sue”もオーケストラなしのバンド・サウンドで録り直しされていて、異常にドラムンベース感が増しているもんね。そこでも僕らがたてた推測に合致する」