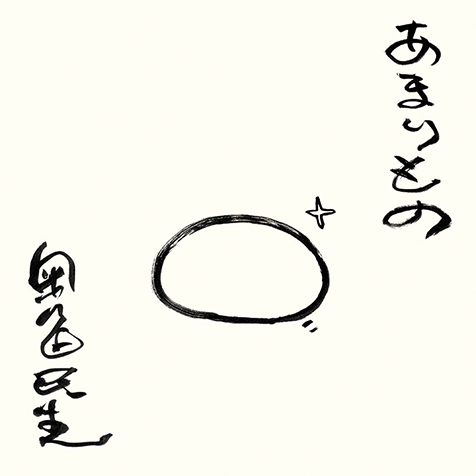98年から活動する、テキサス州オースティン出身のオッカーヴィル・リヴァー。実質的にはウィル・シェフのソロ・プロジェクトであるこのバンドは、これまでに8枚のアルバムを発表、現代的なルーツ・ロック~アメリカーナ音楽を模索してきた。そのキャリアを通じてノラ・ジョーンズや亡きルー・リード、ライアン・アダムス、ロッキー・エリクソン(!)などと交流を重ねた彼らには、新旧アメリカを代表するミュージシャンたちが厚い信頼を寄せている。
そんなオッカーヴィル・リヴァーの前作『Away』(2016年)のテーマは〈人生の終わり〉。祖父や敬愛する音楽家たちの死に着想を得た作品だったが、2年ぶりの新作『In The Rainbow Rain』からは一転してポジティヴなムードが感じられる。その秘密は、サウンド・プロダクションにあり? モダンなロック・サウンドを定義したアラバマ・シェイクスの傑作『Sound & Color』(2015年)のエンジニアであるショーン・エヴェレットがミックスしたという事実を手掛かりに、本作のユニークな音作りをOkada Takuroこと岡田拓郎が分析した。 *Mikiki編集部

このロック下火時代に……
ジャクソン・ブラウン、ランディー・ニューマン級のグッド・ソングを書けるインディー・ロック畑のシンガー・ソングライターといえば、ファーザー・ジョン・ミスティ、デストロイヤー、そしてオッカーヴィル・リヴァ―ことウィル・シェフを挙げたい!
2年ぶりとなるオッカーヴィル・リヴァ―の新作『In The Rainbow Rain』。ヴァン・モリソン『Astral Weeks』(68年)も引き合いに出された暖かみのあるアコースティックなバンド・サウンドに、yMusicのメンバーを中心としたコンテンポラリー・アメリカーナ的ストリングスとホーン・アレンジ、そしてウィル・シェフのナイーヴな歌声が絡み合った前作『Away』と本作とでは、冒頭の一音を聴いただけでもガラリと様相が異なっている。
2016年12月。かつてフランク・シナトラが住んでいたカリフォルニアはパーム・スプリングスの家に隣接する別荘で、ウィルが“The Dream And The Light”を書き上げたところから、本作の制作が始まった。その後、ウィルは『Away』を制作したキャビンに再び籠り、また新たな曲をいくつか書いた。バンドでスタジオに出向いての初めてのセッションでは、3日の間に10曲のレコーディングをしたそうだ。そのセッションで録音されたのは、“The Dream And The Light”、“How It Is”、“External Actor”、“Pulled Up The Ribbon”、“Famous Tracheotomies”の5曲。
ひとつの部屋に集まってバンド・メンバーで同時録音されたという事実は、本作のグリッドされたような、固めの音像からすると少し意外にも思える。このセッションを振り返るウィルのコメントには、「新たな楽曲たちは『Away』のサウンドを受け継いだものになるように意識して作っていたけれど、スタジオに入ってほとんど即座に、かなり大きく方向性が変わりはじめた。よりエレクトリックで遊び心に満ちた、ハッピーなサウンドへとシフトしたんだ。なぜなら、僕自身がここ数年間でいちばんハッピーだったから。僕はその方向性で進めていくことに決めた」とある。
〈このロック下火時代に……〉などと書くのも聞くのも、もう本当にウンザリではあるが、鬱屈としたルサンチマンを抱えた〈インディー・ロックイズム〉に対する作品として、ベック『Colors』と本作『In The Rainbow Rain』は、どこか重なるところがあるかも知れない。または、ちょうど2017年頃から、霊的な体験を重んじるクエーカー教徒のコミュニティに定期的に足を運んだウィルの変化は、幻覚剤のマイクロドージングをはじめたそうだが、それは、不思議なキノコによってチャクラが開いてしまった(!?)J・ティルマンからファーザー・ジョン・ミスティへの変化にも通じるかもしれない。
アラバマ・シェイクス『Sound & Color』のエンジニアがミックス
アルバムへと話を戻すと、前回から2ヶ月ほど置いた後、新たな楽曲のアイデアを携え、バンドのメンバーたちと共にブルックリンで再びセッションが再開され、“Family Song”、“Shelter Song”、“Human Being Song”、“Love Somebody”の録音が行われた。本作のミキシングはショーン・エヴェレット。アラバマ・シェイクス『Sound & Color』を手がけ、その後もジョン・レジェンド『Darkness And Light』(2016年)やパフューム・ジーニアス『No Shape』、ウォー・オン・ドラッグス『A Deeper Understanding』、グリズリー・ベア『Painted Ruins』(2017年)などに携わった、各所で引っ張りだこのエンジニア/プロデューサーだ。
流行なきゆえに散り散りになったロック・シーンのなかでも、近年、ロック・バンド・フォーマットでの録音物の数少ないトレンドとして、アラバマ・シェイクスの『Sound & Color』のサウンドが挙げられるだろう。アナログ・コンソールのビリビリとしたふくよかな歪み成分を過激に押し出した、ダイナミックなアタック感。ヒップホップ的な重心の低い帯域感。近距離のマイクで収音したと思われる、張り付くような聴感の、各楽器の分離の良い音。今回、ブライトで風通しの良いドライなロック・バンドに生まれ変わったオッカーヴィル・リヴァ―にとって、エヴェレットをミキシング・エンジニアに選んだのは最良の選択であったと感じる。
『In The Rainbow Rain』のサウンド・デザインとは?
ここからは『In The Rainbow Rain』の収録曲を一曲ずつ聴いていこう。まずは1曲目、トレードマークであるアコースティック・ギターのフィンガー・ピッキングではなく、立体的なウーリッツァーをバックに、ドライなヴォーカルで幕開ける“Famous Tracheotomies”は、ウィルが幼少期に、長く病院での生活を過ごしていた頃のことを歌ったナンバー。2017年にリリースされたデストロイヤー『Ken』(2017年)のサウンド・プロダクションを思わせる、エレクトロ・ビートと空間的なエレクトリック・ギターの絡みは、これまでのフォーキーなアメリカーナ的サウンドから一転、ニューウェイヴィーで硬質な仕上がりとなっており、従来のファンは面食らうだろう。
続く“The Dream And The Light”は、アコースティック・ピアノとシンセを交えたアンサンブルの、ウォー・オン・ドラッグス直系ハンマー・ビート・アメリカン・ロック。中盤のスラップ・エコーで味付けされた抜けの良いサックス・ソロもあって、なんともブルース・スプリングスティーン的だ。3曲目の“Love Somebody”は、バンドのベーシストのベンジャミン・ラジャール・デイヴィス、ギタリストのウィル・グレーフェとの共作。4曲目“Family Song”は、点で打つリズム・ボックスと長めの音符で奏でるウワモノのアンサンブルが、オリエンタルなフィーリングを織りなしている。
もともとは8分近いスロー・ワルツだったという5曲目“Pulled Up The Ribbon”は、無数の別ヴァージョン(初期のスコット・ウォーカー風や、パンキッシュなモータウン・アレンジなどを試みたそう)が出来上がる程、繰り返し書き直されたという。テーム・インパラを思わせる重たいキックにコズミックなシンセが重なるサイケデリックな仕上がりとなっている。
現代的サウンドと、70年代の良質なアナログ録音と
アナログ・レコードでは、ここからB面。6曲目“Don't Move Back To LA”は、レイドバックしたオーセンティックでフォーキーなアメリカン・ロック。ようやくここで、以前からのオッカーヴィル・ファンにも馴染みのあるフィーリングがあるように感じるかも知れないが、やはりショーン・エヴェレットらしいグリッドされたような端正なドラムスの処理、ボトムの低さは非常に現代的だ。
7曲目の“Shelter Song”は、リズム・ボックスがヒプノティックに反復されるなか、ドリーミーなシンセが散らばるトラック。甘いファルセット・ヴォイスも相まって、メロウなムードに惹かれる。デイヴィ・グレアム〜デヴィッド・クロスビーも多く用いた〈DADGAD〉のオープン・チューニング・ギターが特徴的な8曲目“How It Is”は、トラディショナルなアメリカン・フォーク的な香りをほとんど漂わせることなく、このチューニングの新たな可能性を引き出している。
ダン・ヒックスを現代的な感覚で解釈したような9曲目“External Actor”は、本作のなかでも、ドラムスはもっとも控えめ。軽快なギター・バッキングが転がるグッド・タイム・ナンバーに仕上がっている。こっそりと聴かせる間奏のホーン・セクションは、ヴァン・ダイク・パークス『Song Cycle』(68年)を思わせる。
そして、ラストの“Human Being Song”は、ショーン・エヴェレットらしい過激なサチュレーションやボトム感こそないが、こういったフォーク・ロック・スタイルの楽曲がもっとも心地良く、美しく映える70年代の良質なアナログ・レコーディング作品のような帯域感だと感じる。本アルバムのなかでも、脈々と続く北米シンガー・ソングライターの系譜としてのオッカーヴィル・リヴァー=ウィル・シェフの魅力がもっとも感じられる楽曲ではないだろうか。
ウィル・シェフの感情とサウンドがシンクロ
全編を通して聴くと、改めて〈ルーム成分〉をほとんど感じさせないことに気付く。各楽器の、耳に張り付くような距離感、エレクトロニクスをふんだんに使った煌びやかな質感は、前作『Away』のウォームでタイムレスなサウンドと比べると、非常に今日的なサウンド・デザインに劇的に変化したと感じられる。
けれどもそれは、時代や流行に照準を合わせたものではなく、痛みや悲しみを受け入れ、優しさを体現した『Away』を経たウィル・シェフが、新たなバンド・メンバーを得てポジティヴなムードになっていったタイミングと、今日的な音楽の持つブライトな感覚が奇跡的にシンクロした、といった表現のほうが近いように感じられる。
本作『In The Rainbow Rain』は、この2018年に、ひときわ軽快にポジティヴに響き渡ること請け合いだ。