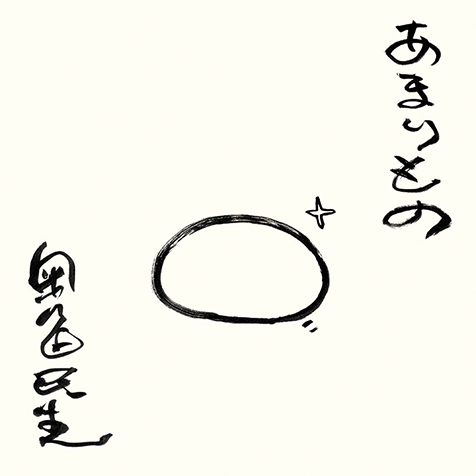4月1日にオールタイム・ベスト・アルバム『4×20 ~20 YEARS ALL TIME BEST』を発表するSCOOBIE DO。彼らがこの20年の間に、笑いながら&泣きながら踊らせてきた珠玉のナンバーがレーベルの壁を超えてCD3枚+DVD1枚の〈FUNKY 4〉仕様で収められている。ライヴの定番曲のみならず、デビュー前のデモ音源や未発表ライヴ音源、盟友たちが続々と登場するミュージック・ビデオも泣かせるスカパラ・ホーンズが参加した新曲“新しい夜明け”も含み、いわばスクービーの歴史を一気におさらいしつつ、これからも前進し続けるバンドの〈新たな門出〉もお祝いできる内容だ。
そんなベスト盤のリリースを控えた某日、Mikikiはスクービーのメンバーをキャッチ! 激動の音楽シーンで止まることなく着実に活動してきたバンドの歩みを振り返ってもらった。
SCOOBIE DOに会いに、下北沢に来た。数年前に小田急線が地下に潜り、駅周辺の景色もずいぶんと変わったな――そんなことを思いながら緩やかな坂を下り、待ち合わせの喫茶店(ここは昔からちっとも変わってない)に着く。街の景色ももちろんだが、音楽を取り巻く状況も変わっていくなかで、20年という歴史を刻んできたSCOOBIE DO。彼らはどんなところで〈時の流れ〉を感じていたりするんだろうか? まずはそんなところから話を始めてみた。
マツキタイジロウ(ギター)「見た目は大きいだろうね(笑)。でも、自分たちの中身っていうよりは、外を見て、〈ああ、あの人たちもういないな〉とか、そういうところで時間の流れを感じることのほうが多いですね。自分たちは20年前とやってること自体変わってないんですよ。週に1、2回リハに入って、新曲を合わせて、ライヴだなんだって曲を練って、そういうことを繰り返しやってて。曲とかネタはどんどん新しくなっているんだけど、やってる行為はまったく変わってない。やっぱり、長くやってる人たちっていうのは、バンドとしてやってる行為そのものが変わらないというか、それが楽しいからやってるんだろうし、そういう人たちがやり続けて、そうじゃない人が途中で違う道に行くっていう、そういうことだと思う。自分らも20年やってきて、そんなにすごいことをやってきたとは思ってないし」
――結果として〈すごい〉ということですよね。この20年というのは、音楽を取り巻く状況が決して良いとは言えない方向に変わっていった時代だと思うので、そこをサヴァイヴしてきたというのは〈すごい〉かなと。
マツキ「ちょっと上の人たちと話すと、フラカンにしたってTheピーズにしたってTHE COLLECTORSにしたって、みんなCDバブルの恩恵を受けてたんですよね。当時、そんなに売れてないっていったって、いまと比べたら0(ゼロ)がひとつ多いぐらい売れてたりして。そういう人たちが20年、30年やってるのと、バブルが弾けた頃からやってる20年では違うから、〈君ら可哀相だよね……〉って、ピーズのハルさん(大木温之)に言われて(笑)。〈腐ってたオレらでさえイイ時代にデビューしてるからいまでもやってられるんだよ、オレがSCOOBIE DOだったらここまでやってないよ〉って(笑)」
――デビューするのが5年早かったら景色が違ってたでしょうね。でも、ひとくちに〈20年〉って、結構な時間ですよね。これを機会に当時のことを振り返ることも多かったと思いますけど。
コヤマシュウ(ヴォーカル)「20年前って、チビTとか流行ってた年ですからね(笑)。あとはプリクラとか、マライア・キャリーとかね。ぜんぜんピンとこない(笑)。その当時からまったく一線を画したところにいたんですね、オレら。まあ、ピンとくるのは野茂だけですね、野球好きなもんだから(笑)」
――ハハハ。そもそも、以前うかがった高校時代のエピソード※からして、一線を画した出発点だったんだなと思います(笑)。
※マツキが〈こういう音楽もある、日本の古い音楽もカッコイイんだぜ〉とコヤマに渡したカセットテープの最初に入っていたのがザ・ジャガーズ“ダンシング・ロンリー・ナイト”。流行りモノに乗る軽音楽部員を横目に、グループ・サウンズに心酔していた
マツキ「普通の高校生のような青春を楽しんでなかった(笑)。まあ、それで良かったんですけどね」
コヤマ「でも、アングラ狙いっていう意識はなかったですけどね。自分のなかでは真っ当な王道を進んでるつもりというか、いろいろあるなかからアングラなものを選んだんじゃなくて、最初からそこしか見えてない。端から見てると、まったく主流じゃない、いちばん端っこにいる人たちなのかもしれないけど、オレらはそういう意識はまったくなくて、これがいちばんカッコイイんだって思ってやってた、そういう感じでしたけどね」
――コスプレではなかったわけですね。
コヤマ「うん、ホントそう。最初からホンモノ志向だったんですね(笑)」
マツキ「発信してる形としてはすごくマニアックなものなんだけど、それがなんだろう……ヘンな言い方ですけど、現代の人が聴いてもカッコイイって感じられるものを作ろうっていうのは最初からあったんですよ。要するに、昔の音楽の模造品を寸分の狂いもなくコピーして出すっていうことじゃなくて、そういう要素をピックアップしながらも、いまの音楽として格好良く聴けるようなものを作りたいなっていうところで始めたんで、そのへんの志は、周りにいたバンドとは違ったのかな。とにかく良い曲を作りたい、ヒット曲云々ってことじゃなくて、〈ニクイね!〉って言われるような曲を作りたかったから」
コヤマ「SCOOBIE DOを組んだとき、ミーティングをしてたのか与太話をしてたのかわかんないですけど、どういうバンドをやっていくのかっていう、それを書いたリーダーのノートがね、何年か前に実家に帰ったらあったって。オレはてっきり、その頃からザ・ヘアーとか好きだったから、〈4人組の格好良いリズム&ブルースをやるバンドになる〉みたいな、そういうコンセプトがそこに書いてあったのかなって思ってたら……違ったんだよね」
マツキ「〈ポップスとして通用するような音楽を作っていくバンドになる〉みたいなことを書いてて」
コヤマ「そうそう、そうだったんだ!って。最初から名曲志向だったっていうか、自分がイイなって思う曲、グッとくる曲っていうのを作るバンドをめざしてたんだっていうのは結構びっくりで、最初っからそうだったんだって」
マツキ「オレもびっくりしたけどね(笑)。でまあ、黒い要素、踊れるとかグルーヴ感があるっていうことを前提にってことで、シンクロするバンドはその当時は自分のなかで浮かばなかったから、言葉にするとそういう感じだったんですよね」
――イイ話です……。ところで、SCOOBIE DOはメジャーでの活動経験もありながら、現在はプライヴェート・レーベルかつセルフ・マネージメントで活動しています。成果も緩やかながら右肩上がり……というところで、バンドにとっては鑑のようなところもありますよね。
マツキ「まあ、どうなんでしょうね。自分たちは必死でやってるだけですから、こうやったら上手くいくっていう方法もないですしね、時代も変わっていくし、音楽シーンも変わっていくし、同じことをやってればいいってことでもないし、若いバンドもいっぱい出てくるから日々研究だし、勉強だし、絶えず刺激を受けておかないとまずいなと思ってますけどね」
――結果、音楽を取り巻く状況は激変しても、立ち位置は揺るがないというか。
マツキ「揺らいでもおかしくないですけどね。やっぱり、楽器持って生で鳴らしてどうだ!って、4人で鳴らせる音楽っていうのが柱にあるから、何でもいいっていうわけじゃない。自分たちが良いなと思いつつ、やったときもしっくりくるものっていう、染みついた規準っていうものがあるんです。そこらへんは変わりようがなくて」
――つくづく〈代わり〉がいないバンドだなあと思います。
マツキ「SCOOBIE DOが好きならこういうバンド好きでしょ、みたいなのをTwitterとかでも見かけるんですけど、どのバンドにもオレらに当てはまらないような気がしてて。例えば、ディスコっぽい4つ打ちの曲ばっかりやるバンドでもないし、かといって在日ファンクみたいなコテコテのディープ・ファンクをやってるっていうわけでもないし、いろんな要素はあるんだけど、結局は〈スクービー節〉でまとまってるというか。で、その〈スクービー節〉っていうのは口では説明しづらいというか、〈日本語のファンクです〉とか〈日本語のリズム&ブルースです〉って言うのもちょっと違ったりして、でも、それが上手く説明できないから作り続けてるっていうところはあって。なんか20年やってると、それがスタイルになってくるというか、そういう感覚がある。〈ウチのバンドがやればウチのバンドの音になる〉みたいなことを答える人はいっぱいいると思うんですけど、本当にその通りで、それを20年間ちょっとずつ培ってきた、なんかそういう感じがしてるんです。だから、打ち込みをやってみようとか、あんまりそういう突飛な発想に行き着かないっていうか、とにかくスクービー節を入れたいっていやってきた20年なのかなって」