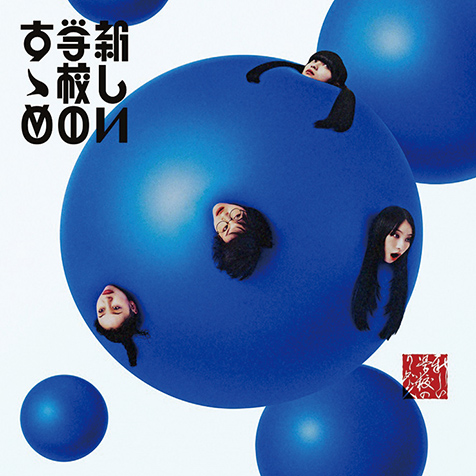日本のジュークが最近おもしろい、というのはややいまさらな話かもしれないけれど、多くのDJ/ プロデューサーが非常に表情豊かな作品を送り出しているのを日々見るにつけ、どうも気になって仕方ない……という編集部スタッフの勢いでスタートしたこの連載。いま日本のジューク・シーンはどうなっているんだろう?ということで、それを語ってもらうならこの人しかいない!と白羽の矢を立てたのが、関西を拠点にレーベル・Booty Tuneを主宰する日本でもっともジュークを知る男、D.J.Fulltono。彼の視点を通して、いま知っておくべきジャパニーズ・ジュークの面々や海外のレジェンドの紹介、さらには自身がこれまでに体験してきたジュークにまつわるエピソードなども披露してもらいます。さて第2回は、昨年4月に急逝したジューク発展の重要人物であり、Fulltonoに多大な影響をもたらしたDJラシャドのお話。

連載2回目の今回、記事を書き終える間際に重大なことに気付きました。4月26日はDJラシャドの一周忌。このタイミングでラシャドのことを書かなければ! そう決心し、せっかく書いた記事を思い切ってボツにて急遽DJラシャドの記事に差し替えることにしました。
これは真面目な話、ラシャドがいなければ、僕はいまほど真剣に音楽活動はしてなかっただろうし、あるいは音楽はとっくに諦めて月イチでクラブに遊びに行く程度の生活を送っていたはずです。
思い返せば、ジューク・トラックスからリリースされた数枚のEPを最後に、僕がDJでプレイしたいジュークやゲットー・テックといった音がまったくリリースされなくなってしまった時期がありました。2004年頃の出来事です。新しい音に出会えずDJはマンネリ化し、これから何を聴けばいいんだろうと暗中模索していた時期でした。
初めて聴いたラシャドの初期作品で相棒DJスピンとの共作曲。
この頃を最後にジューク関連のアナログ盤のリリースが途絶える
しかしジュークやゲットー・テックのレーベルは実はまだ潰れておらず、アナログ・リリースではなくデジタル・リリースに移行しているという情報を得た僕は、〈デジタル・リリース〉なんて馴染みのない言葉にピンと来ないままパソコンを立ち上げ、iTunesを覗いてみることに。するとそこには一晩ではとても聴ききれないほどの大量のEPがすでにリリースされていました。なかでも圧倒的なリリース量だったのがDJラシャドです。ただリリースが多かっただけではありません。一昔前のシカゴなノリのゲットー・サウンドばかりではなく、美しい旋律のメロディーであったり、サンプリング・ネタがヴァラエティーに富んでいたり、ベースの使い方も前より高度になっていて、音楽的な進化が確実に見られました。
これは後のトークショウでの本人の証言ですが、シカゴのレーベル、ダンス・マニアが崩壊した後の2001年、地元シカゴのキッズ数千人が集まるフロアで、彼は毎週ジュークやゲットー・ハウスをプレイしていました。その噂を聞きつけたデトロイトのDJゴッドファーザーから1通のメールが入り、その後活動の場をデトロイトへと広げます。デトロイトのクラブに初めて行った時に見たフロアはいままで見たことのない光景だったそうで、黒人だけじゃなくさまざまな人種が遊びに来るフロアでは、ゲットーなノリだけが求められたシカゴとは違い、より商業的なスタイルが求められたと言います。そしてそのリクエストにラシャドは完璧に答えました。それらの曲はジューク・トラックス・オンラインからリリースされた作品で聴くことができます。シカゴのゲットーなノリだけではないことが一聴瞭然です。
“In Da Club Before Eleven O' Clock”
一方、地元シカゴでもラシャドの勢いは止まりませんでした。DJギャント・マンがジューク・レーベルのバン・ザ・ボックス・レコーディングス(Bang Tha Box Recordingz)を設立。
盟友ギャント・マンの強烈なインパクトを放つヴォーカルをサンプリングしたこの“Juke Dat Juke Dat”は、当時のどのミックスCDにも、どの動画にも必ず入っている、おそらくシカゴのジューク・シーン史上もっとも多くプレイされた曲です。
ラシャドは、ジュークを広めるなんてことをしなくても音楽活動はシカゴだけで充実していたはず。しかし彼はこの音をシカゴの外に広めるという意識が人一倍強かったのです。彼がいなければいまなおジュークはシカゴだけのものだったと言っても過言ではないでしょう。
当時、そんなラシャドの思いなど知らなかった僕はシンプルに〈ジューク〉という音楽そのものに衝撃を受け、次に進むべき道が拓けた! この曲をみんなに教えたい!――そう気持ちを新たにし、自分でも曲を本格的に作りはじめたり、レーベルのBooty Tuneを設立したり、さらにはジュークを紹介するブログまで開始したり、相当意気込んでいたのを思い出します。
その後ラシャドは〈ゲットー・テクニシャンズ〉(Ghetto Teknitianz=テックライフの前身)を掲げ、若手を引き連れてさらに世界をめざすことに。この頃から作風にまた新たな変化が見られはじめます。
これまでリリースを続けてきたジューク・トラックス・オンラインから2009年に『Jukeworkz』というアルバムをリリース。これが耳に飛び込んできた時の衝撃はいまでもはっきりと記憶しています。収録曲の大半は、これまでのリスナーを困惑させるとんでもない内容でした。そのなかでも特にイカれていた曲を紹介します。
何なんだこの曲は! まず、曲の頭がわからない、小節の始まりが掴めない。どうやってDJで使ったらいいのか、そもそもどう踊ればいいのか。僕は困惑しました。当時DJでプレイすることができなかったのは言うまでもありません。でも、なぜこんな曲が生まれてきたのか、なぜいままでゲットー・テックやジュークといったダンス・ミュージックを作っていた人がいきなりこんな踊れないヘンテコな音をリリースしたのかが気になって仕方ありませんでした。
そしてその答えは1本の動画によりあきらかになります。
動画の0:35あたりからこの曲が流れてきます。この曲はシカゴのダンサーがダンス・バトルで踊るためだけに作られたトラックだったのです。
少し話が逸れますが、彼らはなぜこんな複雑な曲をスムーズにミックスできていると思いますか? これには秘密があります。ジューク/フットワークの曲はほぼすべての曲が160 BPMです。彼らはすべての曲を160 BPMで作ることによって、ミックスする際のピッチを合わせる作業を短縮しているのです。なので彼らはDJをする際にヘッドフォンすらしていません。この手法は現在のテックライフ・クルーにも受け継がれています。本当にシカゴらしいアイデアです。
これまで培ってきたデトロイトのゲットー・テックという流儀を完全に無視したこの変則的なビートは、突然変異だと当時は思っていましたが、そうではないことが後にわかりました。ラシャドはこういった変則的なビートを2000年初期から作っていましたが、その手法はデトロイトでは通用しませんでした。しかし、ゲットー・テックのスタイルからこれ以上の広がりが見込めないと悟ったのか、今度はシカゴのサウスサイドで起こっているダンスカルチャーごと世界に知らしめようという大胆なアプローチに出たのです。
その翌年、シカゴのゲットーファイルズ(Ghettophiles)というレーベルから名作“Space Juke”をはじめ、フットワークに特化した作品を次々にリリースします。そして同年、他に類を見ないこれらのトラックにすぐさま反応を示したのは、音楽的にこれまでまったく交わることのなかった意外なレーベルでした。
2009年にジューク・トラックス・オンラインから発表されたこの曲を、
UKのプラネット・ミューがライセンス・リリース
UKの老舗レーベル、プラネット・ミューがフットワークを積極的にフックアップしはじめたのです。この意外な展開にはびっくりしました。足を速く動かすためだけに作られたトラックがまったく別の用途で機能しはじめた瞬間です。ラシャドの名前は瞬く間にヨーロッパに広がりますが、果たしてこの音がUKのフロアで機能するのか、そして日本ではどう受け止められるのか。無理解なまま話題だけが先行しているようにも感じました。そんななか、その翌年に同レーベルからリリースされたフットワークのコンピレーションに入っている曲が凄く印象的。
この“Heaven Sent”は、ラシャドより先にジュークを武器にヨーロッパへ進出していたギャント・マンとの共作によるもの。複雑なリズムのフットワークとは対照的なストレートなビート、美しい旋律のシンセ・フレーズ――デトロイト・テクノのようなこの曲は、ラシャドの凄さを改めて感じる一曲です。これがこのタイミングでリリースされていなかったら、ジューク/フットワークは単なるアヴァンギャルドな音楽として認知されて終わっていたかもしれません。それは後にリリースされるラシャド最後のアルバム『Double Cup』にも言えることですが、彼は自分の音楽スタイルに誇りを持ちながらも、そのアウトプットは常に大衆へ向けられていると言えます。それはラシャドがデトロイトで勝負していた頃に培ってきた経験があってこそなせる技術。絶対にこの人は成功すると確信を得ました。
2012年、待望のアルバム『Teklife Volume 1: Welcome To The Chi』をリリース。この頃からみずからのスタイルを〈テックライフ〉と名付け、ジュークにもフットワークにも縛られず、かと言ってどのジャンルにも呑まれることなく、独自の世界観を提示するようになります。このアルバムはCD化されなかったため、日本の音楽メディアに取り上げられることは少なかったのですが、世界的には非常に高く評価され、ラシャドは一流アーティストの仲間入りを果たして数々のフェスに呼ばれることになります。
2013年に発表された”I Don’t Give A Fuck”。僕はこの曲がラシャドがこれまでに表現してきた音楽の究極のスタイルだと感じました。フットワークのグルーヴを突き詰めた結果、最後に出たのが〈ピー〉という音。これ以上の極限状態は他に存在しないのではないか……いや、まだ先はあったのかもしれませんが、本人がこの世にいない以上、いまとなってはわかりません。そして同年にハイパーダブからこの“I Don't Give A Fuck”も収録されたアルバム『Double Cup』がリリースされます。
実は『Double Cup』の日本盤がリリースされる際、日本限定のボーナス・トラックに入れる曲を選定するにあたってわれわれBooty Tuneも意見を訊かれたんですが、僕らメンバー全員で声を揃えて“Reverb”!!と、満場一致で返答。
ラシャドいわく〈日本盤にしか入ってないからアメリカの奴らはみんな怒っている〉とのこと
この曲はラシャドが地元シカゴのダンサーが踊るためだけに作った、ある意味シカゴ・ゲットーの究極と言える超変態トラックなのです。そんな一般リスナーを無視したような曲をハイパーダブのアルバムに入れるのはいかがなものかという気持ちはあったのだけど、〈日本は君がいままでやってきたことを全部見ていた〉ってことをラシャドに伝えたかったんです。その意見が採用されたからかはわかりませんが(笑)、結果、日本盤には“Reverb”が入ることに。
そして2014年1月。記憶にも新しい〈Hyperdub 10〉のツアーでラシャドが初来日を果たします。超満員のフロアを盛り上げる彼の姿は、こんな音楽が世界で通用するのだろうかという数年前の心配をまったく感じさせない完璧なプレイ。その光景は非常に感慨深いものでした。
自分にとってもっと感慨深かったのは、僕が東京公演のサブ・フロアでプレイしてる最中に、ラシャドがBooty TuneのTシャツを着て現れた時でした。ダンサーたちも集まってきていたので、僕はすぐさまダンサーを挑発する選曲へチェンジ。気付けば僕はラシャドの“Betta My Space”をプレイしていました。するとダンサーに挑発され、スイッチが入ったラシャドは我慢できずにサークルへ飛び出し、フットワークを踊り出しました。

Photo by Ayaka Ikegami
その姿は真剣そのもので、あまりの気迫にコード9が止めに入るほど(この後ラシャドは自身のDJが控えていた)。一緒に居合わせたダンサーのTAKUYAいわく〈殺されるかと思った〉とか。DJに専念すると言い、10代の頃にダンスを封印したラシャドがフットワークを踊ったのは日本だけだったそうです。
僕は最終公演の大阪でパーティー後に通訳を通してもらってラシャドに一言伝えました。〈あなたを信じていままでやってきて良かった〉と。本当に心からそう思いました。訊きたいことは山ほどあったけど、もうそれを伝えられただけで十分でした。これからどんどん交流が進んでいくと誰もが思っていましたし……。
しかしラシャドはその3か月後に突然この世を去ります。
早いものでラシャドが亡くなって1年が経とうとしていますが、僕はいまだに彼のビートを研究しています。彼の残した作品の遺伝子を自分のビートに注ぎ込むことで新しい境地に行けると信じているからです。しかし、2009年に聴いて衝撃を受けた”Betta My Space”のあの湧き出るエネルギーの正体が何なのか、いまだに掴みきれていません。DJラシャド、偉大なり。

Photo by 1945 a.k.a. Kuranaka
PROFILE:D.J.Fulltono

関西を拠点に活動するDJ/トラックメイカー。ジューク/フットワークを軸に ゲットー・テック、エレクトロ、シカゴ・ハウスなどをスピンする一方、自身のレーベル=Booty Tuneを運営。パーティー〈SOMETHINN〉も主催する。また、プラネット・ミューやハイパーダブでリリースされたジューク・関連作品の日本盤特典ミックスCDを手掛けるほか、国内外の音楽メディアへジューク関連記事を多数執筆。2014年に5作目のEP『My Mind Beats Vol.01』をリリースしている。