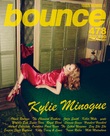DANCE ANOTHER DAY
ロミーの『Mid Air』から考える、ダンス・ミュージックのポップな広がり
The xxのシンガー、ロミーのソロ・アルバム『Mid Air』は、個人的にもっとも楽しみにしていた2023年のリリースのひとつだったが、初めてアルバムを聴いた際には少し肩透かしを食らった。というのは同作が、こちらの予想以上にド直球なダンス・ポップ作品だったからだ。もちろん彼女のそうした作風は2020年のデビュー曲“Lifetime”から一貫されており、意外でもなんでもない。だが、The xxやその首謀者たるジェイミー同様、ロミーにもある種の先鋭性を期待していたのだろう。フレッド・アゲインやスチュアート・プライスと作り上げたトランシーなサウンドには高揚感を喚起されつつも、楽曲の短さ、ややチージーなアレンジに物足りなさを感じたのも事実であった。
それが一転、何度も聴くうちに『Mid Air』は、優れたポップソングをめざした作品だと理解していく。ロミーが本誌も含む多くのメディアで語っていたように、同作は彼女のクィア・クラブでの体験を反映したもの。10代の頃に初めて足を踏み入れたパーティーで、そこにいる者たちがカッティング・エッジなサウンドではなく、誰もが知るポップソングで盛り上がり、それらを背景に愛を伝え合っていたことへの感動が作品の根幹を成している。同作でロミーは、そうした衒いのないダンス・ポップを歌おうとしたのだ。
全英チャートやBBCのラジオを聴いていても、同地の人々は本当にダンス・ミュージックや4つ打ちベースのサウンドが好きなんだなと思うことが多く、2023年のメインストリームでは、ファットボーイ・スリムをモロ使いした“Praising You”を含むリタ・オラの『You & I』、SGルイスの『AudioLust & HigherLove』などが記憶に残った。また、インディー寄りのアクトに目を向けても、ジョージアがロスタムを迎えて作った『Euphoric』、アリソン・ゴールドフラップのミュンヘン・ディスコ愛に満ちたソロ初作『The Love Invention』などが優れたダンス/ポップ作品だった。ジェシー・ウェアの傑作『That! Feels Good!』も含め、それらに共通する〈ポスト・コロナ〉時代を反映した開放的かつポジティヴなムードは、各作品の表題からも感じることができるだろう。
それと同時に、ストイックなエレクトロニック・ミュージック界隈を主戦場としてきたトラックメイカーがポップ志向を見せる局面も目立った。カナダのジェイダGは『Guy』(プロデューサーはジャック・ ペニャーテ!)で自身のヴォーカルにフォーカスし、スコットランドのバリー・キャント・スウィムはエクスペリメンタル・テクノをオーガニックな音作りで鳴らすなど、ニンジャ・チューンからはフロア・オリエンテッド過ぎない作品が登場。そのニンジャではジョージ・ライリーがハドソン・モホークやロレイン・ジェイムズらを招いたEP『Un/limited Love』も、エッジーなポップへの志向性が貫かれていた。なお、ライリーはジェイムズのアルバム『Gentle Confrontation』でも共演。ジェシー・ランザの『Love Hallucination』を含め、ハイパーダブからも歌に力点を置いた作品が続いた。さらには、グランド・ロイヤルっぽいハイブリッドなセンスに磨きをかけたイエジの『With A Hammer』、バレアリック・ポップな作風で驚かせたアヴァロン・エマーソンの『& The Charm』など、インディー・ポップ的な魅力を感じさせる作品も忘れ難い。
そして、独自のインディー、というかアヴァンなポップセンスでダンス・ミュージック・シーンに孤城を築くDJコーツェが全面バックアップしたロイシン・マーフィーの『Hit Parade』は、2023年のシンボリックな傑作だったと言えるだろう。マイクロ・ハウスやサイケデリック・ダブに繋がる享楽的な音作りと、主役のエモーショナルでディープな歌声が有機的に絡み合う様は、斬新ながらもチャーミング――〈これぞポップ〉と呼びたくなるチャームに溢れていた。