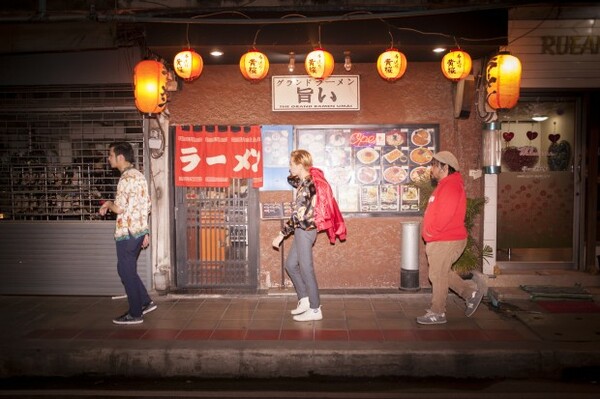J-Popは僕らにとって自己表現みたいなもの
それでは、日本のシティー・ポップスのどんなところに惹かれているのだろうか?
「日本の音楽文化は物凄く独自路線を行っていると、僕らは考えているんだ。とても興味深いよ。例えばアメリカの70年代から80年代のソフト・ロックやAORといったジャンルの音楽を、日本ではうまく採り入れて、新たなジャンルとして確立している。まさに僕らが好きなシティー・ポップといったジャンルがそうだよね。僕たちが所属しているレーベル、スモールルームでは渋谷系の楽曲をプロデュースしているし。とにかく、J-Popは僕らにとって自己表現みたいなものと言えるんだ」。
ナのフェイヴァリット・アルバムを訊いてみると、山下達郎『RIDE ON TIME』、安全地帯『安全地帯IV』、カシオペア『MINT JAMS』、久保田利伸『SHAKE IT PARADISE』といったあたりが挙がってきた。今回の来日ライヴでも、山下達郎“いつか(SOMEDAY)”と久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL“LA・LA・LA LOVE SONG”など、日本語のカヴァー・ソングを用意し、ヤンヤの喝采を浴びたと聞く。
アルバムを聴いてさらに思い浮かべるのは、角松敏生や大沢誉志幸、吉田美奈子、EPO、中原めいこ、杉山清貴&オメガトライブなど、その多くは80sのアーバン・スタイルを取り入れたアーティストたち。主なキメ手はポリフォニックな広がりのあるシンセサイザー群と、やや(イヤ、かなり?)チープなリズム・プログラミング。音はリヴァーブ感たっぷりながら、あまり奥行きがなく、立体感には乏しい。東南アジア圏の文化というと、ちょうど日本の昭和の時代に通じるモノがあるが、彼らの楽曲にはそうしたヴィンテージなサウンド、懐かしいテイストや空気感が蔓延しているのだ。だから当時をリアルに知る世代はノスタルジーを刺激され、メンバーと同じ世代はその手作り感覚を〈いままで体感したことがない〉とフレッシュに受け止める。
少し甘くナイーヴさを孕んだヴォーカル、美麗ながらも儚いコーラス・ハーモニー、そして耳馴染みの良いキャッチーなメロディー・ラインも、ポリキャットの大きな魅力だ。例えば、宅録で音楽制作に目覚めた人が、同朋を集めてバンド遊びを始めたような……。そんな身近さ、親近感がココにはある。
筆者が個人的に思い浮かべたのは、ビートルズのオーケストラ・アレンジを手掛けていた英国のポップ職人、リチャード・アンソニー・ヒューソンのシンセ・ポップ・プロジェクトであるラー・バンド。80年代前半にヒットを飛ばした彼らは、ブリティッシュ・ジャズ・ファンクの流れを汲んでいたが、砂原良徳が90年代に彼らのヒット曲“Clouds Across The Moon”(全英6位)をカヴァーし、クラブ方面で大きく再評価が進んだ。最近も星野みちるがこの曲をネタ化しており、時代の巡り合わせの妙を感じてしまう。
聞くところによれば、ポリキャットのメンバーは他に、Suchmosやnever young beachなど同時代的に活躍している日本のグループにも興味を持ち、自分たちの音楽性にも反映させているとか。また日本以外の洋楽アーティストで影響を受けたのは、ナがマイケル・ジャクソン、プリンス、スティーヴィー・ワンダー。ピュア・ワタナベ(Pure Watanabe)は、ビートルズ、ボブ・マーリー、オーストラリアのテーム・インパラ。そしてトング(Tong、Palagorn Gunjina)は、ジャスティスやアンダーソン・パーク、フランスのオンラーを挙げてくれた。世代的にマイケルやプリンスは当然だろうが、ビートルズからアンダーソン・パークまで、その嗜好性の幅広さには驚かされる。それぞれが活躍する時代には40年、50年の開きがあろうとも、彼らのようなジェネレーションには、すべてが同時代の聴いた音楽として耳に入るワケだから、何処かで一本の線に繋がっているのは間違いない。
さて、日本デビュー盤となる『土曜日のテレビ』。アルバム・タイトルが謎だが、それはタイでは日本のアニメを毎週土曜日の朝に放送しているからとか。そして収録曲7曲中4曲が日本語で歌われるナンバー。残り3曲が、アルバム『80 Kisses』には入っていたタイ語詞の楽曲をチョイスし、エクステンデッド・ヴァージョンで収めている。この新曲群と『80 Kisses』からのピックアップの違いは?
「やっぱり日本語で歌っている、ということに尽きるかな! あとはムードを出すために使ったサックスやトランペット、トロンボーンの音。フュージョンやファンク、ジャズの要素も採り入れてみたかったからね。ピュア・ワタナベの好きなバンドがカシオペアだから、その影響もあって、このアルバムの楽曲のハーモニーはすごく良くなったと思う。正確に言うと、彼はカシオペアの真似をした演奏をしているよ」。
日本のシティー・ポップ系アーティストでカシペオアの影響を口にする人はほぼ皆無だと思うが、実はヨーロッパの若いAOR系アーティストたちの間では、彼らは意外なほど根強い人気がある。80年代中盤のカシオペアは、ちょうど海外進出に熱が入っていた時期で、アルバムのリリースのみならず、毎年のようにヨーロッパ・ツアーに出て、レヴェル42やシャカタク、アイスランドのメゾフォルテといった欧州勢のジャズ・ファンク・グループと肩を並べるほど結構な支持を得ていた。その頃ライヴに足を運んだり、レコードを買ったりしていたファンの息子・娘たち世代が、家にあったレコードを聴いてカシオペアのファンになったりしているらしい。おそらく同じ現象が、東南アジア主要エリアでも発生しているのだろう。ところが本国日本では、フュージョン・バンドというレッテルが邪魔をし、熱狂的ファン層を獲得している一方で、その支持の裾野は一向に広がらないジレンマを抱える。ポリキャットのメンバーのように、カテゴリーやイメージの固定概念を持たずにいることは、彼らの音楽的ルーツを探る意味で案外重要なコトかもしれない。
何より日本の若いシティー・ポップ・ファンは、親の影響で子供の頃からユーミンやら大滝詠一らの都会派ポップスを刷り込まれ、洋楽にも自然に慣れ親しんできた。学校ではアイドル全盛だったのに、少数派や孤立しがちな彼らはそれを横目で見ながら、数少ない同朋たちでヒソヒソと音楽を語り合ってきている。でもそれだけ耳が肥えているから、サウンドへのコダワリが強く、音楽愛も深い。そして近隣国からやってきたポリキャットやイックバルにも、そうしたコミュニティーに支持される要素が自然に備わっている。
「今回の来日には、最高に興奮しているんだ。日本の音楽文化には、日本人の誠実さが顕著に出ていると思う。日本では違法ダウンロードが少ないし、みんなちゃんとチケットを買ってライヴへ行くでしょ。タイでは残念ながら、日本とは真逆だから。だから、日本という国に来ることがとても楽しみだったし、日本にいる間に精一杯のことをやるつもりだ。ライヴではドラムとギターがサポートで付いてくれてるよ。僕らのライヴでは、いつもそうしているんだ」。
J−Popの新しい潮流の一角を、アジアの同胞国からやってきた若手グループが担う。そんな傾向が生まれてきた昨今。最近はアイドルの影の仕掛け人が本格派のサウンド・クリエイターだったり、脱アイドル組がシティー・ポップをめざしたりすることも珍しくない。真の音楽ファンが望んでいるのは、使い捨てのコマではなく、より音楽的なアーティストがシッカリした活動を継続して展開していけること。ポリキャットはそうした海外参入組の、これから先頭を歩む好グループなのである。

LIVE INFORMATION
POLYCAT JAPAN TOUR 2017
earth garden “秋” 2017
第13回代々木クラフトフェア
2017年10月28日(土)東京 代々木公園
★詳細はこちら