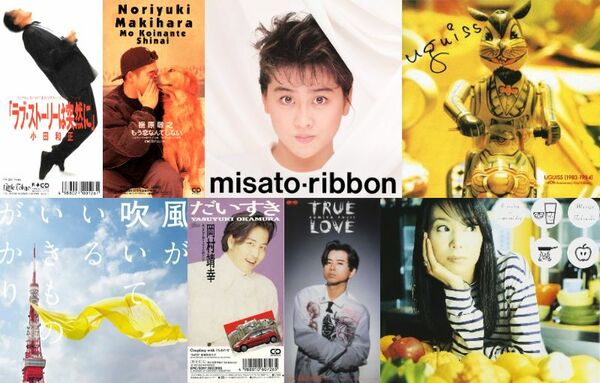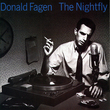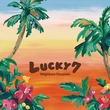Hey baby driver 僕を連れていけよ/ここじゃない どこか遠くへ
――新作『memori』の話に戻ると、今作を作っていくうえで、最初に作品全体の方向性を決めた曲などはありましたか?
「このアルバムに入っている曲は、一番古い曲で2004年に作った曲なんです。それこそ“悲しみのかけら”も、十数年前にゴメスで演奏したことがある曲だし、最後の“ブックエンドのテーマ”は、ライブ活動を再開する前にできた曲で。
『ripple』を作ったあとに、まさかここまで長く休むことになるとは思っていなかったので、『ripple』の次のアルバムに向けて書いていたけど、宙に浮いてしまっていた曲たちもたくさんあったんですよね。自分でソロを10年やってきた中でも、〈この曲はゴメスの曲だからな〉と思って取り上げなかった〈古い新曲〉がたくさんあって。そこに決着をつけたいという気持ちがあったので、本当に、時間を凝縮したアルバムになっていると思うんです」
――〈古い新曲〉というのはまさにな表現だと思うんですけど、“悲しみのかけら”も“ブックエンドのテーマ”も、2019年のゴメスが出す新曲として、ものすごくしっくりきますよね。表現としての年輪は感じるけど、音楽としての古さは感じないというか。僕はてっきり、全曲、近年作られた新曲なんだと思っていました。
「僕も、ここに収められた曲に自分の中で古さを全然感じないので、客観的にそう言っていただけるのは嬉しいです。
そういう曲たちの中で、〈このアルバムは上手くいくぞ〉と思ったのは、“baby driver”ができたときでした。今回は『ripple』の続きのつもりで作ってきた曲も多いので、書きこみの多い、命を削って書いたような歌詞の曲が多く入っているなと思うんですけど、“baby driver”は〈なにも言わない〉ことをテーマにして作った曲で。本当に、どうでもいい曲というか(笑)。〈ウェ~イ!〉みたいな(笑)」
――ははは(笑)。
「ただ演奏して楽しい、自分にも問いかけない、単純にその状況を歌っているだけ。そういう意味では、新機軸の曲なんですよね。ただ〈海に行こうぜ〉と言っているだけなんだけど、そういう曲を作れたことが自分にとってはすごく楽しいことで。〈GOMES THE HITMANの新曲です!〉と言って出してきたと思ったら、なにも言ってない。〈いいこと言うと思っているでしょ? でも、なにも言っていないですよ〉っていう(笑)。
この曲は2年前にできたんですけど、できたときに、〈あぁ、これはアルバムの核になるな〉と思いました。それこそ、20年前に出した『weekend』(99年)の頃に通じるテンポ感の曲だし。ゴメスの新曲として最初に聴いてもらうなら“baby driver”が一番だし、〈この曲があれば、アルバムは大丈夫だ〉と思いましたね」
――確かに、“baby driver”はいい意味での軽薄さがある曲だと思うんですけど、冒頭の歌詞にある〈Hey baby driver 僕を連れていけよ/ここじゃない どこか遠くへ〉というようなエスケーピズムは、もしかしたら90年から、山田さんの音楽の中に根深くあり続けたものなのかもなと思ったんです。
「そうかもしれないです。でも、それこそ20年前は車も持っていなくて、当時は池袋界隈で過ごしていたんですけど、渋谷すら遠くて。生活していくのに精一杯で、海に行くことすら、憧れや想像でしかなかったんですよね。その頃、『weekend』に収録された曲なんかは、本当に妄想のなかから作りだしたもので、理想像なんです。
でも、あれから20年経ち、自分も普通に車に乗っているし、〈海に行きたいな〉と思ったら、仕事をサボって海に行けるような状況にある。そういう中で、すごく地に足の着いた逃避行の歌を書けるようになったなって思うんです。それこそ、“baby driver”は、インドネシアのバリで作ったんですよ」
――そうなんですね。
「めちゃくちゃ仕事が忙しくて疲れ切ってしまったときに、無理やり休みをとってバリに行ったんです。そこで、非日常を何日間か過ごしているときにできたのが“baby driver”で。現地のドライバーさんに、英語が通じないから身振り手振りで行きたい場所を伝えるんだけど、〈ちゃんと連れていってもらえるかな?〉っていう不安を抱えながら後部座席に座っている……そういうシチュエーションの曲なんです、実は(笑)。
昔はただの想像だったし、行った先の場所がどんなものかわからなかったけど、今はどれだけ忙しくても、〈これが終われば解放される〉みたいな感じで、行きついた先の場所が把握できるようになっている。行こうと思えば本当に行ける、というか。
昔はがむしゃらに空想や妄想に手を伸ばすようなエスケーピズムだったものが、時間が経ち、歳をとったことで、今は〈本当にそこにある〉というリアリティーを持って、エスケーピズムを描けるようになった。それが昔と今の説得力の違いかなと思います。昔の曲はキラキラしているけど、今はもっと現実的で、日常と接着していると思う」
――それは、聴いていてまさに感じました。僕は今30代なんですけど、10代や20代の頃ほど無邪気に現実逃避を追い求めてはいないし、もう、そう簡単に現実から目を背けることはできない。かと言って、現実や社会ばかりを直視することも疲れてしまうし……自分の中にある欲望や夢想も、大切にしたくなる。そういう感覚に、このアルバムはすごくフィットするなって思うんです。
「〈このアルバムが日常にあったら、相当いいんじゃない?〉と思えるものになったと思うんです。僕は最近、車に乗っているときも、電車に乗っているときも、このアルバムばかり聴いているんですけど、生活のサウンドトラックとして、すごくいい作品だなと思うんですよね。いろんな景色を見ながらこのアルバムを聴くと、すごく腑に落ちるんですよ。〈この言葉の選択は間違っていなかったな〉と自分で思える。
今年の年末から、このアルバムがみんなのもとに届きますけど、ふっと暮らしが変わるなにかしらの魔法は、このアルバムにはあるような気がします。そういうものが作れたのは本当に嬉しいんですよね」