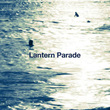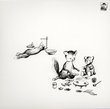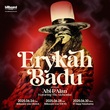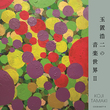要素と構造の組み合わせが過去にない音楽を生む
――アルバムでは、キーボード2人体制、パーカッションありという編成ですよね。
「管楽器を入れるとか、そういう考えはなかったですね。キーボードのほうがいいなと」
――確かに、以前のインタビューでも〈ホーンとかは入れずに、キーボード2台でとかで、僕もエレキに持ち替えて〉という発言があります。
「おおかた作りたい感じに出来ました。最初はもっと思い切って現代的な音質にしようと思ってたんですが、成り行きでちょっと昔っぽい音になってしまいましたね」
――現代的というのは、低音もすごく効いている、みたいな?
「そうです。クリアですごく解像度が高い音質で。でも、やっていくうちに結局もっと優しい感じの音がいいなとなりました」
――何が〈やっぱり違う〉というところだったんでしょう?
「疲れる音はイヤだな、ってことですね。みんな今はどぎついじゃないですか。それはそれで良さなんですけど、聴いてて疲れない音のほうが自分はいいかな。だからキックの音もそんなにゴツくしていないし」
――こないだリリースされたシルク・ソニックのアルバム(『An Evening With Silk Sonic』)も、そういう音質でしたよね。70年代オマージュなテイスト。
「そうですね。でも、1月30日のライブからベースを弾いてくれるCoffくんともこないだ話したんですけど、結局シルク・ソニックってあまりに昔のソウルの焼き直しっぽいんです。自分はそうではないものにしたいので。実はこういう色味の曲は過去にはないな、というものにしたい」
――そこを違えていくものって何なんでしょう?
「それは、要素と構造ですね。たとえば新譜の6曲目“水月 うきよ”だったら、シック(Chic)からエレガントさが消えてもっと荒々しくなって、そこに(70年代エレクトリック期の)マイルス・デイヴィスが弾いてるようなオルガンが乗る、とかそういうイメージ。〈そんな音はないな〉というところを目指していく作り方です。
それが、要素と構造の組み合わせなんです。その組み合わせの妙味で独特なものにする。でも音楽って結局そうやって変わってきたと思うんです。マイルスがジャズとかモードを編み出したわけじゃなく、彼がすでにあるものを合わせて独特なものにした。それが創造性じゃないかという考えです」
――〈ありそうでないもの〉は〈ないもの〉を新しく産むのではなく、〈あるものの組み合わせでないものを作り出す〉ことでもあるという考え方。
「そういうものにしたい。そんなにすごく新しい音楽という印象は、僕の新譜にもないと思うんですよ」
――なじみのある音楽だなと思って聴いていると、どんどんズレてゆく、ようなところを目指している?
「そうですね。結局、今ある音楽を見ていったとき、すごい低音でも、変拍子でも、目まぐるしく変わるコード進行でも、その要素はすでにあるものなんです。それよりは、インパクトがないけど独特なもの。そっちのほうがいいですね」
――こないだTVで近田春夫さんと小泉今日子さんの対談を見ていたら、近田さんがわりと近いことを言ってました。〈音楽の要素はすでに出尽くしている。だけど組み合わせは無限で、そこに可能性がある〉って。
「僕もまったくそう思います。何百年も世界中で無数の人たちが音楽をやってきたんだから、それはもうあらゆる要素は出尽くしてますよ。そういうのを踏まえたうえで僕はやりたい」