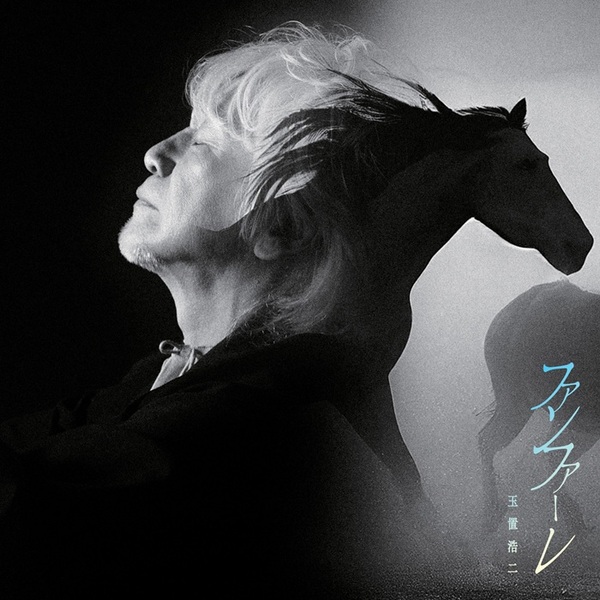上手くなりたいのなら、とにかく練習あるのみ
――改めて〈DMC〉の歴史について教えていただけますでしょうか?
「イギリスにトニー・プリンス(ラジオ・ルクセンブルクの元プロデューサー)という名物DJがいて、彼が〈Disco Mix Club〉というリミックス作品をメインとしたDJ専門レーベルを始めて、その略が〈DMC〉だったんですね。そこからトニーがDJの技を競う大会を〈DMC〉という名で開くようになって、そこから略が〈DJ Mixing Championship〉という意味に変わっていったみたいです。
最初の大会は1985年に行われて、初代はロジャー・ジョンソンというDJが優勝したんですけど、初めの頃はターンテーブルの上に乗っかってブレイクダンスみたいに回ったり、ビリヤードのキューでレコードをこすったりとパフォーマンス的な要素が強かったみたいです。日本大会が最初に開催されたのは1990年で、GM YOSHIさんが優勝しました」
――90年代に入ってからは世界的に〈DMC〉も認知されていきましたが、それ以降はどのように発展していったのでしょう?
「90年代に入ってからはDJキューバートやミックス・マスター・マイクなどが出てきて、ガシガシとスクラッチする、当時では斬新なテクニックを使って優勝していくような流れに変わっていきました。それとDJクレイズが出てきて3連覇(1998年、1999年、2000年)するんですけど、彼は本当に新しい、圧倒的なスキルと音楽性を見せつけてくれましたね。
そこから2000年代に入って僕なんかが登場して、いろいろ音楽性をアピールしていくスタイルが出てきて、アメリカ、カナダ、ドイツ、フランスなどのDJが優勝していくんです。2010年代になると2012年にDJ IZOHが日本人で10年ぶりに世界大会で優勝して、日本は強豪国だという認知が世界でも広まりました。2019年にはCreepy NutsのDJ松永がバトル部門で世界チャンピオンになりました」
――日本のバトルDJの評価は世界的にも高い印象がありますが、他の国のDJたちと比べてどんな部分が優れていると思いますか?
「一言で言うとスキルですかね。スクラッチにしても、ビートジャグリングにしても、手の動きとかスピード感とか、圧倒的なスキルを持ったDJたちが多いと思います。アイデアも豊富だし、日本人はやっぱり勤勉なんですかね。僕はいつも〈上手くなりたいのなら、とにかく練習あるのみ〉と言っているんですが、ターンテーブルにどれだけの時間を費やしたかが上手くなるポイントでしかないんです。その後にバトルDJを辞めて、現場のDJになったときにも生かされますしね。自分も少しサボっただけで手捌きが鈍くなりますから(笑)」
――DJたちのスキルは使用機材の進化とともにレベルアップしてきたと思いますが、そのあたりはいかがですか?
「2010年ぐらいからレコードではなくデジタルに変わって、機材もかなり進化したので、それに伴ったパフォーマンスになっていますね。レコードからセラート※に変わりましたし、その頃からスタイルは一変したと思います。ミキサーにボタンがいっぱい付いていて、ボタンひとつで好きなポイントに音が飛ばせるとか、アナログにはなかったプレイをよく目にするようになりました」