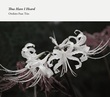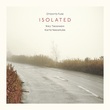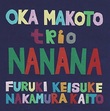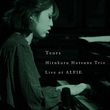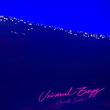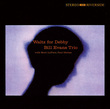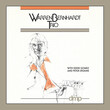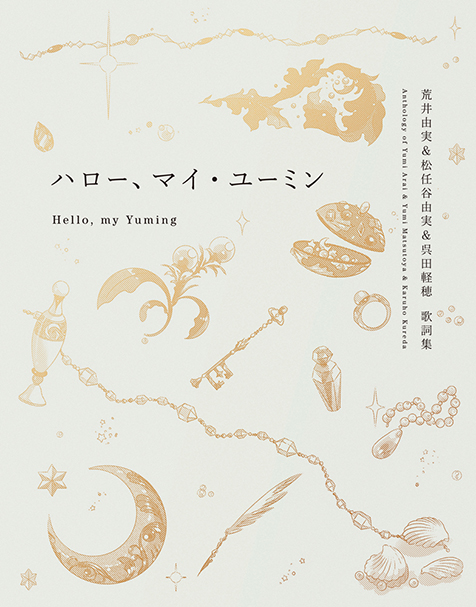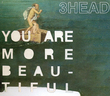2024年3月にリリースされた『Isolated』から1年7か月。ここに布施音人トリオのセカンドアルバム『Thus Have I Heard』が登場した。メンバーは布施音人(ピアノ)、高橋陸(ベース)、中村海斗(ドラムス)という、2020年以来不動の顔ぶれ。前作同様、アナログテープによるレコーディングを行ない、全曲を布施のオリジナルで構成。アルバムタイトルの『Thus Have I Heard』は、漢訳仏教経典の冒頭に置かれるフレーズ〈如是我聞〉の英訳で、〈私はこのように聞きました〉という意味を持つ。ジャケットはデジパックになっており、20ページのブックレットには布施が撮影した風景写真の数々が、自らのライナーノーツ(エッセイ)と共に収められている。
この、実に興味深い作品を送り出した布施音人とはいったいどんなミュージシャンなのか。どんな音楽観の持ち主なのか。Mikiki初登場となるこの鬼才に、バイオグラフィ的なことも含めて話を聞いた。

数学を志したピアニスト
――最初に、幼い頃の音楽環境について教えていただけますか。
「父は作編曲の仕事をしていて、母はクラシックピアノの演奏家で国立音楽大学の教授でした。その関係で家にグランドピアノがあって、小さい頃から遊びで弾いていたと思います。将来、音楽をやりたいなとは小さい頃から思っていて、小学校の七夕の短冊にも〈ピアニストになりたい〉〈指揮者になりたい〉などと書いたのを覚えています。中高の間は吹奏楽部に所属しましたし、クラシックピアノのレッスンも4歳頃から高校生くらいまで通っていました。
他方、中学に上がる頃に数学への興味も増し、数学の研究者になりたいとも思っていました。なので、大学では数学科に行ったのですが、それと並行してジャズ研に入ったところ、また演奏が楽しくなってきたんです。大学3年生の頃にセッションホストの仕事を始めて、いろいろ演奏の仕事をもらうようになりました」
――セッションホストということは、ジャムセッションの進行役も兼ねていたのですね。ところで、最初に聴いたジャズのレコードは何ですか?
「ビル・エヴァンス・トリオの『Waltz For Debby』です。高1の頃、亡くなった祖母の住んでいた部屋で父がこのアルバムをかけていて、それが聞こえてきて気になったので貸してもらいました。その後で父に他のおすすめのピアニストを尋ねたところ、ウォーレン・バーンハートの『Trio ’83』を薦められました」
――そこでウォーレン・バーンハートが出てくるという、研ぎ澄まされたセンスに鳥肌が立ちます。なんと幸せな音楽との出会いでしょう。
「父がステップス・アヘッドを好きだったみたいです。(そのメンバーの)マイク・マイニエリやウォーレン・バーンハートは作曲も素晴らしいでしょう。それに、バーンハートはビル・エヴァンスをとても尊敬していますからね。
『Trio ’83』は(ステップス・アヘッドに在籍経験のある)エディ・ゴメスとピーター・アースキンとのトリオですが、私はまだジャズを何も知らないに近い状態でこの作品を聴いて、中でも後半の3曲、“New Samba”と“Four Part Improvisation”と“My Bells”がとても気に入って、高校の通学のときに毎朝聴いていました。こんなふうに自分も弾きたいと心から思いましたね。“Four Part Improvisation”のお互いに新しいことを出し合って作っていく感じなどは、クラシックを聴いていたときにはなかった音楽体験でした」
――YouTubeにフルート演奏の動画もアップしていますが、フルートを吹くようになったのはいつ頃からですか?
「中学高校と、吹奏楽でフルートを吹いていました。そこでもフュージョンやジャズの曲に触れたんです。ジャズのフルートを聴きたいなと思ったときに、父親がビル・エヴァンス・ウィズ・ジェレミー・スタイグの『What’s New』を貸してくれたので、それを何度も聴きました。チャーリー・パーカーもジョン・コルトレーンもまったく知らない状態で、ジェレミー・スタイグばかり聴いていました」