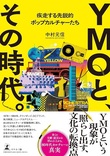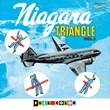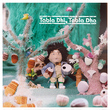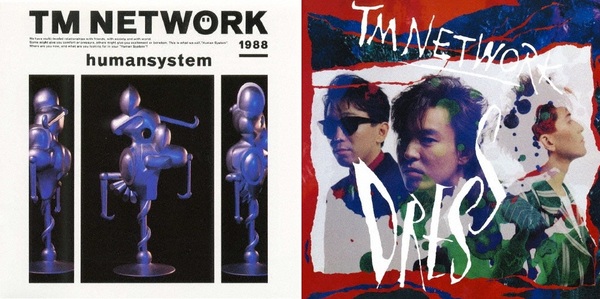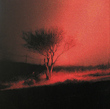音楽は(芸術は)はたして残るものなのだろうか。
「残さない音楽」、2022年12月29日の日記に、坂本龍一はそう記した。そこには、「音楽を残すこと」について、音楽が「残す音楽」と「残さない音楽」のふたつがあること、そのもうひとつのアイデアとして「霧散する音楽」ということが記されている。エリック・ドルフィが言ったように、音楽は終わってしまえば空中に消え去ってしまい、二度と捕まえることはできないものであり、そもそも演奏されるそばから霧散してしまうものだ、とも言えるだろう。だからこそ、いかに残すかが考えられてきたのだし、その一方で、残されなかった、あるいは積極的に残さない音楽というものがありうるだろう。
しかし、この映画は、結果として坂本龍一というひとりの音楽家が、その生命の潰える直前まで音楽家として創造的に生きようとし、そのことをもって積極的にあらゆる記録に残ろう/残そうとしていたことを記録することになった。それを思う時、坂本の言う「残さない音楽」とはいったい何なのかを考えないわけにはいかない。ヒポクラテスの言葉である「芸術は長く、人生は短し」を、最期に残した坂本は、自身の人生の限りあることにたいして、その音楽は後世まで残ることにむしろ希望を持っていたのではなかったか。いや、それだけではない。坂本は、すぐれた芸術を達成することにたいして、人生はあまりにも短すぎる、という無情な運命にたいして、まだまだ自身には成すべきことがあると考えていたことだろう。そこでは、残すべき音楽、残るべき音楽とは何か、という大きな問いが立ちはだかることになる。音楽は(芸術は)はたして残るものなのだろうか。
「人は自分の死を予知できず 人生を尽きぬ泉だと思う」とはじまる、ベルナルド・ベルトルッチ監督の映画『シェルタリング・スカイ』のラストシーンに登場する原作者ポール・ボウルズ自身による朗読は、坂本の著書である『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』や、楽曲《fullmoon》のモチーフともなった。私たちが自らの死期を知り得ないこと、それは誰でもが等しく受け入れなければならない運命である。しかし、それがいつかなのかは知り得ないにしても、遠くない間近に控えていることを意識せざるを得なくなってしまった坂本にとって、それならば、とジャン=リュック・ゴダールが自ら選択した死へのシンパシーをあらわにすることも無理からぬことであるだろう。だからこそ、坂本は「人類の破滅と自己の死を見据えて曲を書く」(2021年10月28日の日記)ことを想起したのだろうし、そのために「心にグサっと刺さるような」、「何か強烈なものを」、「見たい、読みたい」と思った。それはまた、自身もそうした音楽を書きたい、書かねばならない、という意思の現れにちがいない。