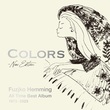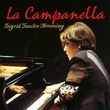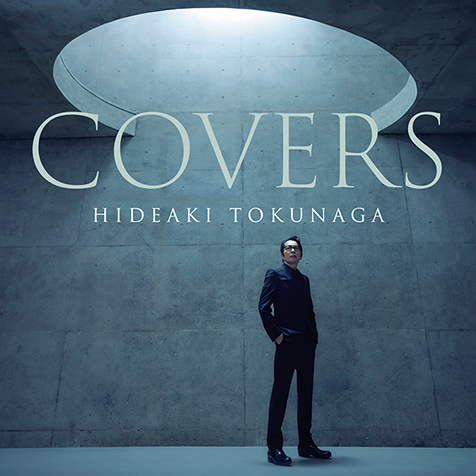フジコ・ヘミングの音楽はまさにブルースだと思う。
苦くせつなく、それでも愛に満ちたブルース。
音楽記者になりたての20代の頃、フジコ・ヘミングの演奏を聴いた。
彼女は70代だったはずだ。すでに〈魂のピアニスト〉として揺るぎなく、ステージに現れたときのオーラには目を瞠ったが、演奏はいささか不安定に思えた。同年代の先輩が「一度聴けばいいかな」と呟いたのを、今も覚えている。東京では日々、目が回るほど多くのクラシックコンサートが開かれ、国内外の精鋭たちの演奏を追わねばならなかった。必死に喰らいつこうとしていた私はその言葉を妄信し、〈経験済〉というフォルダに乱雑にフジコを投げ入れた。
若いというのは、なんと無知で、愚かなのだろう。劇中のフジコの言葉をなぞりながら、今、涙を止められずにいる。あの頃、私が知っていたフジコの人生なんて、わかりやすく切り取られたドキュメンタリーとドラマくらいのものだった。〈無国籍や聴力喪失の苦難を乗り越え、60代でようやく認められる人生〉に感銘は受けたけれど、綺麗にパッケージされたシントラ―のベートーヴェン伝と同じで、そこに人間らしい体温はなかった。そして後年、彼女の演奏を聴きに行くこともついになかった。
2024年4月21日、フジコ・ヘミングは92歳で旅立った。彼女の〈音〉を聴くことは、もうかなわない。

映画「フジコ・ヘミング 永遠の音色」は、ロングランヒットを記録した「フジコ・ヘミングの時間」(2018)で知られる小松莊一良監督が手がけた、フジコ・ヘミング最後のドキュメンタリー映画である。初公開のインタヴュー映像と、フジコが生涯描き続けた絵日記、家族の証言、そして全編にたえまなく流れる音楽。これらが、私たちをフジコの人生の旅へと誘う。説明的なナレーションを排し、よく知られた〈苦難〉への言及も最低限に留めた、親密で、愛に満ちた巡礼のような作品だった。
巡礼の出発点は横浜である。バウハウスで学び、天才と呼ばれたスウェーデン人の父が遺したポスターと再会するフジコ。幼少期に別れた父への衒いのない憧れの言葉に、これまでとは違う、という肌触りを感じる。日本に残された母子は苦境に立たされ、無国籍のハンデもあって、苦労したのではなかったか――おなじみのモチーフが、まるで変奏曲のように違って聞こえてくるような気がした。その〈音〉はさらりと明るい。当時を回想するフジコの言葉や、菅野美穂が朗読する絵日記のせいかもしれなかった。言葉から、明るく自己肯定感に満ちた少女が浮かび上がり、悲劇性よりも、強さが印象づけられるのだ。

その強さはそのまま、20代から40代にかけてのヨーロッパ生活でも発揮される。ベルリンからウィーン、そして父の故郷ストックホルムへ。何度もつまずきながら、強い衝動に駆られて流転していく彼女の青春の旅には、放浪という言葉がふさわしい。1960~70年代のモードを纏い、こちらに強い視線を送るモノクロ写真のフジコはたまらなくクールで、激情家だったという父の魂が宿っているようだ。
当時の恋愛についての独白は、12年間追い続けた小松監督だからこそ迫れた本音だろう。「騙されてきたから、人を騙すことだけはしたくない」という言葉に、ヒリヒリするような〈人間フジコ〉を感じ、息が止まった。ああ、だからあの音楽は生まれたのだ、と思った。
貧しい留学生活で辛酸をなめ、「ピアノはお金持ちじゃないと続けられない」と繰り返しても、恋をして裏切られ「日本に帰りたい」と弱音を吐いても、彼女は異国にとどまりつづけた。そこまで彼女を駆り立てたものは何だったのだろう。
その答えはたぶん、信念にある。「自分はピアノを弾くために生まれてきた」という信念を、彼女はおそらく一度も捨てたことがなかった。そしてその信念は、幸福だった(はずの)子ども時代に結びついている。