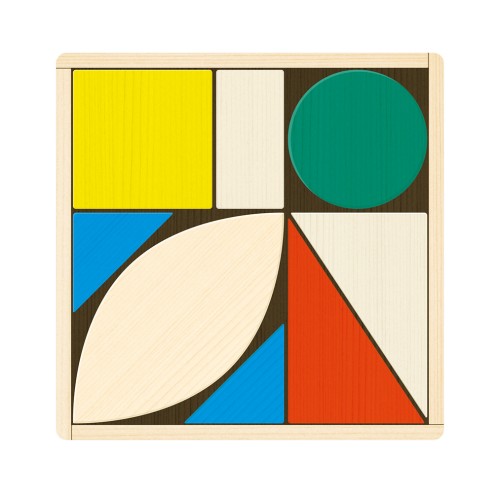2014年に東京で結成された4人組バンド、CHIIO。パワフルなドラムが力強いグルーヴを生み出すなか、ツイン・ギターやコーラスが色彩豊かにサウンドを彩っていく。ロックンロールのダイナミズムを失わずミニマルに構成された音作りは、サウンドをデザインするような独自のポップ・センスが光っているが、すべての曲の作詞作曲を手掛けているのはバンドの中心人物、中村太勇(Tao Nakamura:ヴォーカル、ギター)。デス・キャブ・フォー・キューティを聴いて音楽に目覚めた彼は、USオルタナやエレクトロ・ポップなどさまざまなバンドから影響を受けてCHIIOの音を生み出した。9月27日(水)にリリースされる彼らのファースト・アルバム『toc toc』にはバンドの多様な表情が見て取れる。アルバムについて、中村に話を訊いた。
曲の温度は低いけどノれるバンド
――まず、バンド名について伺いたいのですが、これはなんて発音するんですか?
「〈チーオ〉です。これは造語みたいなもので。バンド名を決める時にモチーフがあったほうがわかりやすいのかなと思って、僕は寒い国の人たちが作る音楽が結構好きなので、ペンギンをモチーフにしようと思ったんですよ。それでベース(吉田涼乃)の提案もあってペンギンをいろんな国の言語に変換してみたんですけど、中国語だと〈チーオ〉に近い発音をするらしいことがわかって。それで〈チーオ〉をアルファベットに直してみたら、文字の見た目も図形っぽい感じでいいな、と思ったんです」
――〈寒い国の人たちが作る音楽が好き〉っていうのは中村さんの嗜好ですか。それともメンバー全員?
「僕です。CHIIOは僕が〈バンドを組もう〉と思ってメンバーを集めたんですけど、その時にどんな音楽が好きな人がいいか、とかは考えてなかったんです。タイミングよく周りにいた人たちに声をかけたんですよね。例えばドラム(フクタハヤト)は僕と同い年で、一緒にライヴをしたことがあって。ギター(北山裕人)は昔からネットを通じて知り合いだった。で、ベースは僕がライヴハウスで働いている時、そこで彼女がライヴをしていて。それを観て〈演奏だけじゃなくて立ち姿もいいな〉と思って、知り合いじゃなかったんですけど後日誘いました。そんな感じで始まったので、僕以外の人たちはお互い〈初めまして〉なんですよね。だから最初の頃は、音を合わせようと思ってもなかなかうまくいかなくて試行錯誤していました」
――それまでにバンドはやっていたんですか?
「昔、高校の友達とバンドをやってて、でも全然(音楽性が)合わなくて辞めちゃったんです。その後もサポートでいろんなバンドに入ったりしたんですけど、活動休止したりして、不完全燃焼的なところがあって。このままじゃちょっと寂しいな……というのがあり、それで〈自分でバンドをやろう!〉と思ったんです」
――〈こんなバンドにしよう〉とか、具体的なイメージはありました?
「昔からコーラスが好きだったので、コーラスは入れたいと思っていました。僕は今メイン・ヴォーカルですけど、結成した頃はコーラス兼ヴォーカル兼ギターみたいな感じで、メイン・ヴォーカルはいなかったんですよ。それでみんなで歌う曲を軸にしてやってたんですけど、ある時から自分がメインで歌うのがバンドとしてまとまりそうだなと思ったのと、単純に歌いたくなって。やってみたらいい感じだったので、今のスタイルになりました」
――コーラスが好きなんですね。
「学校で合唱コンクールってあるじゃないですか。それが好きだったんです。あとは、TVのCMで流れている曲に、自分で勝手にコーラスを入れるような遊びを10歳ぐらいからしていて(笑)。バンドを始めてパッと周りを見渡した時、コーラスを主体にやっているバンドはあまりいないとも思ったんですよね」
――確かにそうかもしれないですね。ギターを2本入れたいというのは、最初から考えていたのでしょうか。
「そうですね。ギターは好きなので2本欲しいと思ってました。それとメンバー構成も最初から頭にあって。女性が一人いて、女性の声が入っているバンドをやってみたかったんです」
――ギターを始めたのはいつ頃?
「ちゃんと始めたのは中学3年生の受験シーズンぐらいですね。最初はスピッツを弾いてました。高校時代は自分もそうですし周りにも音楽に詳しい人がいなかったので、J-Pop中心であまり広がらなかったです。それが変わったのが高校を卒業してから。2012年の〈サマソニ〉でデス・キャブ・フォー・キューティを観て驚いたんです。それまで彼らのことはあまり知らなくて。〈デス〉が入っているのでメタル・バンドかと思ってたんですよ(笑)。それで聴いてみたら〈こんなに優しいのか!〉と驚いて。〈曲の温度は低いけどノれるバンド〉っていうのを初めて知って。それが今の自分の軸になっています」
できるだけ最小限度の要素で構成する
――デス・キャブから広がっていったんですね。では、『toc toc』について伺いたいのですが、レコーディングはどんなふうに進められたのでしょうか。
「今回はドラムだけ天井が高いスタジオで録りたかったんです。それぞれのパートはアンプとかが密閉された空間にある状態で録って、後で重ねて録って行きました」
――どの曲も太いドラムの音が屋台骨になってますね。アルバムをレコーディングする前から、ドラムの音は具体的なイメージがあった?
「例えば“march”はスネアの余韻がないほうがいいとか、そういう音のイメージはあったので、まずドラムテックの人に音作りをしてもらって〈これでいきましょう〉と録りましたね」

――各パートの演奏については、メンバーにイメージを伝えてそれを再現してもらうやり方ですか。それとも、自由に弾いてもらう?
「ドラムは〈こういうノリ〉というヴィジョンだけ伝えてとりあえず叩いてもらって、そこから削ったり足したりという感じです。ギターに関してはほぼ完全に任せていて、〈こうしたほうが良さそう〉っていうのだけ言ってます」
――アルバムの全体像については、何かイメージしていたことはありましたか。
「自分の音楽性の幅を広げたいというのもあって、いろいろなタイプの曲を入れたいと思いました。例えば“chapter 2”はアコースティック主体で鉄琴の音とかも入ってて。“pupils”は1曲通して変な音をずっと後ろで鳴らしているんですよ。“PLANET”はシンセサイザーを入れたり。でも、〈絶対ギター主体で〉っていうのだけは決めてました」
――なるほど。 CHIIOの曲はサウンドが構造的というか、きっちり整理されていますよね。まずビートがあって、そこに音のパーツがカッチリと組み立てられていく。
「一番こだわってるところが曲の構成なんです。できるだけ最小限度の要素で作るというのを心がけていて。聴いてて〈長いなあ〉って感じるところは一切なくしたいと思ってます」
――ミニマルな構造ですが、ダイナミックな奥行きがあるので淡白な感じはしないですね。
「そうですね。ギターの音にもかなりこだわってます。“who”はエレキ・ギターの後ろに薄くアコギを入れていて。今回、ギターは何回か録り直したんですけど、この曲が一番時間がかかりましたね。エレキ・ギターとアコギのバランスが難しくて」
――“who”はハーモニーが印象的な曲でもありますね。
「サビ的なところで四重コーラスを入れているんですけど、最初そこに歌を入れる予定だったんです。でも〈なんか歌が邪魔だな〉という感じがあって。歌が邪魔だと感じた時は、コーラスを使うことが多いです」
――音の作り方がエレクトロニカとかダンス・ミュージックに通じるところもあるように感じたのですが、そういう音楽も聴いていますか。
「最近、聴くようになりました。モール・ミュージックっていうドイツのレーベルの、ラリ・プナとギューターが好きで。無機質なんだけどポップな感じが良いなと。“march”のサビとかはギューターの"You"に影響を受けてますね」
――ドイツといえば、反復ビートを軸にした“pupils”はクラウト・ロックのような雰囲気がありますね。
「この曲はアルバムのなかで一番異様な感じにしたくて。デモでバシッと曲を作り上げることって少ないんですけど、これは完全に作りこみました。ドラムはフレーズがずっと一緒なんですよ。この曲に関して言うと、4ADにLNZNDRFっていうバンドがいるんですけど……」
――ナショナルのデヴェンドーフ兄弟のバンドですね。
「そうです。彼らのアルバム『LNZNDRF』を聴いて、すごくカッコ良いなと思って。この曲を作ってる最中にそのアルバムをよく聴いてたんです。反復するビートが前に出てギターとかシンセで曲に展開をつける、で、曲が長い――みたいなところは影響受けてますね。実は長い曲を作るのが得意じゃないんですけど、一度作ってみたかったんです(笑)」
――CHIIOの曲は、実験的なアプローチをとっている曲でもポップな親しみやすさがありますね。メロディーも良い意味であっさりしているからこそ、曲の構造がくっきりと浮かび上がる。
「3分間くらいの長さで、抑揚があって聴きやすい曲が好きなんです。ラリ・プナとかもそうなんですけど、メロディーが平熱で声を張らなくても歌えるような曲を意識して作っています」