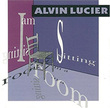アルヴィン・ルシエの音楽
音の振る舞い、音の出来事に立ち会う
アルヴィン・ルシエの最後の来日公演、というふれこみのコンサートが京都の京都大学西部講堂と東京のスーパー・デラックスで3日間にわたり開催された。「最後の来日公演」とはいかにもという感じではあるが、たしかに1931年生まれのルシエは御歳86歳(公演当時)。今後海外での自身による公演は行なわれないということで、特に日本への長時間にわたる旅程は体力的にもむずかしいということなのだろう。とはいえ、前回の来日(ICCでの展覧会「サウンディング・スペース」のために来日)が2003年のことだから、15年も待たされたと言うべきか、むしろ若い観客にとっては初めて接するルシエであり、またそれが最後の来日でもあるという貴重な機会となった。来日公演は、ルシエの楽曲を専門に演奏するアンサンブル、エヴァー・プレゼント・オーケストラとともに行なわれ、ソロ奏者として、同アンサンブルのメンバーでもある、オーレン・アンバーチ、トレヴァー・セイントがフィーチャーされたものだった。
ルシエはかつてより、「音楽によって詩的な感情を喚起させることには関心がない」と言っている。彼にとって音楽とは、作曲家の内面的なもの、なんらかの感情を表現する手段としてあるのではない。それは、彼の作品を特徴づけるものであり、音を物質の振動から起こる波動として捉え、そうした物理現象としての音が空間に放たれることで、空間と音が関わりあいながら一つの作品を構成する。そこで起こる現象=出来事としての音、音の振る舞いを体験することがルシエの音楽なのである。たとえば、楽器から空間に放たれた音が、空間で電気的なサイン波と干渉しあい、演奏者の手を離れ、空間でその状態を変化させながら消えていくようすに聴き入る。音響現象としての音に着目し、空間における現象そのものを音楽として提示する、それらの革新的なルシエの音楽は、ジョン・ケージ以後(《4分33秒》以後)の音楽のあり方を指し示すものだと言っていいだろう。そして、その乗り越えとしての自身の実験音楽の確立、そこからサウンド・アート、サウンド・インスタレーションへの道を切り開くものでもあった。
ルシエは、「演奏者がいなくても一度作品を会場に設置しさえすれば、音楽が演奏され続ける」というアイデアに関心を持ち、多くのインスタレーション作品も制作している。オシレーターからの信号で振動しつづける、調律されたAの音を響かせる一本の長いワイヤーが、温度や湿度などの、ある空間の状態の変化によって、その振動を変化させるようすを聴く《ミュージック・オン・ア・ロング・シン・ワイヤー》(1977)は、その代表的な作品である。それは、空間にある期間展示されるものでありながら、タイトルに表されているように、一本の長いワイヤーが振動し続けることで延々と演奏され続ける一音のみからなる音楽、という見方もできるだろう。一方で、大きなうねりを伴いながら、空間の状態とともに振動としての音を変化させる、不確定な変動する要素を持った音楽でもあるように、それは持続と変化というふたつの要素を持った音楽でもあった。


日本初演となった、2本のエレクトリック・ギターのための作品《Criss Cross》(2013) でも、2人の演奏者がE-Bowを使用して持続音を演奏しているのを聴きながら、音程を変化させていく過程でおこる干渉現象を聴くことになる。それらのルシエの音楽は、詩的な感情を表現することを排除して作曲されているにもかかわらず、音どうしの響き合いの中から、より豊かなイマジネーションが私たちにもたらされる。両日のメインアクトとしてルシエ本人によって実演された《I am Sitting in a Room》(1969)や《Bird and Person Dyning》(1975)のような作品においても、現象が立ち現れる、音の出来事に立ち会う体験は、いまでも新鮮な驚きを与えてくれるものだった。
アルヴィン・ルシエ (Alvin Lucier)
1931年ニュー・ハンプシャー州生まれ。いわゆる演奏家、作曲家とは一線を画し、50年代初頭より「音楽」という枠を超えてさまざまな電気テクノロジーを用いた数々の作品を発表している。一方、「音」という振動現象に焦点をあてたインスタレーション作品を数多く制作。世界各地の展覧会/コンサートに招聘されている。