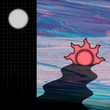ここ数年はインディー・ロックやギター・ポップが世界的に低調だった、という論調がある。しかし、果たしてこれは事実なのだろうか。台湾や中国、あるいは東南アジア諸国に目を向けると、近年、良質なギター・バンドが次々と登場している。ここ日本のインディー・アーティストとの交流も盛んになっており、国境を跨いだシーンが形成されてきた。今でこそ世界的パンデミックで停滞を余儀なくされているものの、アジアではインディー・ロック/ギター・ポップの新たな土壌が築かれている。
ここで紹介するI Saw You Yesterday(以下、ISYY)は、そんなアジア全域にファンベースを広げている東京のインディー・ロック・バンドだ。90年代オルタナティヴやシューゲイザーを音楽的ルーツとしつつ、キャプチャード・トラックスあたりの北米インディー勢とのシンクロニシティーも感じさせる彼らは、年明けから4つのシングルを連続でリリース。海外を視野に入れながら2021年も攻め続けている。今回はそんなISYYSから、ヴォーカリストでメイン・ソングライターのシモダヒデマサとギタリストのムラカミカイにインタビュー。バンドの成り立ちや、シングル4曲それぞれのアプローチについてなど、じっくりと訊いた。
暑苦しくない、サビを作らない
――SpotifyでのISYYのリスナー所在地を見たら、台北やシンガポールやバンコクでもたくさん再生されていて驚きました。東アジアでこれほど支持されている状況を、おふたりはどう受け止めていますか?
シモダヒデマサ(ヴォーカル/ギター)「すごく嬉しいです。日本の場合は日本語詞じゃないとリスナーに伝わりづらいところがあると思うんですけど、東アジアのリスナーは言語を問わず、サウンドで聴いてくれるので、そこには僕ら自身もすごく可能性を感じていて。今後も東アジアにはリーチしていきたいし、それこそコロナ禍が落ち着いたら、各国を回りたいですね」
ムラカミカイ(ギター)「やっぱりサブスクの影響は大きいですよね。自分たちがこうして海外のリスナーに発見してもらえたのも、ここ数年でサブスクが浸透して、どんな国の音楽も分け隔てなく聴かれるようになったおかげだと思う」
シモダ「きっと今の東アジアには、僕らと同じような音楽を聴きながら育ってきた同世代がたくさんいると思うんです。それこそ僕らや彼らはは中学の頃からYouTubeで音楽を聴いてきたような世代なので、住んでいる国によって音楽性が違うこともないですし、リスナー間の垣根もなくなってきているような気がしていて」
――実際におふたりがどんな音楽に触れてきたのか、教えていただけますか?
ムラカミ「僕は24歳までグランジ・バンドをやってました。シモダもそれとは別でオルタナ系のバンドを組んでて、僕らは対バンで出会った仲なんです」
――どちらもグランジ/オルタナを志向していたと。つまり、双方の音楽性には通じるものがあったということ?
シモダ「そうですね。お互いに同じライブハウスに出ていたんですけど、そこでグランジ/オルタナっぽいことをやっていたのはカイくんたちだけだったので、すごくシンパシーを感じてました」
ムラカミ「でも、当時はふたりとも壁にぶつかっていて。それこそ僕はちょっとヤケになってた時期だったんです。〈誰がなんと言おうと、俺の好きな音はこれなんだ!〉みたいな感じで変にトガっちゃってたし、いま思うと音楽的にも硬化してたなと。そんな頃にシモダがバンドを解散し、そのあとに彼の知り合いが集まっていくなかで、ISYYの基盤ができたんです。言ってしまえば、僕らは挫折から始まったバンドなんだよね?」
シモダ「そうだね。僕らはグランジ/オルタナティヴを共通項として仲良くなったけど、一緒にやるならそれだけじゃダメだと思ってました。もちろん好きなことをやるのは前提だけど、かといって以前と同じようなことを繰り返したくはなかったし、ちゃんとリスナーに受け入れられるような音楽を作りたいなって」
――具体的には、どんな音楽性に向かおうとしていたのですか?
ムラカミ「グランジ/オルタナを基調としつつ、もっとハイブリッドなことをやろうと思ってました。僕らは2000年代以降に育ってきたわけだし、それまでに聴いてきたさまざまな音楽のテイストをうまく取り入れていきたいなと」
シモダ「バンドを結成した2015年頃は〈暑苦しくない〉がキーワードでした。それこそグランジ/オルタナにはそういうイメージがあるし、2000年代前半のストロークスとかも、あらためて聴くとけっこう暑苦しい感じがして。そうした時期にミツメとかを聴き始めたのもあって、もっとバランスが取れた表現の仕方があるんじゃないかと思うようになったんです。それでまずはバンドにいろんな制約を課してみようかなと」
――それはどんな制約を?
シモダ「最初にトライしたのが〈あえてサビを作らない〉ということ。それこそ拳を突き上げるような感じにはしたくなかったし、それまでは歌が担ってきた部分をギターに任せようとも考えてました。別の言い方をすると、ヴォーカルもギターと同じく楽器として捉えたらどうかなと」
肉体性を取り戻したい
――2017年のファースト・アルバム『Dove』では、ヴォーカルにもかなり深めのリヴァーブをかけていましたね。
ムラカミ「そうですね。当時は演奏としてもサラッとした表現を模索していたし、確かヨ・ラ・テンゴの流れを汲むようなイメージもあったんじゃないかな。ただ、ここ数年はそれだけじゃ済まないというか、僕らのやろうとしてることも結成当初とは変わってきてて。これは今回のリリースにも言えることなんですけど、また肉体的な表現に戻ってきているような感覚なんですよね」
――そこには何かきっかけがあったのでしょうか?
ムラカミ「たぶんそこに関しては世の中の流れも大きいと思います。それも音楽とかアートに限った話ではなくて、それこそ社会情勢とかも絡んでると思うし、僕ら自身が年齢を重ねてきた影響もあるんじゃないかな」
――連続でリリースされた今回のシングル4曲を並べてみると、どれも音楽的なアプローチが異なっていますよね。
ムラカミ「そうですね。アルバムを最終目標にしつつも、まずは自分たちが今やりたいことをひとつひとつ形にしていきたくて」
シモダ「今は結成当初の制約を取っ払ってる状態なんです。シングルはトライ&エラーができるので、その時々の気分に従いながら、ひとつひとつをぶつ切りで試してみたいなと思ってて」