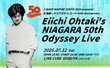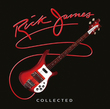呉青峰のアイデンティティーと和楽器の融合
――今回のコラボレーションを通して、お互いにシンパシーを感じる部分はありましたか。
蜷川「自分が前に進んでいるのか、後退しているのか。これは誘惑なのか、そうじゃないのか。目の前のことをやっていくうえで、とにかく進んでいるけども上手くいってるかどうかわからない状態というのは、すごくシンパシーを感じます。
先ほど〈海の神獣〉のお話もありましたけど、私も無意識の部分で生まれるアレンジやメロディーはあると思っていて。インプットをもとに頭のなかに浮かんでいることが、そのままアウトプットできるかというと、そうでもないですし。関わる相手や環境によって、その時々で発信する内容って変わってくると思うんです」
――自分のなかから生まれてきたアレンジやメロディーであっても、自分だけで完結しているわけではないと。
蜷川「外に向けて発信した先で起こる化学反応ってあるじゃないですか。今回は和楽器と台湾の音楽のコラボレーションでしたけど、そもそも私たちのやっている和楽器バンドのテーマは一方的に日本の伝統文化や音楽を伝えていくのではなくて、トレンドやシーンを取り入れつつ上手く融合させることで、今の世代の人たちが受け取りやすいように届けていくこと。なので、今回のコラボレーションも自分の〈和楽器をやっている〉というアイデンティティーと海外の彼が持つアイデンティティーが上手く融合して、お互いの可能性を広げられたらいいなとすごく思っていました」
青峰「同意します」
――青峰さんは、いかがですか。
青峰「もちろんシンパシーを感じました。コロナ禍ということもありインターネットを介しての音楽のやり取りとなったものの、べにさんたちから返ってきた曲は、自分が“(......Siren Salon)”を作りながら想像していたものでも想像以上のものでもあったので。
実をいうと、僕も自分の好きな中国文化やギリシャ神話など古典的なものを、現代の人に伝わる新しい形でアウトプットしたりアレンジをして作品化したりすることをすごく重要視しているんです。それは、べにさんたちの活動とも繋がることですし、だからこそべにさんたちの活動がクールだなって思ったんですよね」

自分が満足できる作品なら他人に認められなくても価値がある
――作品作りにおける化学反応を楽しめるおふたりかと思いますが、ご自身がよいと思える楽曲を作るために大切にしているのは、どのようなことなのでしょうか。
蜷川「そもそも〈何がよい楽曲か〉というのは、軸をどこに置くのかによって答えが変わるとても難しい問いですよね。売れる楽曲がいいのか、それとも自分のいろんな思いや発想がアウトプットされて昇華された楽曲がいいのか、アーティストとして活動していくうえでずっとずっと考えていくテーマだと思います。
私が〈いいものができたな〉とか〈わかりあえたな〉と思うのは、自分のなかで生まれた自分中心のインスピレーションが、何かしらの全く違う文化や国のアイデンティティーとぴったりハマったとき。今やっている和楽器バンドもそうですけど、いろんなジャンルの音楽やいろんな楽器があるバンドサウンドのなかで、自分が三味線でどういうアプローチをするのか、どんなふうにやれば新しい化学反応が起きるのかっていうところが、私にとって音楽の神髄かな」
――そう思うようになったきっかけがあったんですか。
蜷川「自分のルーツである三味線や日本民謡で、海外の楽曲や文化にアプローチしたりコラボレーションしたりするのは、ずっと〈やりたいな〉と思っていたことなので。小さい頃から演歌や民謡を聴く一方で、中近東や南米のラテン音楽や各国のオリジナリティーが出る民謡が大好きだったんです。今の自分はその想いを実現することができているように感じますね」
――青峰さんは、いかがですか。
青峰「すごく本質的かつ難しい問いですよね。僕も音楽人として正式に創作活動を始めて17、18年経ちますし、〈いい曲とはなんぞや〉という問いに対する葛藤は一通り経験してきたと思います。過去には、いろんな人が様々な意見やアドバイスを僕にくれました。〈もっとわかりやすい作品を作ったらいいのではないか〉という意見もありましたし、台湾で受けのよいバラードやラブソングは僕の得意とするものではないので、ひとつの課題であったことは事実です。
でも、下心ありきな目的や目標のある作品って、結局そんなにモチベーションがあがらないですし、自分が無理をしているといいものってできないと思うんですよ。自分が心の底から〈作る価値がある〉と信じられる、自分の内心から湧き上がってくる〈作りたい〉からしか、いい作品はできない。この年になって思うのは、自分にとって満足できるものであれば、他の人から〈これはいい曲だね〉という承認を得なくても、それは価値があるものなんだということ。
この曲のタイトルの海の妖怪が、僕たちを危険に晒し、どこかへ誘うかもしれない。そういったものに惑わされない気持ちをもって創作することが重要だと思います。僕は17、18年創作をするなかで、自分がまだやったことないことを『マラルメの火曜日』で実践・実験できたことが、何よりも嬉しいです」