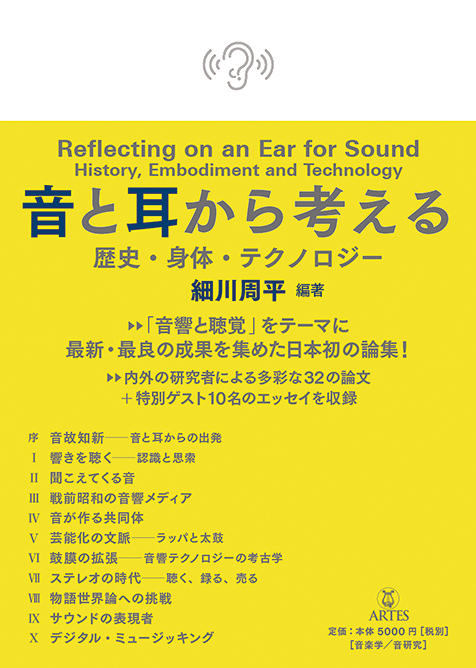鮮烈に細部がみえてくる〈声〉の研究

私にとっては初めてのタイへと家族旅行で向かっていた。バンコクのホテルにチェックインし、スマホをみると、本書の書評依頼が届いていた。なんてのはあまりにもできすぎた奇縁だが。濃密すぎるタイ行から帰宅すると本が届いてて、ワクワクしながらページを捲る。
日本コロムビアが、本書にもその名が登場する民族音楽学者・田辺尚雄が録音・収集し、1941年にSP10枚組でリリースした『東亜の音楽』を、CDとして復刻したのは1997年。この頃、ビクターも同時代の日本の〈軽音楽〉の復刻をしていた。研究者、演奏家、流通・販売業者、当のレコード会社のなかでも、掘ればいろいろ出てきそうだという話になっていた。その数年前、日本と韓国をまたぐかたちで韓国の巫俗(シャーマン)ものも含め民俗音楽の掘り起こし・記録も開始され、その中で〈悔しいけれど、戦前、日本のメーカーがかなりの録音を残している〉といった声も聞こえてきていた。
ざっと一読して、ぼやけているけど、強烈に心惹かれるモノクロ写真が、一気に画質を上げて迫ってくるような印象を受けた。ぼやけたままカラー化されたのではなく、あえてモノクロのままといいたいが、しかし鮮烈に細部が見えてくる感じというか。
総説では、共同研究をもとにする本書の成立経緯と問題設定・方法が記述される。植民地主義や資本主義研究の新たな視角と音楽研究も無縁ではいられなかったことが明確化されると同時になぜ〈声〉なのかも説明される。また、直接的なスタートラインですらが2011年開始の共同研究であり、本としてまとまるまでに長い時間がかかったことがわかるが、当然のことだと思うし、本書もまた熱心に研究を続けておられる研究者たちには途中経過でしかない。さまざまに〈続き〉も登場するだろう。
どの論考も、研究者ならではの緻密さで資料としても非常に重要なものだ。総説はまず読むべき。大きく〈レコード産業〉と〈レコード音楽の諸相〉と二部で構成された全9章は好きなところから読んでいいだろう。第1章の細川周辺論考と、第9章の垣内幸夫論考は、私見だがセットのようにも感じられ、冒頭と巻末のこのニ論考を経て、各章に進むのもいいかもしれない。近年の個人的な興味では、台湾の演劇と音楽の繋がりを論じた長嶺亮子論考には目を見開かされた。
本書は、さまざまに読まれうるだろう。細かな、忘れられた〈声〉〈音楽〉〈文化〉の襞のなかに分け入ろうとする人にも、大きく世界史を学ぼうとする人にも。それだけではなく、現代や未来の文化を探ろうとする人にも無数のヒントを惜しげもなく与えてくれるに違いない。