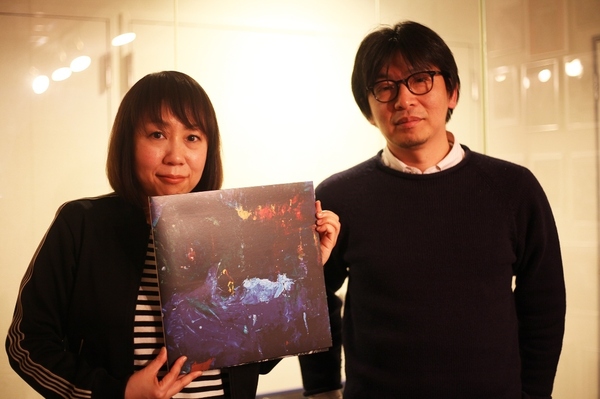常に変なものを生み出して、パラダイムシフトを起こすのは西海岸
岡村「ところで大和田先生に伺いたいんですけど、最近は西海岸に限らず、アメリカでは他のカルチャーも『ラ・ラ・ランド』のようなアングルのものが増えているのでしょうか?」
大和田「例えばアトランタのヒップホップ・シーンも、ラッパーの髪の毛がみんな赤や緑だったりするんですよ。もう完全にファンタジーみたいになっていて(笑)。リル・ウージー・ヴァートやリル・ヨッティー、コダック・ブラックとか、もうどれだけ髪の毛を派手にするかになっていて」
岡村「それはティム・バートン的なものとも、きっと違うんですよね。でもヒップホップの場合は、いくらかメッセージ性みたいなものが……」
大和田「いや、アトランタにメッセージ性はないです(笑)。だからやっぱり、うるさ型には批判されるんですよ。〈あんなものはヒップホップじゃない〉って。でもフォクシジェンの場合は、西海岸の表層的なイメージを徹底的になぞっているというのとも違う気がします」
岡村「オバマの任期が終わって、時代の気風みたいなことを考えたときに、やっぱりネガティヴになってしまう傾向がずっと続いていますよね。でもフォクシジェンの音楽は、ある種のアイロニー、特有の問題提起みたいなものも出てこないじゃないですか」
大和田「そうなんですよ、アイロニーなきファンタジーというか(笑)」
岡村「そういう彼らのスタンスは、社会性との乖離とイコールではない――そのように思いたいのですが、どう思われますか?」
大和田「政治と無関係に言うと……あまりこういう言葉も使いたくないんですけど、ポスト・モダンの完全なる内面化みたいな話は段階としてはあって。菊地さんがあんなに怒るのは、ポスト・モダンというのはもっと意識的にやるものだったんですよね。B級なものを用意して、断片を精緻に組み立てる、みたいな。でも、そうした価値観が無意識化され、内面化されたときにどうなるかというと、そこに作為やアイロニーがなくなるんですよ。メジャーなものとマイナーなものが留保なく並置されていて、何も悪びれずにアイロニーもなくなっていくという。それである種の人たちが『ラ・ラ・ランド』に激怒して、同じ場所からフォクシジェンのようなグループも出てきた。『ラ・ラ・ランド』に対して、ミュージカルや音楽が好きな人ほど怒っている印象がありますが、あの怒り方って、フォクシジェンを肯定する理屈とたぶん同じなんですよ。この反知性的に見える清々しさを許せるかどうか」
岡村「なるほどね」
大和田「ちなみに、〈ラ・ラ・ランド〉というのは夢の国を指す一般名詞で、もともとLAを意味していたんですよ。それで調べてみたら、ヴィレッジ・ヴォイスのサイトに〈Foxygen's Hang is a Technicolor Ode to La La Land (The Town, not the Movie)〉という記事が見つかって。タイトル通り、映画ではなくLAについて話した内容なんですけど。フォクシジェンには“San Francisco”という曲もありますが、そこでもサンフランシスコのサイケデリック・ムーヴメントが持っていた知性やカウンター性が剥奪され、LAが象徴するコマーシャルな書割りのなかでサイケデリックな世界観が全体化している。それがある種のふてぶてしさに繋がっていて、アンファンテリブル感がすごい。もはや〈お前の見ている世界はファンタジーだ〉なんていう批判がまったく通用しないというか。〈それで?〉、みたいな」
岡村「あと、LAの光と影というところで、イーグルスの“Hotel California”との関連性もありそうですよね。あれはすごく象徴的な歌詞だから」
――“On Lankershim”は、音的にもイーグルスと近いですね。
大和田「“Hotel California”はやっぱり西海岸における虚構のイメージを象徴していますよね。これもインタヴューで見掛けたんですけど、『Hang』をレコーディングしているとき、ケネス・アンガーの『ハリウッド・バビロン』※をスタジオに置いていたんですって。オーケストラ隊のメンバーに読ませるわけではなく、ただ置いておくと。そうしたら休憩時間に、それを読んだ人が影響を受けるんじゃないかと思ったそうで(笑)。だから、そういうハリウッドの暗部みたいなものには自覚的だったんでしょう」
※1959年にパリで出版された、ハリウッド黄金時代のスキャンダル暴露本
――そういえばLA繋がりで、サンダーキャットの新作『Drunk』と『Hang』に同時代性みたいなものを感じたんですよね。サイケ感やフランク・ザッパっぽさも含めて。
岡村「あっちは、ケニー・ロギンスにマイケル・マクドナルド(笑)。やっぱり今は、西海岸が目まぐるしく動いている」
大和田「常に変なものを生み出して、パラダイムシフトを起こすのは西海岸なんですよ。昔はハリウッド映画だって、エリートが観るものではなかったわけだし。ジャズもそう」
岡村「NYのショウビズに対してのLAのあり方というのは、明らかに分断役でありますものね」
大和田「〈この表層的で薄っぺらいのはなんだ!〉と良心的な人たちに批判されるんだけど、いつの間にか時代は西海岸に移っていくという。そういう痛快さがフォクシジェンにもありますね。東海岸でコンシャス・ラップを一生懸命やっていたら、いきなりギャングスタ・ラップが出てきた頃みたいな」
岡村「似ているかどうかは別にして、ジェリーフィッシュが西海岸(サンフランシスコ)の出身ですよね。ジェリーフィッシュはここまで突き抜けたことはなかったけど、彼らが登場したときも〈突然変異〉と騒がれて。でも彼らは、ウェストコースト・ポップの系譜にきちんと乗っていたわけですよ。(初期メンバーの)ジェイソン・フォークナーは、元を辿ればペイズリー・アンダーグラウンドという音楽シーンにいたスリー・オクロックの一員で、そこにはバングルズのような人気バンドもいた。さらに元を辿っていくと、その根っこにあるのがハーパーズ・ピザールで、レニー・ワロンカーがいて、バーバンク・サウンドに繋がっていく。フォクシジェンもその系譜にある存在だと思うんですよ」
大和田「そうですよね、バーバンク・サウンドのように映画音楽的だし、サウンドとしてはヴァン・ダイク・パークスの系譜にも乗っかっている」
岡村「けれども、ネタとして洒落たものとか、当時は売れなかったマニアックなものではなく、バカみたいに売れたような作品をレファレンスにしている邪気のなさたるや、ってところですよね(笑)」
大和田「良くも悪くも、NYには知的な抑圧があるので、ビリー・ジョエルやシカゴが最高とはまだ言えないんじゃないかな。そういう意味では、ダーティ・プロジェクターズは東の人だというか」
岡村「でも、デイヴ(・ロングストレス)はLAに移住したんですよね。昔はみんなブルックリンに集まっていたのが、どんどん西に移っている」
――そこも重要ですよね。では最後に、『Hang』について話しておきたいことはありますか?
岡村「ラジオ・フレンドリーだし、ジューク・ボックスから流れてきても不思議ではないというか。シカゴやビリー・ジョエルのような70年代のメイン・ストリーム・ロック、ポップスに思い入れのある方にもぜひ聴いてほしいですね」
大和田「このアルバムで、すごくスケールアップしている感じがありますよね。それなりにバジェットをつけて、やりたいことをやっている。もう肯定するしかないですよ」
岡村「録音はアナログでこだわっているけど、そういうハンドメイド感が貧乏臭くないんですよね。それもかなり大きい。ゴージャス感も出ているし、音質も悪くはない。チープなところが一切ないし、あったとしてもそれを過剰なアレンジでカヴァーしている。〈ギター一本で俺の気持ちを届けます〉みたいな価値観に対する、完全なアンチテーゼになっていますよね」
――インディー・ロックは、〈地味だけどいい〉という価値観にすがりがちだから。
岡村「そうですね。ボン・イヴェールだって、最初に出てきたときは〈地味だけどいい〉ポジションだったのが、今ではあんなふうになったわけじゃないですか。それに続く形で、フォクシジェンみたいな存在が表に出てきている。このまま下克上で覆るとおもしろいなって。もしかしたら、こういう形でしかインディー・ロックの突破口はなかったのかもしれない。それくらい大きな意味のある作品だと思います」
大和田「確かに、ここは手つかずでしたよね」
岡村「あとは売れまくって、50年後に100円で転がってるレコードになっていてほしい(笑)。もちろん褒め言葉ですよ」