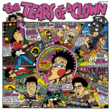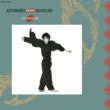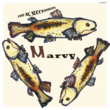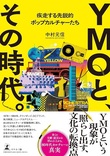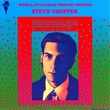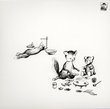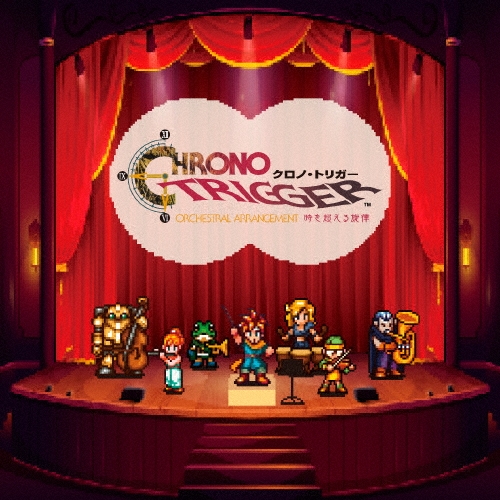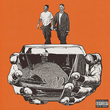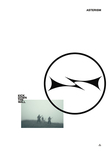ポップなレコード『COVERS』が理解されず反逆者になってしまった
――野音のライブは8月13、14日ですね。
「夏の野音って、お祭り的なところがあったのに……。それが、変な意味を持ってしまったんです」
――セットリストはどうでした? 『コブラの悩み』の収録曲は一部ですよね?
「正直、あまりいいセットリストじゃなかったですね……。はっきりしたメッセージがあったとは、僕には思えなかった。
これは難しいところで、清志郎さんはトップスターだから、どんな表現もポップにできるんです。さらに、スタッフの生活を背負っているので、商売にしなきゃいけない。でも、スベってしまった。
それより、このときのライブは、ポップで偉大なバンドによるミラクルなロックンロールショーではなくなってしまっていたのが残念でした。翌年(89年)の野音は、そういうにおいを消した素晴らしいロックンロールショーに戻っていて、僕が体験したRCのライブのなかでもベストに入る内容でした」
――〈LOVE ME LIVE TOUR 1988〉(12月5~25日)はどうでした?
「事件のにおいは残っていたと思いますし、全体的に暗いトーンだと感じました。『COVERS』は、あんなにポップなレコードなのに……。
こんなことを言うと怒られてしまうかもしれませんが、RCって真面目なメッセージをドカンと投げるようなバンドじゃなくて、それを別のところにバウンドさせて届かせるセンスがあったのに、ストレートに権力に立ち向かう社会派に仕立て上げられてしまったんです」
――ファンは、活動家になってほしいわけではないですよね。
「THE TIMERSはパロディだと打ち出していたのでまだよかったのですが、『COVERS』の発売中止と夜ヒット(夜のヒットスタジオ)事件※のおかげで音楽的なイメージが吹っ飛んでしまったのが残念でした。
2016年の兵庫慎二さんによるインタビューでCHABOさんが、RCは大メジャーでもなければでもマイナーでもないおもしろいバンドだったと語ってましたが、僕もそこが好きでした。が、そのおもしろさが理解されなくなってしまった。
社会派の一面があるおかげでRCはいまもいい位置にいられていると思いますが、ソングライティングについてももっと語られてほしい。『COVERS』だって、新しいソングライティングを提示しているのに」

替え歌ソングライティングのパイオニア
――替え歌というソングライティングですね(笑)。
「清志郎さんって、海外のポップスに日本語が付けられたものが好きだったんだと思います。先ほどの高石さんの“明日なき世界”や越路吹雪さんの“ラストダンスは私に”、中尾ミエさんの“可愛いベイビー”、弘田三枝子さんの“夢見るシャンソン人形”など、昔は素晴らしい作品があって、“シークレット・エージェント・マン”にはそのムードを感じます。シャンソンの“サン・トワ・マミー”やレインボウズの“バラバラ”のカバーも秀逸です」
――“ラヴ・ミー・テンダー”もそうですよね。
「THE TIMERSの“デイ・ドリーム・ビリーバー”だって、元の歌詞をべースにしていますが、まるでオリジナルのようです」
――原曲に沿った歌詞の曲もありますが、“サマータイム・ブルース”などは歌詞をガラッと変えています。このいたずらっ気、ユーモアがおもしろいですね。
「CHABOさんは、90年のライブでキンクスの“All Day And All Of The Night”に日本語詞を付けてカバーしていました。
発明とまでは言いませんが、このソングライティングはRCが日本のロックにおけるパイオニアだと思います。洋楽からのインスピレーションを昇華させるセンスが絶妙だったんです」

奇才チャールズ・ハロウェルとの出会いが生んだオルタナサウンド
――〈RCサクセションの忌野清志郎〉とその後のソロは、またちがいますよね。
「RCでは、エンターテインメント性を追求したんだと思います。RCはあくまでもバンドで、メンバーの個性が合わさるのが最大の魅力でした。清志郎さんはバンド内で1/3、あるいは1/5の存在で、それがみずから〈バンドマン〉と名乗ることに繋がっている。
CHABOさんは、バンドのなかにソングライターが2人以上いるのは難しい、と松村雄策さんとの対談でおっしゃっていました。特に、自分でソロアルバムを作ってから難しくなってしまったと」
――CHABOさんにはCHABOさんの美学や哲学がありますからね。
「清志郎さんのソングライティングって、リスナーの考える余地を空けておくので、自分もそこに参加できるんです。
そういう清志郎さんの個性とCHABOさんの美学が最高の形でハマったのは、“ハイウェイのお月様”だと思います」
――“ハイウェイのお月様”、名曲ですね! もうひとつの“スローバラード”とも言える世界が素敵です。
「なので、はっぴいえんどやシュガー・ベイブのように、RCもソングライティングや音楽面を掘り下げてほしいんです。
『COVERS』は、エンジニアのチャールズ・ハロウェルと一緒にやりはじめた頃の作品で、すごくいいと思いますし」
――そうですね。
「チャールズとは、ケミストリーが起こっていると思います。彼はABCなどのニューウェーブ系やPIL、サイケデリック・ファーズにも関わっていたエンジニアです。有名どころではパワー・ステーションのドラムの音を作ったと言われていて、ペイル・ファウンテンズのサードアルバムにも取りかかっていたそうですね。
彼は、トッパー・ヒードンのソロ作を担当していて、その流れで『RAZOR SHARP』を担当することになりました。チャールズの音って、ネオアコにも繋がる独特のオルタナな音ですよね。彼は音をいっぱい入れるのが好きだったようですが、清志郎さんはとにかく〈消せ消せ〉と言っていて、それで〈erase〉という英語を覚えたそうです(笑)。
『RAZOR SHARP』から『MARVY』、『COVERS』、『コブラの悩み』、『THE TIMERS』(89年11月8日)まで、清志郎さんとチャールズの仕事を追うと、相当おもしろいんですよ。日本人音楽家としてのアイデンティティを確立させた清志郎さんと英国のシーンからはみ出した奇才の出会いが生んだ、オルタナサウンドなんです」
――それは新鮮な視点ですね!
「アメリカ人やロック系エンジニアだったら、これほどリバーブ感のある音にならず、重厚になっていたかもしれませんが、楽しめるものになったかはわかりません。ヘビーなことを歌ってもチャーミングにやるRCの魅力に、チャールズの音はぴったりでした。
RCは、レコーディングバンドとしてすごくトライをしているんです。〈レコードよりライブのほうがいい〉と言われていましたが、そんなことはないですね」