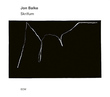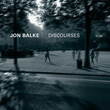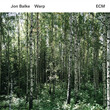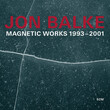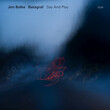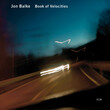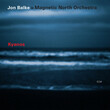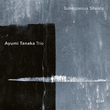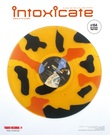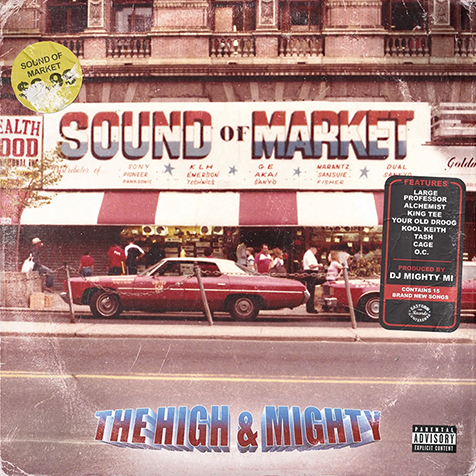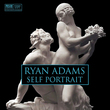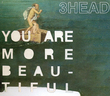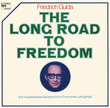〈Jon Balke “Piano with Spektrafon” Sound in Motion, Silence in Layers〉が2025年10月5日(日)に東京・南青山BAROOMで開催される。ノルウェー生まれ、北欧ジャズを代表する音楽家の一人であり、ECMの鬼才として知られるヨン・バルケの来日公演だ。今回は、彼が独自に開発したライブエレクトロニクスシステム〈Spektrafon〉を駆使し、ピアノと音のレイヤーを自在に往還する最新プロジェクトが日本で初披露され、ドラマーの福盛進也、書家の白石雪妃と特別なセッションを展開する。一夜限りの貴重な公演に向けて、彼を敬愛し、同じくノルウェーの地でECMから作品をリリースしている日本人ピアニスト/作曲家の田中鮎美に特別寄稿してもらった。 *Mikiki編集部
ヨン・バルケさんのこと
〈私たちの耳は聞こえているか。〉
ヨン・バルケの今年発表されたアルバム『Skrifum』を聴いていると、この言葉が頭を巡った。
これは、作曲家の武満徹さんの著書のタイトルにもなったエッセイの題であり、〈音を積極的に聴き出すということ〉の大事さについて、武満徹さんは度々、お話をしていらした。私は一人の音楽と向き合う人間として、この言葉に立ち返ることを大切にしている。
それから、ピアニストの菊地雅章さんが少なくとも晩年、レコーディングする時にヘッドフォンをつけなかったという話を、最近ある人から聞いたのだけれど、それは倍音を最大に聴くため(聴き出すため)であったそう、という話を思い出した。
じゃ、どうしてヨン・バルケのこの作品を聴いて、このようなことを考えずにはいられなかったのだろう。
タイトルの〈Skrifum〉という言葉はアイスランド語で、英語の〈Write〉という意味だそう。日本語でいうと〈書く〉とか〈記す〉とか。そういえば、曲を書く時も、〈Write〉という単語を使ったりもする。
ヨン・バルケの音楽はとにかく旋律が美しいのだけれど、このアルバム全体を通して、ピアノで奏でられるほとんどが、単旋律なのが印象的だ。筆で描かれた線が現れたり消えゆくようだったり、一匹の魚が水の中を泳ぐのに伴って揺らめく、水の動きを眺めているような気持ちになった。旋律そのものよりも、その旋律により移ろいゆく周りの様相に魅了されていたのかもしれない。これらの旋律がもしも、文字ならば、私は本の空欄に美しさを見い出していた。
もう一つ、このアルバムの特徴は、Spektrafonという彼が開発に関わった電子機器を使っている点で、〈ピアノから出る音〉から引き取った要素をこの機器で奏でて、ピアノの音と同時に演奏する、ということをしているそうだ。
そこで考えた。〈ピアノから出る音〉とは何なのか。Spektrafonによって引き抜かれた〈音〉を私はヘッドフォンから聴いていたのだけれど、私の耳にはちゃんと聴こえているのか。そして、Spektrafonという機器には、ちゃんとピアノの音が聴こえていたのか。(機械だから、もちろん耳はないけれど、森に住む、野うさぎのように耳を立てて聴いている様子を想像してみたりした。)
ただ純粋な音を、そのできる限りの質感や振動、倍音、そしてその向こう側にある音を聴きたいと願い、耳を澄ませる。でも、うまく聴こえたり、聴こえなかったりする。
そして、気づいた。私が聴いているのは、そこに録音された音だけではないのかもしれない、と。それは、想像による〈音〉なのか、それとも記憶の中にある、経験や知識に基づく〈音〉なのか。耳で聴いているつもりでいて、実際は、頭で聴いてしまっているのか。