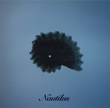海外でも人気を集めるポップバンドLampのサポートや、奄美大島の唄者・里アンナとの異色ユニットなど、多岐にわたるフィールドで活躍するドラマー佐々木俊之。彼がリーダーを務めるインストバンドがNautilus(ノーチラス)だ。
ドラム、ベース、ピアノのトリオ編成によるアンサンブルは、ファンク、ソウル、ゴスペルをルーツに持つゴリッと太いビートに、個々のプレイヤビリティが存分に投影されるジャズのインプロビゼーションを柔軟に取りいれたサウンドで、無二の存在感を示している。2014年の結成以来、年に1枚のペースでアルバムを発表し続け、近年は日本国内での活動のみならず、2年連続でドイツツアーを成功させるなど、海外での評価を高めている。
結成10周年を迎えた2024年12月に、通算9作目のアルバム『Sunrise』を完成させたNautilusから、リーダーの佐々木に話を聞いた。


ジャズとクラブシーンの間で掴んだ音楽性
――佐々木さんがドラマーとしての活動を始めたのは、いつ頃からになりますか。
「ドラム自体は高校生ぐらいからやっていて、大学に入ってからはサークルの仲間とバンドを組んだりしていました。ジャズ研の他にも、ゴスペルのサークルに入ってバックバンドをやっていた時期もあったりしましたね。
プロとしての活動のスタートは22、23歳の頃です。もう亡くなられた方なんですが、サックスの臼庭潤さんのセッションに呼んでもらったんです。その方と一緒にやっている時に、トロンボーンの北原雅彦さん(東京スカパラダイスオーケストラ)だったり、腕利きのプレイヤーの方々と一緒にやらせていただいて。その頃から、自分のキャリアが始まったのかな。
あと、自分で曲を作ることも好きだったので、自分のバンドもやりつつ、いろいろなアーティストのサポートもしつつ。本当、いろいろやってきました」
――僕が佐々木さんの演奏に触れたのは、〈里アンナ × 佐々木俊之〉での演奏が最初でした。奄美島唄とドラムという一風変わった組み合わせながら、多彩なリズムアプローチで島唄が描く情景をさらに広げていくような印象で、とても興味深く聴きました。
「そうでしたか。それは嬉しいですね」
――その他にも、ここ数年で海外リスナーからの評価も高まっているLampのライブサポートを手がけるなど、活動は多岐にわたります。中でも本筋といえるのが自身が結成したバンドであるNautilusですが、そのサウンドからはファンクやジャズ、ソウルなど、ブラックミュージックからの影響が強く感じられます。
「やっぱりブラックミュージックがすごく好きなので、自分の音楽の基本にあると思います。きっかけになったのは、中3の頃に初めて聴いたジャミロクワイでした。それまではユニコーンしか聴いたことなくて……、今でもユニコーンはすごく好きなんですけど。ジャミロクワイを聴いたときに、最初はよくわからなかったけど〈この音楽なんだろう?〉みたいな感じでどんどん気になっていって。ライナーノーツを読んだら、 ボーカルのジェイケイが好きなアーティストを挙げていて、それがスティーヴィー・ワンダー、ロイ・エアーズ、ギル・スコット・ヘロンだったんです。まずはこの3人から聴き始めて、そこからブラックミュージックにどっぷりハマっていった感じですかね。
今やっているNautilusのサウンドも、ジャズの要素を取り入れつつ、ビートはしっかり立っている。そういうものがやっぱり一番好きなので。今でいうと、ロバート・グラスパーあたりになるんでしょうけど、それも大元にはロイ・エアーズなどがいてこそのものだと思います。そういうビートをジャズにのせてきた先達に、リスペクトを感じますね」
――1990年代のジャズファンクやアシッドジャズのムーブメントの影響をダイレクトに受けた世代というか。
「はい。大学1年生の頃、西麻布のイエローでU.F.O.(United Future Organization)が主宰する〈Jazzin’〉というイベントがあって。よく一人で行っては朝まで踊っていたんです。クラブ向けのいわゆる4つ打ちビートをジャズにのせたりするセンスが新鮮で、U.F.O.からはかなり影響を受けましたね。
あとは沖野修也さんが選曲したコンピレーション盤なんかを聴いて、いまクラブではこういうのが流行ってるのかと情報を得たりして。そうしてクラブシーンとジャズシーンを行ったりきたりしながら、自分の志向が見えてきたような気がします」