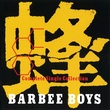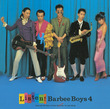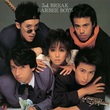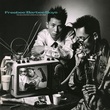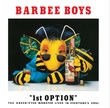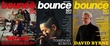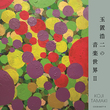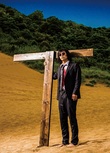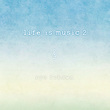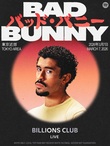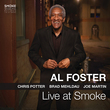タワーレコード新宿店~渋谷店の洋楽ロック/ポップス担当として、長年にわたり数々の企画やバイイングを行ってきた北爪啓之さん。退社後は実家稼業のかたわら音楽に接点のある仕事を続け、時折タワーレコードとも関わる真のミュージックラヴァ―です。
そんな北爪さんのユーモラスな発想と語り口で、時代やジャンルを問わず様々な音楽を紹介してきた連載〈パノラマ音楽奇談〉が2024年をもって終了。そしてこのたび、北爪さんのリスナーとしての原体験、果てしない好奇心を前面に押し出した新連載〈聴いたことのない旧譜は新譜〉がスタートします。
日々めまぐるしい速さで更新されていく音楽シーンにおいて、瞬く間に新譜(=新作)は旧譜(=旧作)と言い換えられてしまいます。そんな旧譜と称されてしまった作品から、いま現在の耳で聴くべきものを独自の視点を交えて新譜として紹介していくのが、本連載のテーマです。
記念すべき初回は、1984年にデビューし、現在40周年イヤー真っただ中のバービーボーイズをピックアップ。KONTA(ボーカル/サックス)、杏子(ボーカル)、いまみちともたか(ギター)、エンリケ(ベース)、小沼俊明(ドラムス)から生み出される音楽の魅力に迫ります。 *Mikiki編集部
バービーボーイズの音楽は〈シティポップ〉だった
昨年メジャーデビュー40周年を迎え、オリジナルアルバムがアナログとBlu-spec CD2で順次リイシューされているバービーボーイズに再び注目が集まっている。
僕が彼らを初めて聴いたのは1987年、中学3年生のときだった。たしか何かのテレビ番組だったと思うが、ソプラノサックスを吹きながらハイトーンで歌う男性ボーカルと、スカートの裾をひらひらさせながら踊る低音の女性ボーカルが掛け合うスタイルのインパクトは絶大で、すぐさま小遣いを握りしめて“女ぎつね on the Run”のシングルを買いに走ったのだった。
もっとも、まだ恋愛経験のないウブな中坊には、男女の複雑な関係を描いたバービーの歌詞はほとんど理解できなかったのだが、それでもKONTA(コンタ)と杏子の丁々発止でスリリングなボーカルの応酬がじつに〈大人的で都会的〉に聴こえたのだ。それは当時なぜか好きだったわたせせいぞうの漫画「ハートカクテル」の、日本だかNYだか西海岸だかよくわからないお洒落な街で小粋な大人たちが恋したり別れたりする物語に近いものを感じていたように思う。ようは地方の中学生の実生活とは遠くかけ離れた華やかな世界への憧れというのか。その意味において僕にとってのバービーの音楽とは言葉通りの〈シティポップ〉だったのだ。
以上は当時リアルタイムで聴いていた僕の体験と感想だが、曲がりなりにもタワレコのバイヤーとして20年以上を過ごし、その後も音楽に関わる仕事でどうにか生計を立てている現在の自分は、当然そんなテキトウな印象だけで原稿を終わらせるわけにはいかないのである。
なぜ〈男女ツインボーカル〉で〈サックス入りのロックバンド〉だったのか
バービーボーイズの特徴といえば、〈男女ツインボーカルでサックス入りのロックバンド〉という変則的な編成と、〈男と女の生々しいやり取りを描いた歌詞&会話調の文体〉になるだろうか。それに〈同時代のニューウェーブを思わせる洋楽的なサウンド〉というのを加えてもいいかもしれない。バービーは元ネタがわからないバンドと言われることも多いが、今回は彼らのそうした特異性のルーツや影響源について、いまの自分の視点から思うところを書いてみたい。
そもそも〈男女ツインボーカルでサックス入りのロックバンド〉というアイデアは一体どうして生まれたのか? リーダーのいまみちともたか(イマサ)が過去に語っていた発言からすると、サックスに関してはメン・アット・ワークの大ヒット曲“Who Can It Be Now?”を聴いて感銘を受けたイマサが、まるで吹いたことのないコンタに無理やり勧めたようである。なるほど、言われてみればメン・アット・ワークはサックスやフルートを効果的に導入していたバンドなのでそれは腑に落ちるのだが、だからといっていきなり素人に吹かせるのは、むしろNYノーウェーブばりに破天荒な発想ではないか。しかも当時のコンタは天井桟敷や暗黒舞踏などのアングラ演劇にハマっていたらしいので、一歩間違えたらかなり怪しく前衛的な方向に向かっていたのでは……という要らぬ心配をしてしまうのだった。