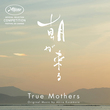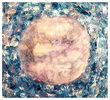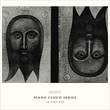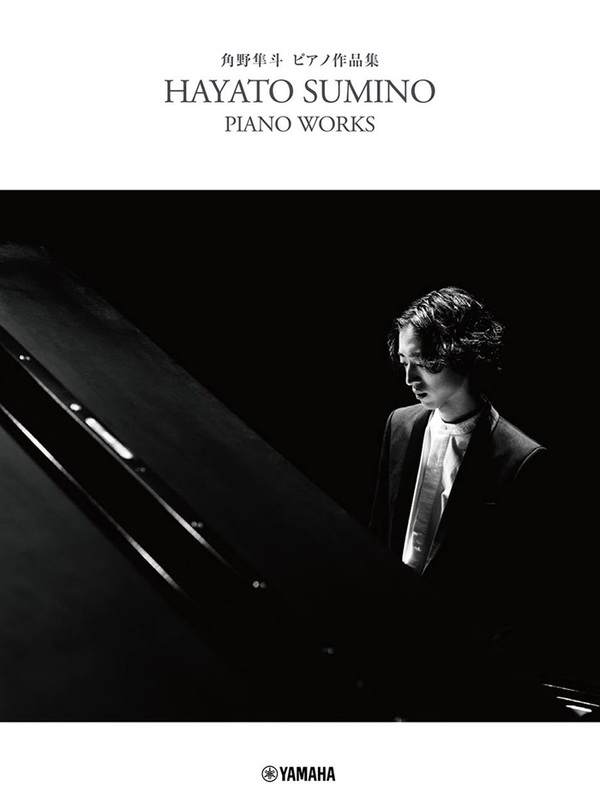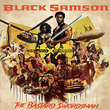双方向的な共同作業とコミュニケーションで作り上げていった〈歌〉
――歌詞に関しては、どういう風にアプローチされたのでしょうか?
「曲ごとに違います。こちらで歌詞を渡した曲もありますし、畠山美由紀さんに歌っていただいた“Autumn Moon”は、百人一首の歌に僕が曲を付けました。これは日本の歴史的な和歌から自分がシンパシーを感じるものを選んで、それを曲にするという新しい試みだったんです。
ベンジャミン・グスタフソンとデヴェンドラ・バンハートには僕が書いた日本語の歌詞を歌ってもらいました。デヴェンドラは日本の70〜80年代の音楽をめちゃくちゃ掘っていて、〈次に一緒にやる時は日本語で歌いたい〉と言っていたんです。彼って仕事で音楽をやらない人で、音楽をとことん気に入らないとダメなんですよね(笑)。それで僕が書いた曲と日本語の歌詞、そして、その英語の意味を彼に送ったら、幸いすごく気に入ってくれました。そして、曲の後半にアドリブでコーラスを入れてくれたりもしたんです。
ベンジャミンはスウェーデンのアーティストなのですが、最初日本語がうまく発音できるか心配をして歌うことをためらっていたみたいで。僕はスウェーデンの言葉でも英語でも良かったので、どの言語に置き換えて収録するかという話もしていたのですが、彼が試しに日本語で歌ったものを聴くとすごく素敵な歌になっていたので、〈とっても良いよ!〉と感想を伝えたら納得してくれていました」
――曲によってアプローチが違うんですね。
「いま海外のメインストリームの音楽シーンでは、5〜6人で一曲を作るのが主流になっていますよね。トラックを作る人が何人かいて、トップラインを作る人、そして歌う人がいる。なので今回は、僕も歌をお願いした方と曲を作り上げていくようにしました。
畠山さんのように歌うことにフォーカスをして、歌手として魅力的な活動ができる方もいれば、自分の歌は自分の身体から出てくるものなので、ただ歌うだけなのは表現の手段として苦手という人もいる。だから、僕が作った曲をそのまま歌ってもらうというよりは、僕が送った曲に対して受けたインスピレーションでコラボレーションしようと思ったんです。
例えばバスには〈こんな感じのイメージなんだけど〉とトラックを送って、彼がトップラインを考えてくれました。バスは日本の音楽やカルチャーに詳しく、トラックを聴いたら谷口ジローの『歩くひと』という漫画のイメージが湧いたそうで、そこからトップラインと歌詞を思いついたんです。だから、“The Walking Man”という曲名になりました。コライト(共作)の曲に関しては、自分では思いつかないアイデアが入ってくるので発見があって面白かったですね」
ミスター・ハドソンやデヴェンドラ・ヴァンハートらとの多彩なコラボ
――コラボレーションの仕方が様々ということもあってか、本作には多彩な曲が並んでいますね。そこも、これまでの作品とは違うところです。
「僕は劇伴などでいろんなタイプの曲を作ることがあるんです。でも、ソロ作品ではピアノを弾くだけで自分の表現ができるから、いろんなタイプの曲を作ろうという気持ちはそんなになかったんですよね。でも、今回は言語の融合とか、楽器の融合、ジャンルの融合とか、様々なことを試してみたかったんです。
これまでだったら、ひとつのアルバムにいろんなジャンルの曲を入れるよりも、コンセプチュアルにまとめていたと思います。でも今回は、自分がこれまで影響を受けてきた音楽の引き出しを開きながら作ってみました」
――確かに個性豊かな曲が並んでいますね。ミスター・ハドソンをフィーチャーした“Always You”は洗練されたポップソングに仕上がっていて、これまでの小瀬村さんの作品にはなかったタイプの曲です。
「ミスター・ハドソンはジョン・レジェンドの『LEGEND』というアルバムに参加した時に、“The Other Ones (feat. Rapsody)”という曲で僕の曲(“Asymptote”)をサンプリングしてくれたんです。
彼はジョン・レジェンドやカニエ・ウェスト、ジェイ・Zなど、ヒットメイカーたちとコライトしている人で、僕からはかなり遠い存在でした。でも、彼が僕の曲をスタジオに持っていったら、ジョンが気に入ってジョンの曲に昇華された。メインストリームの人が僕の曲を認めてくれたというのは自分にとっては発見で、〈じゃあ、僕のフィールドでメインストリームの人とやってみたらどうなるんだろう?〉と思ったんです。
それでハドソンに連絡して〈一曲一緒に作りたい〉と言ったら、〈いいよ、曲を送って〉と言われて。曲を送った3日後ぐらいには完璧に構築されたトップラインが送られてきて、〈あとはマネージャーと話してくれ〉というプロフェッショナルな対応で(笑)。この曲ではトラップ風のトラックとモダンクラシカル的なハーモニーを構築してみたいと思っていたのですが、うまくいったと思います」
――それは面白い組み合わせですね。デヴェンドラが歌った“Ongaku”も和楽器を取り入れてユニークな仕上がりになっています。
「デヴェンドラと一緒にやるんだったら、彼が好きな70〜80年代の日本の音楽に向き合ってみようと思いました。そして、お祭りのようなイメージで、いろんな音楽を融合させて自分なりの日本のポップソングを作りたいと思ったんです。三味線、尺八、箏、二胡、笙、ドラム、フレットレスベース、ウーリッツァーも入っているんですけど、何度かご一緒しているジャズドラマーの能村亮平さんを誘ってECMっぽいリズムを試したり、ベースはジャコ(・パストリアス)が大好きな織原良次さんに頼んでフュージョンっぽいアプローチをしたり、西洋やアメリカの音楽要素を組み入れつつも、ちゃんと日本っぽい曲にはなっている。でも、ちょっと変なんですよね(笑)。
このアルバムをいろんな人に聴いてもらったんですけど、〈どの曲が良い?〉って訊くと、この曲をあげる人が多いんですよ」
――様々な要素がミクスチャーされて、不思議なエキゾティシズムとポップさを醸し出している。それが東京っぽいなと思いました。
「デヴェンドラも敬愛する細野晴臣さんが、そういったことをすでにやっていらっしゃいましたよね。やり方は違うけれど、いま聴いてもすごく面白い音楽なので、この曲で自分なりにやってみたんです」
――“Atlas”で歌っているトム・アダムスとはどのようにして出会ったんですか?
「彼のアルバム『Silence』(2017年)の1曲目(“Come On, Dreamer”)がすごく好きで、一緒にできたらいいなと思っていました。なので、プロジェクトのかなり早い段階でトムに連絡しようと思っていたんです。僕も作品を出しているカナダのモデルナ・レコードから彼もリリースしていたので、モデルナ経由で依頼しています」
――すごくシンフォニックでレイヤーの厚い曲ですよね。
「〈トムとやるんだったらこのサウンド〉と最初から決めていたんですよね」
――唯一日本人シンガーとして参加されている畠山さんは、なぜ起用したのでしょうか?
「昔から聴いていて、妻も大ファンなんですよね。エンジニアの檜谷(瞬六)さんが畠山さんと仕事をしたことがあって、〈百人一首の曲は日本人に歌ってもらいたい〉と相談したら畠山さんの名前があがったので、〈絶対に合うな〉と思ったんです。畠山さんに歌っていただいたら〈命を吹き込んでもらった〉と思うぐらい変わって、すごく感動しました」
――曲自体はミニマルで、短歌など日本的な世界観に通じると思いました。
「ええ。詩自体はすごく古いものですが、長く愛されているだけの説得力がありますよね。日本人の魂や血が感じられて、そういうものにちゃんと耳を澄ませたいと思わせられます」