
色情狂の終わらない性遍歴
俗にいう「うつ三部作」の掉尾を飾るにふさわしい作品である『ニンフォマニアック』は「色情狂」を意味し、表題通り、三部作すべてに出演したシャルロット・ゲンズブール演じる色狂いの女、ジョー(「Joe」とはつまり「Jaw」でもあるだろう)の性遍歴を描く、『Vol.1』と『Vol.2』合わせると4時間にもおよぶ大作である。
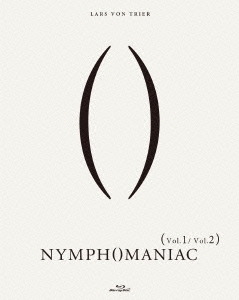
物語は路地裏で叩きのめされたジョーがセリグマンなる読書家の童貞の老人に拾われ、性に憑かれた彼女の生を問わず語りに語りはじめる、その回想にくりかえし影のようにあらわれる男、性癖、生活の営みのおりおりにおける転換と変転を時間に沿って描いていく、その視点はトリアーらしい突き放したもので、そのため過激な性描写あふれるこのフィルムは劣情をもよおさせるより、とくに前半は乾いてユーモラスですらある。モペットをもつ男、ジェロームに前を3回、うしろを5回突かれ処女をうしなったジョーは、3と5とをふくむフィボナッチ数列が雪だるま式にふくらむように性の谷へ転げ落ちる。いや、性だけに昇りつめるのか。ところがそこにまちうけるのは快楽ばかりではない。むしろその道程は歓びより痛みをともなっている。乱脈、不倫、異人種間セックス、SMにいたってジョーの性は物理的な痛みさえ丸呑みするがそこにあるのは倒錯や背徳のうしろめたさより黒い笑いである。人のセックスを笑うなともうされましても、人のセックスはほかのだれかの裸体がたいがい滑稽なようにおかしいのは、人のセックスは当事者ではない第三者を窃視者にするから、目のあたりにした私たちは勃起したり濡れたり眉をひそめたり鼻白んだりする。映画の虚構の語り口を性の他者性に重ね合わせたトリアーは性愛の真ん中を確然と分かち、愛のドラマを性の寓話に従わせる。ゆえに『アンチクライスト』で(意図的な)不注意で死なせてしまった息子もここでは死ぬ必要はないし、『メランコリア』のように癒されるべきものもない。「私は色情狂よ!」セックス依存症の集団治療でそういって決然と席を立ったジョーのセリフは前2作を経てオブセッションを肯定するにいたったトリアーの言葉としてだけでなく、パゾリーニがサド原作の『ソドムの市』にこめたように、その美しさもふくめてメンタルヘルスが支配する現代への批判とも読める。結末への流れはいかにもトリアーらしいものだが、黒みに覆われ判然としないラストシーンは、トリアーの女性観もまた変わりつつあることの暗示かもしれない。つまり『ニンフォマニアック』はラース・フォン・トリアーという21世紀の巨匠の転換点となる作品であり観て損はない、というか、観なければ。笑えるかどうかはあなたしだいだが。

















