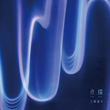自身のオリジナル作品のみならず、数々のCMへの楽曲提供やGotchバンドへの参加でも知られる京都在住のシンガー・ソングライター、YeYeがサード・アルバム『ひと』をリリースした。すべての楽器をみずから演奏した初作『朝を開けだして、夜をとじるまで』(2011年)、そして田中成道(キーボード)や浜田淳(ベース)、妹尾立樹(ドラムス)という現在もサポートを務める3人のライヴ・メンバーと共に、カラフルなポップスを作り上げた2作目『HUE CIRCLE』(2013年)――これら2作で浸透したガーリーでファンシーな彼女のイメージを、今作『ひと』は覆すはずだ。パンキッシュで躍動感溢れる一発録りのアンサンブルからは、日本各地でのライヴやリトアニアでのパフォーマンスなどを経て、さらに結びつきを強めた不動の4人編成が透けて見える。そして、プレイヤー陣の活き活きとした演奏を受け、YeYeのソングライティング・センスはいっそう多彩に開花した。それにしても、なぜ彼女はここまでロックなサウンドに傾倒したのか? Mikikiでは、その理由に迫るべくYeYeにインタヴューを行った。
これまで自分を馬鹿にしてきた奴を蹴り倒そうと思った
――『ひと』はバンド・サウンドに力点が置かれた作品になりました。
「活動しはじめたときから、最終的にはこういう感じのを音楽をやりたいと考えていたんです。でも、具体的にどんなサウンドかはフワフワしていた。逆にやりたくないことはいつも明確なんですけどね(笑)。YeYeバンドの3人と一緒に音楽をやり、彼らからいろいろな刺激を受けるなかで、やっとやりたいことがクリアになってきたんです。私は3人のことをすごく尊敬していて、傍から見たらサポート・ミュージシャンかもしれないですけど、私からすれば3人とも先生みたいな存在なんですね」
――ええ。
「音楽を始めた頃からずっとパンク精神を持って活動してきたつもりなんですけど、それを自分の音で伝えるのに時間がかかっちゃいました。今回はやっとそれができたように思います。演奏云々よりも、3人との信頼関係があったから今作に到達できたんじゃないかな」
――パンク精神を持って音楽をされている、というのは前作『HUE CIRCLE』のときにも話されていましたね。
「でも、もっとわかりやすく表現しないと、私のパンク精神は伝わらへんのかなと思いましたね。それをわかりつつ、この5~6年で反発心が積もり積もったことで、今回やっと自分なりの尖ったアルバムが出来たんです。アートワークについてもそうで、このアルバムはこれまでと違って、ジャケットに私が出ていない。もちろん前2作では、顔を前に出すことで、こんな人がやっている音楽だと伝わったとは思うんですけど、基本的にはレーベルの方針だったんです。ただ今作に関しては、私が小池アミイゴさんに直接〈作ってください〉とお願いしました。彼と初めてお会いしたのは、去年の12月に東京・参宮橋LIFEsonで行ったライヴなんですけど、なぜかアミイゴさんがその日のPAをされていて、すごく演奏しやすかったんです。YeYe史上初めて(PAに)なんの注文もなく演奏できたし、この人には委ねられる、と確信を持てた。何かを話さずとも、演奏しただけで私のパンク精神や反発心を全部見抜いてくれたんですね。実は、それまでアミイゴさんの手掛けた作品を見たことがなかったんですけど、〈この人しかないな〉と作成をオファーしました」
――YeYeさんがアミイゴさんにお願いするにあたってディレクションはあったんですか?
「それは一切なかったです。その代わりじゃないですけど、話し合いの場を設けて、私が音楽に対してどういう気持ちを持っているのか、どんなふうに育ってきたのかを伝えた。それらを汲み取ってくださり、このジャケットを作ってくれたんです」
――そのときYeYeさんが話していたどんな内容が、このジャケットには反映されているとお感じですか?
「ずっと〈ナメられたくない〉という気持ちがあるんです。何に対してナメられたくないのかはよくわからないんですけど。アミイゴさんとの会話でも、シンプルに言えばロック精神みたいなものをもっと前に出していこう、これまで自分を馬鹿にしてきた奴を蹴り倒そうとなった。アミイゴさんは毎回作風が変わる方なんですけど、今回は初めて切り絵で制作してくれて。それは、これまでのイメージを切り裂くという私の想いを投影してくれんだと思った。でもダークになりすぎず、明るさもしっかり残してくれて」

――YeYeさんはnoteで、いまのマネージャーが入る前は、交通手段の手配やメンバーのスケジュール管理など、マネージメント的な業務もすべて自分でされていたと書かれていて。いまの話を聞いて、そうしたやり方を執ってきたことも、〈ナメられたくない〉という意思の表れだったのかなと思いました。
「あー、そうですね。いまマネージャーとして手伝ってくれているマナちゃんも、レーベル(Rallye)のスタッフではなくて、私が個人でお願いしているんです。前の『HUE CIRCLE』ツアーでは、まだマナちゃんがいなかったし、物販もどんなふうに作るのかわからなかったので、トートバッグを4種類くらい作ってしまって(笑)。それがあまりに重かったのと、さらに25キロのスーツケースとギターがあり、荷物運びで腱鞘炎になったんです(笑)。普通やったらマネージャーやローディーがやってくれることまで、すべて自分がやろうとしていたことは、意識してなかったですけど、確かにナメられたくないというのがあったのかも」
――今作のロック色の強い演奏は、『HUE CIRCLE』以降の4人編成でのライヴを通して形作られていったものなのでしょうか?
「1曲目の“a girl runs”や“のぼる、ながめる”など6割くらいの曲は、ライヴを通していまの形になっていきましたね。基本的には、私がギターと歌だけのデモを3人に投げつつ、リズムはこういう感じで、とかなんとなくは伝えるんですけど、それを彼らなりの解釈で演奏してくれます。具体的な曲名を挙げるというより、映像的な描写で伝えることが多いですね。〈細長い空間をドアを開けながら進んでいくように淡々と〉とか、頭の中にあるイメージを伝える。たぶん信頼関係がなかったら意味がわからないと思うんですけど、この4~5年間一緒にやってきたことで、3人も私の性格を理解してくれて、〈なっちゃん(YeYe)がこう言うんやったら、こういう音作りやろうな〉 と返してくれるんです」
――〈このバンドのこの曲〉という言い方でなく、抽象的なイメージでやりたいことを伝えると。
「でも曲で伝えることもありますよ。”Broke Your Phone“は、ブロークン・ソーシャル・シーンにファイストがヴォーカル参加した“7/4(Shoreline)”が頭にありました。もともとファイストがすごく大好きで、そこからブロークン・ソーシャル・シーンに辿り着いたんですけど、あの曲には衝撃を受けたんです。ファイストもこういうパンクなときもあったんやな、と思って。〈私もこういう曲がやりたかったんだ!〉ということで、〈イメージはこの曲で〉と伝えました」
――いまブロークン・ソーシャル・シーンの名前が出ましたけど、それ以外にも前作以降にYeYeさんが発見した音楽はありますか?
「アルバムを作っているときは、ホントに他の音楽は聴いてなくて。前のアルバムのときは、ダーティ・プロジェクターズやスフィアン・スティーヴンスなど、そのとき聴いていたものを自分の音楽に落とし込めた感じやったんですけど、今回のアルバムに関しては音楽的なコンセプトはなかったですね。でも泥臭いというか、綺麗で整ったものじゃない、リアルなものを作りたいというテーマはあった。マナちゃんが入る前は、音楽を聴くどころじゃないくらい雑務に追われていて、自分が演者なのかスタッフなのか立ち位置がよくわからない時期もあったんです。気がついたらYeYeとしての新曲は“a girl runs “と“ate a lemon”の2つしか出来てなくて。彼女が入って、ようやく音楽に集中できるようになったんですが、新しい音楽を掘るというよりも、やたらとファイストばっかりを聴いていましたね。もともと大好きだったんですけど、いまはサウンドよりも歌に集中してみたりと、2巡目ならではの聴き方をしています。あとカレン・Oとかも」
人生の行事と音楽の行事は全部同じ部類に入っています
――歌に意識が行くようになったという変化は、今作にも反映されているのでしょうか?
「私はあんまり音楽ジャンルや歴史を知らないんですけど、ベースのジュンジュン(浜田淳)さんやドラムのリッキー(妹尾立樹)さんはすごく詳しくて、よく〈この曲のドラムはビートルズのアレな感じやな〉みたいな話をしているんです。私は全然わかっていないんですけど(笑)。今回のアルバムでは、音はもう4人の信頼関係に任せて、4人から出たものそのままで良かった。ただ歌い方に関しては、ファイストやカレン・Oを参考にしつつ、いろいろヴァリエーションを持たせて歌おうとしました。あとGotchさんのバンドにコーラスで参加している影響もありますね。Gotchバンドでは、声の出し方をGotchさんの声に合わせていくというか、自分の歌い回しだと合わないので、ひたすら〈リトルGotch〉になりきっているんです(笑)。小学生のとき、SPEEDやBoAをラジカセでかけて、物真似しながら歌っていたんですけど、それがGotchバンドではすごく活かされていて。中学生の頃に空気公団やベル&セバスチャンを好きになって、これまでのYeYeには彼らの歌い方が反映されていたけど、Gotchバンドを通ったことで、BOAやSPEEDの力強い歌声が戻ってきた(笑)」
――Gotchバンドでのサポート経験は、歌い方以外の面でも今作になにがしかの影響を与えていますか?
「音楽的な影響というよりも、Gotchさんはアジカンをずっとやってきて、チームで動いてきた時間が長いですよね。なので、その姿勢をすごく勉強させてもらった。ソロのときは、スタッフもそんなに多いわけではないですけど、Gotchさんを含めてみんながすごく気配りをされていて。例えばレコーディング・スタジオに美味しいお菓子が置いてあるとか、そういう些細なことだけで、みんなのテンションが違ってくるんですね。マネージャーを含めた〈チームYeYe〉を引っ張っていく存在として、こういう気持ちでいなきゃなと心掛けを学びました。あんなに人気があるのに、親戚のお兄ちゃんくらいのラフさで接してくれるし。Gotchさんの姿勢を見て、いつまでもみんなとちゃんと寄り添ってやっていきたいなと改めて実感しました」
――YeYeバンドの3人にも今作を通じて変化はあったのでしょうか?
「あったと思います。例えばジュンジュンさんは基本的にムードメイカーだし、ミュージシャンとしてもすごく器用な人なので、どんな変化にも対応するし、なんでもすぐできるんですよ。その姿勢が今回のアルバムで変わったみたいなんです。いつもオン/オフがないくらい陽気なのに、レコーディング中に突然黙り込んだときがあって。〈なんか怒らしたかな〉と不安になっていたら、どうやら〈今回のアルバムはこれまでのように雰囲気で弾いたらあかんな〉と思ったそうなんです。今作のレコーディングは一発録りだから、そのままの音が作品に残る。ずっと誇れる可能性もあるし、一生悔いが残る場合もある。だから、ちゃんと満足できる演奏をしたいと。ジュンジュンさんは、YeYe以上にこのアルバムが売れてほしいと考えてくれているみたいです」
――浜田さん以外のおふたりについては、いかがですか?
「成道さんに関しては、最初はNordが1つだったんですけど、スタジオに入るたびに機材が増えていきましたね。もはやなんの楽器から出ているのかわからん音を鳴らしてくれています(笑)。リッキーさんも〈これは基礎練習せなあかんわー〉と言い出したり。バンドになった当初は楽しいだけやったし、それでも3人のクォリティーは相当高いから、私は満足できていたんです。でも3人はずっと向上心を持って参加してくれていた。それに驚いたと共に、嬉しかったです」
――今作を聴いて、ギター・サウンドがすごく多彩なことにも驚いたんですよ。すごくノイジーな音もあれば、乾いた音も鳴っている。ギターはすべてYeYeさんが弾かれたんですか?
「私が全部弾いてます。でも本当に申し訳ないんですけど、楽器や機材には一切興味がなくて(笑)。とりあえず音が出たらいい……まあ自分なりの好みはありますけど、適当にこれくらいかなと音を出すんですよ。そうしたらリッキーさんが調整しにきてくれるんです(笑)。彼はギタリストでもあるので、ドラマー兼YeYeの専属ギター・ローディーみたいになっていて。私のギターから、最大限に気持ちの良い、風通しが良い音を引き出してくれています」
――前作からの変化を、歌詞にも感じました。英詞と日本語詞の割合が前作とほぼ逆で、今作は英語詞が多くなっていますね。
「いま言われて〈確かに!〉と思ったくらいで。どの言語であるかに関しては特に意識してなかったです」
――ただ、“Veronika”はリトアニア語ですよね? YeYeバンドで2014年の秋にリトアニア・ツアーをされていたし、その経験から出来た曲なのかなと思ったんですが。
「あの曲はそうですね。ヴェロニカという現地でコーディネートしてくれた女の子の名前。ツアーの最後に4人でストリート・ライヴをしていたときに突然出来た曲なんですけど。その子にリトアニア語で気持ちを伝えたいという想いがあった」
――リトアニア・ツアーも、当初はYeYeさん単体へのオファーだったようですが、〈いまのYeYeの音楽を伝えるには、いつもの最強サポート・メンバーなしには成り立たない!〉と、旅費を賄うためにクラウドファンディングを兼ねたライヴを行って、実際に4人編成での渡航を実現させていました。YeYeさんの言う〈パンク精神〉というのは、自分の工夫でやりたいことを叶えていくことなのかなと思うんです。そこで、今作を踏まえて、さらにどんな活動をしていこうと考えていますか?
「そうですね。今回のアルバムで〈YeYeはフワフワしてないぞ〉というのを、みんなに認知してもらいたいし、その土壌を固めたうえで、もっとバンド・サウンドを重視したアルバムをもう一枚出そうと思っています。そのあとは、そうですね……お母さんになりたいな。自分のなかでは、人生の行事と音楽の行事は全部同じ部類に入っているんです。アルバム出す、結婚する、子供を生む、次のアルバム出す、みたいな。だから、ずっと活動していきたいし、死ぬ直前がいちばん売れているミュージシャンになりたい。私は〈いますぐに〉と急いではないんですよね」