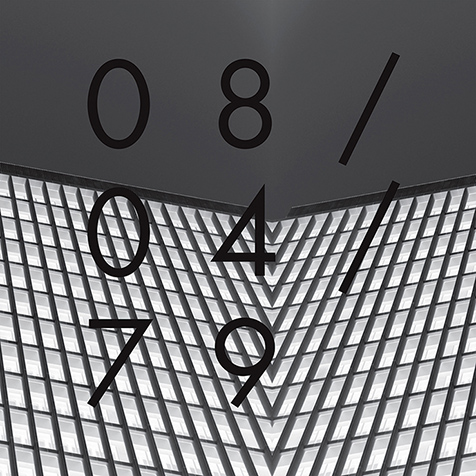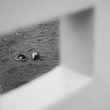〈みんなが使いやすいアプリ〉みたいなバンド
――『超ライブ』と似たことをやろうとしていたんじゃないかと思える他の作品はありますか?
高橋「自分たちに課していた責任感と、その結果鳴らされたサウンドは全然違うと思いますけど、Hi-STANDARDの『MAKING THE ROAD』(99年)ですかね。あの当時に彼らが作らなければならなかったサウンドの広がり方は、僕らと次元は全然違うけど、同じような気持ちだったんじゃないかな」
藤原「おもしろいなあ(笑)。元希くんってフジロッ久(仮)の現状をそう捉えているんだ。僕はコンセプトを感じるアルバムが好きなんですけど、そういう意味ではピチカート・ファイヴの『さ・え・ら ジャポン』(2001年)は近いかもしれないですね。今日は真面目な話をしていますけど、フジロッ久(仮)のもう一つの側面の、聴いた人が〈はぁ?〉となるような謎の展開や、笑えるところとかがベタに感動するものと平然と同居して、超大作としか言いようのないものにまとまっている感じが似ているかなと思います。ジャケが〈そう来たか!〉というところにもシンパシーを感じるな。もうひとつ言うと、〈ひふみよ〉ツアー(2010年)での小沢健二のライヴは、このアルバムでやっていることと近いような印象です」

――それも興味深いですね。
藤原「照明が真っ暗な状態から始まる演出だったり、幕間に朗読があったり、そういうことも含めたあのライヴでの体験と、このアルバムを聴くことは似ていると思います。僕はオザケンは、完全に〈ひふみよ〉ツアー以降にハマったリスナーで、それまでは好きな曲が4曲くらいあるという程度の認識だったんですけど、あのツアーでの、過去の音楽と超社会的な詩の朗読というやり方がすごく衝撃的だったんです。さっきも言った〈ラヴソングとパンク・ソングを両立させる〉ことにも通じるんですけど、MCが土台にあることで、その後で歌われる深みを持ったラヴソングが私的であるまま社会的にも響く、というオザケンのライヴを体験して、〈こういうことができるんだ!〉と思った。だから、それは僕らが〈発明〉したというより、そのときオザケンを観て〈発見〉したことだったんですよ。もしも小沢健二が〈ひふみよ〉ツアーのコンセプトでオリジナル・アルバムを作っていたとしたら?と妄想したことがあって、『超ライブ』にはそういったものを自分が作るんだという気概もあった」
――今年の〈魔法的〉ツアーは観に行きました?
藤原「はい。この間のツアーで聴いた新曲では、小沢健二は想像のもっと先に行ってました」
――いま3人になったフジロッ久(仮)ですけど、今後どうなりたいかについては、自分たちもまだはっきりとは見えていない?
藤原「そうですね。DVDを観たらわかるんですけど、あれも現場ごとにすべてが違うツアーでしたし、僕らはある種行き当たりばったりなので。でも、そのなかで出会う人だったり、イヴェントだったり、価値観だったり、そういうものに常に影響を受ける形で、その日ごとにフジロッ久(仮)を作っていくというか。『超ライブ』も、僕は20人くらいで作るくらいのつもりで最初から曲を作っていたから」
高橋「コンセプトもすごく大事にしてるんですけど、コンセプトにフィジカルを近付けていくというよりは、自分たちが見たり経験したりしてきたこととしてのフィジカルがあって、そこからコンセプトが見えてきて両方が共に完成に至るというイメージなんです。僕の場合も、自分が見てきた景色や体験してきたことから生まれる気持ちが、藤原が出してくる曲なりメロディーに沿っていく。そこはもうばっちりなんですよ」
藤原「そのとおりなんです! いまみたいに、元希くんがフジロッ久(仮)のことを僕よりもわかりやすく人に説明できていることが多々あるんです。僕より一歩深いところまで踏み込んで状況を捉えているし、音楽的にも僕がしようとしたことを100%わかっている感じがするんですよね。こういうところまで踏み込みたいけど、俺の表現だとどうしてもこういう言い方しかできない、みたいな部分に、元希くんの言葉があることで、そこに届いた!と思えることもあったり。こういうスタンスのツイン・ヴォーカルのバンドってあんまりないですよね。そもそも、僕らはツイン・ヴォーカルなんですかね(笑)?」
――フジロッ久(仮)の2人を〈ツイン・ヴォーカル〉と言っていいのか問題(笑)。
高橋「そもそも僕の肩書きは〈パッションモンスター〉なんで(笑)」
藤原「僕の場合、先に作りたいものがあって、それをいまいる人たちでどうやればいいか、そのために呼ぶべき必要なミュージシャンは誰か、みたいな考えになっていくんです。そういう意味では、今後はしばらくメンバーを固定せず、3人+誰か、という編成でいろいろと試せるのはおもしろそうだなと思います。そのなかで、僕と元希くんが意思疎通できていれば舵は取れる。だから、立場としては2人で監督みたいな?」
高橋「2人であることって大事だと思うんですよ。どんなに強い人が引っ張っていてもワンマン・バンドって絶対に限界が来ると思うし。フジロッ久(仮)のいいところは、僕が言うのもなんですけど、藤原がいて僕がいて、僕がいて藤原がいるというところだと思うんです。この2人でフジロッ久(仮)を引っ張っていって、フジロッ久(仮)が好きな人がついてきてくれたら続けていけると思うし、これからも曲をがんばって作りたい。僕にとってのフジロッ久(仮)は、自分が何よりも夢中になれる曲を作れるチームなので」
藤原「結局、音楽なんだよね」

高橋「バンドという形態に愛もあるんだけど、自分がいちばんいいなと思える、パンクでありラヴな曲を作れることが大事なんです」
藤原「僕の曲も元希くんは自分の曲のように乗りこなしますからね。演奏もそうです。勝手に自分のものとして乗りこなす人たちばかりなんで」
――それを言ったら、お客さんもそうじゃないですか?
藤原「そうなんです。〈みんなが使いやすいアプリ〉みたいな(笑)。フジロッ久(仮)の音楽は、それくらい私物化しやすいんだと思います。僕自身も、自分の曲を日常的によく口ずさむんですけど、そういうときは完全にリスナー感覚なんですよ。〈ここ好きだな~〉みたいな(笑)」
――流行歌が出来にくい時代に、無意識に人の口に乗りやすい曲が出来ることは貴重な力だと思いますよ。
藤原「再生ボタンを押さなくても自分で再生できて、都合良く好きな部分だけを繰り返して歌ったりできる。僕はそういう歌の力をすごく信じているし、憑りつかれている。だから〈今後、バンドがこうなりたい〉みたいな話は、僕にはできないんです。こういういい音楽を作り続けて、ちゃんと新しい領域にも踏み込んで、でも僕らが作った音楽をひとりひとりが勝手に持ち帰れるような感じでありたい」
――聴いてる人の数だけたくさんのフジロッ久(仮)がいると言えるんじゃないですか?
高橋「ひとつ視点を変えればいくらでも世界を豊かに捉えることができるというのが、僕らの基本的なテーマですから」
藤原「今年、アニメの曲(「宇宙パトロールルル子」のオープニング・テーマ“CRYまっくすド平日”)をやったじゃないですか。アニメを観てあの曲を気に入った人が、今後僕らのライヴに来たりすることがなくても、好きに歌って膨らませて、違う現場に持ち帰ることで、何かと繋がってほしいなと思っています」
高橋「望んだ変化じゃないですけど、アルバムを出すごとにメンバー・チェンジがあるんで、結果的に僕らは毎回ファースト・アルバムを作っている感じなんですよ。だから次も、すごくフレッシュなものを作らざるを得ないんです」
――アダム・サンドラーとドリュー・バリモアが主演した映画「50回目のファースト・キス」(2004年)が、まさにそれですよ(笑)。事故に遭った彼女が1日ごとに記憶を全部忘れちゃうから、毎日〈愛してるよ〉と言って恋に落ちさせなきゃいけないというストーリーで。でも、そういうことは別の視点では幸せでもある。新しいリリースがあるたびに、またフジロッ久(仮)に恋できるわけだから。
藤原「自分でそのくらいまで思えないと〈出来た!〉と思っちゃいけないルールが僕にはあるんで。次に〈出ました!〉ってなったときも、そういうものになっていると思います」
――つくづく、真っ直ぐでも回り道でも、それがフジロッ久(仮)の道ですしね。
藤原「そうですね。結局僕らはそれを全部回収して音楽にしていく気がします。だから、メンバーが抜けたりしたことも全部、この先音楽の糧になるんだろうと思うんですよね。それを原動力に、作品として成功したのが『超ライブ』なんで、これからもいろんな体験が音楽に反映されるんだろうなと、いますごくワクワクしています」
高橋「次がどうなるにしても、これまでのライヴを通じて、僕らの心臓はがっちり出来たと思う。そういう意味では『超ライブ』から続いていく物語というのもフジロッ久(仮)の基本になる。それくらいの自信作だし、この先のスタンダードになるものが出来たなと思います。でも、ここからまた〈めちゃくちゃ変わったな!〉と思われるものが出来てもおもしろいですけどね」
藤原「〈フジロッ久(仮)は何がしたいんだ?〉ってね(笑)」