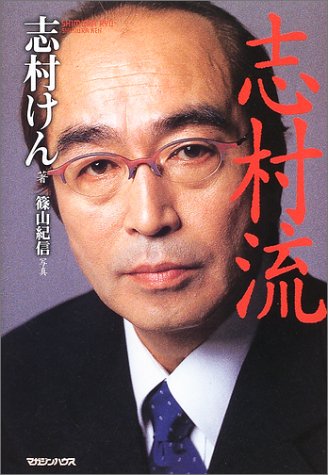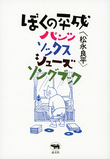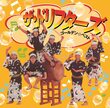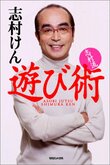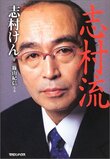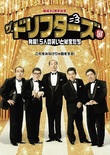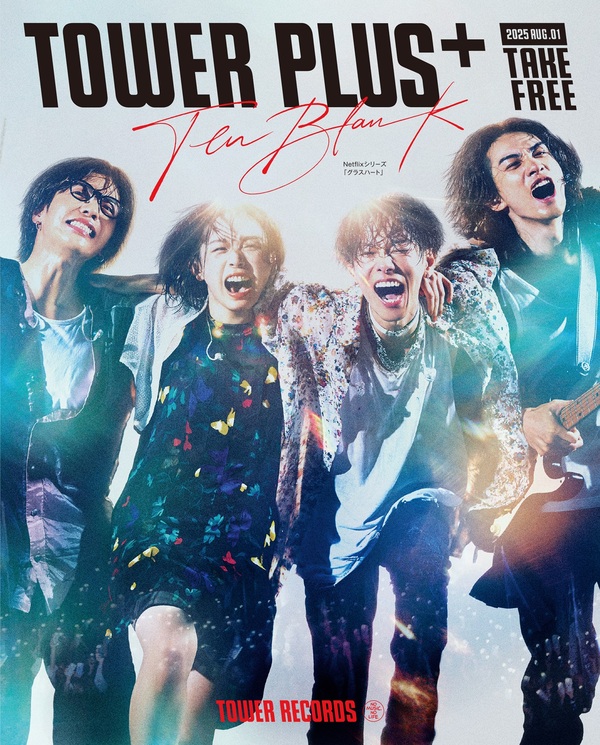その後のドリフ=志村路線のヒット・コントだった〈早口ことば〉がシュガーヒル・ギャングからアイデアを思いついたもので、バック・トラックが“Don’t Knock My Love”(ウィルソン・ピケット)だったことや、〈ヒゲダンス〉が“Do Me”(テディ・ペンダーグラス)だったこと、そのチョイスが志村さんだったことは、いまではもちろんよーく知られている。後年のソロ・ギャグである〈ヘンなおじさん〉が喜納昌吉&チャンプルーズの“ハイサイおじさん”を下敷きにしていたとか、「志村けんのバカ殿様」にラッツ&スターの田代まさしや桑野信義を抜擢したこともそう。1980年前後、あの多忙な時期に雑誌「JAM」にスティーヴィー・ワンダーやダニー・ハサウェイなどのブラック・ミュージックのアルバム・レビューを寄稿(しかも冷静な名文)していたという事実もそう。
とはいえ、当時小学生が大半だったドリフのファンはそんな背景はまったく知る由もなかったし、志村さんがそのことを強くアピールすることはいっさいなかった。ただただぼくらは、志村さんがドリフに持ち込んだリズムとソウルとダンスを、笑いを通じて毎週ひたすら浴びていただけだ。
おそらく、70年代後半に起きたサタデー・志村・フィーヴァーがなければ、ドリフの人気は「オレたちひょうきん族」の登場(81年)を待つまでもなく、もっと早くにシュリンクしていただろう。志村以前のドリフのエースはいうまでもなく加藤茶であり、いわゆるバンマスがいかりや長介。70年代前半の加藤さんの音楽的なヒット・ギャグといえば、エキゾチックなナンバー“タブー”に乗せて、ピンクの照明を浴びながらストリップ劇場の世界に視聴者を誘う〈ちょっとだけよ〉を思い出す。“タブー”は必ずしもストリップ界の定番じゃなかったかもしれないが、ドリフを通じて不可分な曲と認識されてしまった。エンディングの“ドリフのビバノン音頭”(デューク・エイセスが歌った“いい湯だな”の改作)にしても、リズムは当時としても古い時代のズンドコ・グルーヴだった(めちゃめちゃ愛されてはいたけど)。
志村けんは、そのズンドコをファンクに変えた。志村さんが〈全員集合〉に持ち込んだのは、70年代をリアルタイムで生きる青年がまとっていたファンキー・ソウルだったし、ダンスのアクションだった。“東村山一丁目”でのディスコ的な振り付けから出発して、80年代を迎えようとしていた〈ヒゲダンス〉では、より自由に踊れるムードを醸し出した。大人の社交場である〈クラブ〉ではなく、現代的なイントネーションの〈クラブ〉にもつながる空気感といってもいいだろう。子どもたちはそんな場所は知らなかったけど、それが新しいものかどうかはすぐに察知する。知らず知らずのうちに時代遅れになってしまいそうだったドリフを結果的に救ったのは、間違いなく志村けんだった。