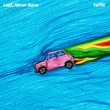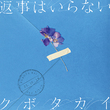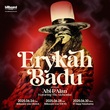音楽は言語によって変化していく
──そうしたテーマを肉付けしていく上で、インスパイアされた作品や出来事などありましたか?
「色々ありましたが、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の映画『メッセージ』の影響は大きかったと思います。映画もとても良かったのですが、テッド・チャンの原作『あなたの人生の物語』が好きなんですよ。肉付けという意味で、今ぱっと思い出すのはその作品ですかね」
──テッド・チャンの「あなたの人生の物語」は、宇宙人の言語を理解することで主人公の時間軸が〈更新〉され、それで未来を予見できるようになるストーリーでした。
「映画は映像になっている分、どうしてもSF色が強くなりがちですが、おっしゃるように小説はもっと観念的であり言語学的で。
僕もちょっと言語フェチなので(笑)、そこにも惹かれました。外国語の語感が好きなんですよね。意味が分からなくても、フランス語にはフランス語のグルーヴがあるし、イタリア語も中国語にもヒンドゥー語にも特有の響きがあるじゃないですか」
──確かに、例えば韓国語のラップを聴くと、英語にはないグルーヴやスピード感があるし、意味が分からないぶん音の響きがダイレクトに入ってきます。もしかしたら日本語も、海外では特有のグルーヴとして受け止められているかも知れないですね。
「それはめちゃくちゃあると思います。言語によって含まれる倍音も変わりますから、当然メロディーの動きも変わってくる。次に向かいたい音程の癖が、言語によってあると思っていて。
それに、メロディーだけでなくトラックにも影響を少なからず与えています。意識的に〈これは英語だから、こういうトラックにしよう〉とは思わないですけど、言葉や歌詞にはものすごく引っ張られる」
──ものすごく興味深い話です。
「ヒップホップの現場ではよくあることですが、トラックをラッパーに投げて、ラッパーがそこにラップを乗せてそのままリリースするという制作フローが僕は苦手なんですよ。トラックに声が乗った時点で、もう一度トラックに手を加えたくなる。逆にいえば、最初の段階で〈メロディーを乗せればもう完成です〉というところまでトラックを作り込むこともしたくないんです。
例えば今作も、まずは完成形の5パーセントくらいのラフなドラフトを作って、そこに歌を乗せてもらってからオケを作り込んでいくやり方をしているんですよね。場合によってはオケを全て消して、歌に合わせてイチから作り直すこともありますし」
──誤解を恐れずに言えば、〈歌〉も素材として考えているというか、トラックと等価で考えているからこそ、そういう作り方をしているのでしょうね。
「確かに、〈オケと歌〉みたいに二層化して考えてはいないと思います。
これは余談ですけど、例えば楽曲提供のお仕事をもらったときに、〈カラオケ・ヴァージョンを作る際、声はどこまで消せばいいですか?〉とよく言われるんですよ。僕の曲の場合、メインのヴォーカルを消しても、声っぽいフレーズがめちゃくちゃ入っているので、それも全部消してカラオケにしちゃうとスカスカになってしまう。
おっしゃるように、どこからが〈声〉でどこからが楽曲の〈フレーズ〉なのか、その境界線は曖昧かも知れないです」
神秘的な残響と立体的な音像
──今の話で思い出したのですが、今回のアルバムはゴスペルっぽいと思う瞬間が結構あって。トラックの中で〈声〉の要素がふんだんに盛り込まれているからなのかなと思ったんですが。
「なるほど。実は僕、ユルユルのキリスト教徒ではあるんですよ。幼稚園から高校までクリスチャン系の学校だったので礼拝もしたし、母親もユルユルのキリスト教徒なので、キリスト教的世界観の方が、仏教的世界観よりもシンパシーはありますね。
当然、ゴスペルにも馴染みがあります。音像的にも教会のような、広い空間で声が多声でワーッと鳴り響いているものは親しみがある。〈残響〉にはすごく聖なるものを感じるし、神秘性を感じますよね。逆に近い音像にはパーソナルなものを感じる。
ただ、テクニカルな話でいうと、聴き手がすごく近くに感じられる音像の方が個人的には好きなんです。それを活かすために、あえて広い空間を作ることはありますね。
例えば、J-Popのいわゆる〈落ちサビ〉ってあるじゃないですか。サビの最後でピアノだけになる、みたいな。ああいうところでリヴァーブやエコーをかけてワーッと広げる演出よりは、逆に歌をバキっとセンターで出したくなる。それを強調するために、前後の音像を広く作っておくとか、そういう極端な立体感を演出することはよくあります」
〈ローファイにどう向き合うか?〉という課題
──極端な距離感によって音像に立体感を出すという意味では、“You Come Undone”は歪んだ音を入れることで、逆にクリアな音の透明感を際立たせるような手法を取っていると思いました。
「音楽の機材の値段がここ数十年で下がったじゃないですか。今はスマホがあれば誰でも録音ができる時代で、昔よりもローファイが普及したと思うんですよね。とんでもない素人が、とんでもない音源を作るみたいなケースもよくあるし。
そうなったときに、今度は〈ローファイに対してどう向き合うか?〉という問題が出てきた。いいスタジオでいい機材を使った、オーディオ的に正しいだけの、ただハイファイなサウンドって逆にダサく感じるようになりましたよね。トラップとかの隆盛もその流れで捉えることも出来ると思うのですが」
──よく分かります。
「逆に、安価なスピーカーから聴こえてくるだけでカッコよく聴こえてしまうから、ただローファイなだけだとそれはそれで〈逃げ〉だとも思うんです。そうなると、いわゆるクリアな音と、汚れた音とのバランスをどうするか、どう対比させていくかが重要になってくると思うんですよね。
“You Come Undone”は、そういう意味ではちょっと実験的な要素もあったと思います」