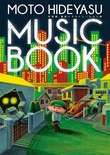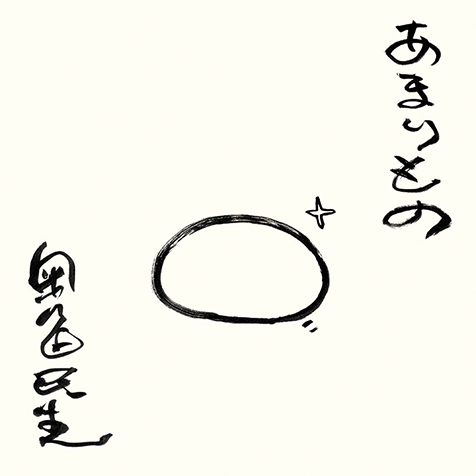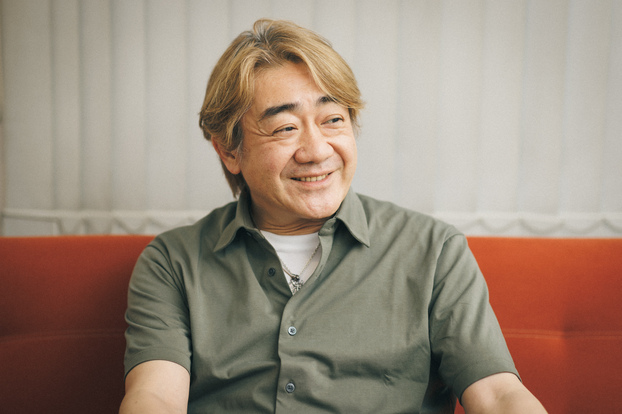
TV出演も楽曲制作もワンセット
――結成の経緯、すごく深いお話でした。僕がお訊きしたかったのは、アイドルとしての忙しい活動と、本格的なロックバンドとしてのスタジオでの制作は、みなさんの意識の上で切り離されていたのでは?ということなんです。例えば、“LOVE AGAIN”(84年作『Good Vibrations』収録曲)は〈味の素 マリーナ〉のCMソングですが、あれってロックバンドの域を超えて、もはや職業作家の仕事だと思うんです。僕は『FIFTH DIMENSION』(86年)の頃にロックバンドとして覚醒したのかと思っていたのですが、それは間違いで、当初からアイドルとロックミュージシャンとしての側面が切り離されていたのかなと。
曾我「う~ん。そもそも、あんまり自分たちをアイドルとは思ってなくて。当初からスタジオでレコーディングをやらせてもらってたので、もう意識がそっち(楽曲制作)に行ってたんですね。
逆に、あの頃はロックバンドの体で出てきた人たちが、自分たちで曲を作らず、プロの作家さんが用意した曲を演奏するばっかりでした。なので、僕らの外からの見られ方と、実際にやってることのギャップに対する〈何でだよ!?〉というジレンマはありましたね。ロックバンドと言われている人たちのほうが、ロックバンドのふりをしたアイドルじゃないかって」
――そうですよね。The Good-Byeは、TVや雑誌でアイドルとしての仕事をこなしながら、よくあれだけのクォリティーの曲を作ってレコーディングしてたなと。大変なことだと思います。
曾我「ほんとにね(笑)。TVの収録が終ったら、そのまま朝までレコーディングして、車で録った音を聴きながら別の曲を書いて、昼に起きたらTV局に行って、という生活をずっと続けてましたからね。〈自分の曲がレコードになる〉という思いだけで、必死で作っていました」
野村「〈アイドル〉というのは、周りから見たイメージじゃないかな? TVや雑誌でピースしてニコっとする、そういう仕事も楽しんでこなしながら曲を作ってレコーディングをする――全部がワンセットで当たり前の日々だったんですね。大変だとも思わなかったな。若いからできたんだけどね」
――同時期に活動していたロックミュージシャンと仕事量が違うわけですが、フラストレーションはなかったんですか?
野村「ない。だって、他のミュージシャンのことを知らないからね」
曾我「ただ、僕は事務所に掛け合って、当時出てきていたロック系雑誌の取材を取ってきてほしいとお願いしてましたね」
――曾我さんは〈ロックバンドとして見られたい〉と思っていたんですね。
曾我「僕は強く思ってましたね。『ミュートマジャパン(ミュージックトマトJAPAN)』というTVKの番組で紹介されるバンドの人気が出ていたので、出演を掛け合ったこともありました。なかなかわかってもらえなかった、という思いは抱えてましたね」

奇跡的なバランスのバンド
――初期のシングルは歌謡曲としての完成度が高いので、僕はロックバンドとしての魅力に気づけなかったんですよ。その後リリースされた『FIFTH DIMENSION』があからさまにロックで。あまりのギャップに驚きました!
曾我「売上はドーンと落ちたけどね(笑)。
当時はアイドルや歌謡曲とロックがかけ離れてた時代で、真ん中にいる僕らはコウモリ状態だったんです。とはいえ、TVに出てシングルも出さなきゃいけなかった。でも、B面やアルバム曲は好きにやらせてもらえたんです。だから、好きにやってきたものが、今こうやって評価してもらえてるのかなって思いますね」
――それこそが、いま素晴らしい音楽だと再評価される理由の一つでしょうね。
曾我「The Good-Byeは、ぱっつぁん(加賀)、浩一を含めて、良い意味でジャニーズ系じゃない4人が揃っていたから、それも奇跡的なバランスだったと思います。全員アイドルチックな4人組だったら、こうもいかなかったかも。
さらに、川原さんと出会えて、曲作りやレコーディングを教わって、僕らがどんどん音楽的に成長していけた」
――ある意味、川原さんにハメられたとも言えますね(笑)。
曾我「(笑)。川原さんが、メンバーが作曲すること、それを作品にすることに強くこだわってくださったからこそだと思います。
ジャニーズの子たちが好き勝手に曲を作って本格的な音楽をやってるギャップも大きかったと思いますが、もし〈ジャニーズ〉〈アイドル〉という側面や振り幅がなかったら、普通のバンドになってたかもね」
――曾我さんの葛藤も、いま振り返れば、評価される良いポイントだったと思います。
曾我「当たり前のように1日2回、3回公演をやってましたからね。なので、事務所に〈1回公演にしてほしい〉〈こういうステージでやりたい〉という交渉もしました。アーティスティックに見られたいという思いがあったので、舞台の演出も考えていましたね」