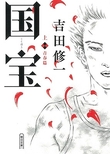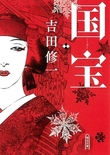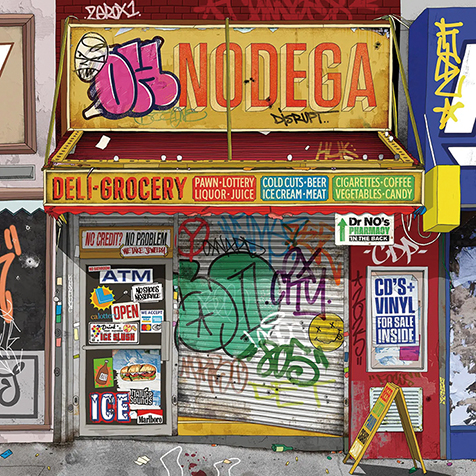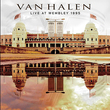任侠の一門に生まれながらも、歌舞伎役者としてのちに国宝に――圧倒される美しさ、歴史に残る壮大な芸道映画
吉田修一の小説「国宝」は、出版された直後から、周囲の歌舞伎好きの間で話題となった小説だった。小説家本人が黒衣の姿に身をやつして舞台の裏事情までをも体験取材し、描ききった世界は非常に説得力があり、〈語られず、察することで芸道が成立する〉というある意味敷居の高い日本の伝統芸の中でも、最大級のエンターテイメントである歌舞伎の世界をより深く理解するよすがとなった。
この小説は映画になるかどうか?!というのは、当時、カルチャー好き友人との飲み屋のネタであり、「国宝」についてはナシという人とアリという人に真っ二つに割れた。前者のナシ派の意見は、芸術をテーマにした映画とは、常にジャンルの〈目利き〉に試されるという宿命(映画内で演じられる〈至高の芸〉は、どうがんばっても本物に到達は不可能)があるわけで、歌舞伎という世襲の人間が幼いときからそれ一筋を追求してきた芸を、国宝級の演技で見せるのは俳優ではムリ、というもの。しかし、私は後者のアリ派を主張したものだった。なぜならば、昨今の芸術テーマの話題作は表現以外の物語要素から、テーマに肉薄するという手法をとって成功を収めているからだ。
たとえば、「TAR/ター」では、クラシック業界の宿痾である構造的問題や権力の乱用、そして業界の生き残り策までをも、女性指揮者のブロとしてのリアルを軸に描いて見応えがあったし、精神の崩壊と肉体鍛錬ありきの創造のせめぎ合いをバレエのプリマを軸にサイコスリラー仕立てとした「ブラックスワン」方式もある。原作の「国宝」は群像劇としても捉えることができ、舞台以外の物語が豊かなので、こちらの方向で落ち着かせるのかな?かと思いきや、かなりの時間を、歌舞伎の舞台シーンに費やしており、その結果なのか、上映時間は約3時間。私が主張したアリ派でも、友人のナシ派の主張でもない新たな映画表現が立ち現れることになったのである。

それを可能にしたのは、役者の演技力につきる。特に主演の吉沢亮! 彼はこの役を演じるに当たって、1年以上の稽古を重ねたというが、日本舞踊の特徴である中腰やすり足で〈地の重力を内包する〉ような動きや女形独特の発声方法を見事に習得。監督に「生まれながらの歌舞伎俳優に見えるように指導してほしい」と言われたのは、振り付けと舞踊指導にあたった流派に所属しない舞踊家として活動を続ける谷口裕和。所作や型をなぞるものではなく、身体をゼロから〈女形〉へと鍛え直す、いわば芸術的身体改造の到達点は、役者によっては全く未知のもの。そこにきっちりと時間とコストをかけた監督の〈賭け〉は見事に成功したといっていい。主人公のライバルである御曹司役の横浜流星は、NHK大河ドラマの主役でもあり、今一番多忙を極める状態にも拘わらず、この難役に挑戦したその役者魂はあっぱれの一言だ。