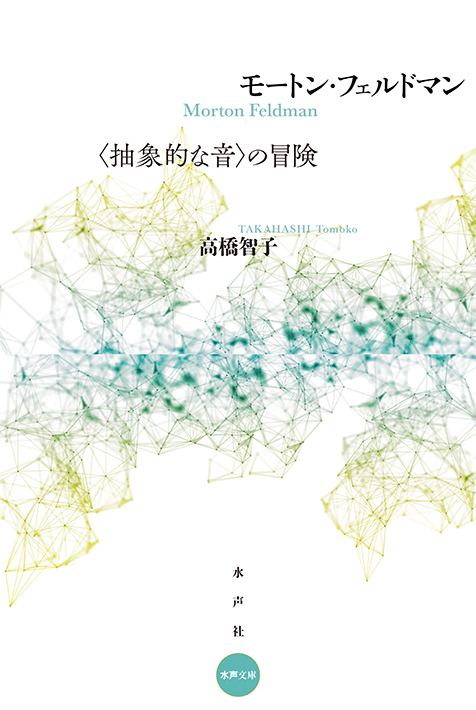耳のためのカメラを置いたケージ、耳のためのキャンバスを置いたフェルドマン
どうやってこの音楽が始まったのか思い出せないどころか、いまどのあたりまで進んだのか、そして果たして終わるのかがわからない。フランツ・カフカの「アメリカ」の冒頭に出てくる客船の外観以上に巨大な内部に迷う主人公のような気分を味わったのが、モートン・フェルドマンの4時間にも及ぶ、PCに取り込んだ4枚組のCD 『フィリップ・ガストンのために』だった。本人曰く「四時間だなんて感じませんよ!」、つまり作曲家本人でさえ完全に時間の感覚を失う。
この奇妙な音楽を書いたモートン・フェルドマンの、日本では初めての評伝「モートン・フェルドマン 〈抽象的な音〉の冒険」が出版された。これまで日本で紹介されてきた欧米の現代音楽史では、フェルドマンはもっぱら〈図形楽譜の発明者〉として紹介されてきた。同時代の作曲家であり、彼の仲間だったジョン・ケージに比べると、庄野進の「聴取の詩学」を中心にいくつかが散見される程度だった。高橋アキというフェルドマンにとって何者にも代え難い演奏家がいるというのに。しかし言語化が進まないこと、彼の音楽を捉える言葉が見つからないことこそが、フェルドマンの音楽の在り様であることも確かだ。
本書では、時代順にフェルドマンのあの音楽が書かれた環境から掬い上げては再び沈めていくー不確定な音楽の中から、抽象表現主義者の絵画の直接性の中に、絵画に現れる光とベケットの影の中へと。そしてその作業の繰り返しの中からフェルドマネスクが異化されて、浮かび上がってくる。図形楽譜によってサウンドを慣習的な書法(記憶)から解放し、音それ自体を減衰していく音に求める。それはアタックからサウンドを解放しその過程として持続時間を重視することに繋がり、音楽はいっそう静かに、長くなっていく彼の音楽が誕生し、生成する過程が浮かび上がる。フェルドマンの音楽を聴くこと、彼の言葉を読むこと、彼について書かれたものを読むこと、彼の音楽を育んだ知的、文化的状況に介入すること、モートン・フェルドマンを編集することを介し、歪なシンメトリーの静寂が持続する、あのサウンドの表皮が言語化されていく。そしてたとえば、〈ゆるやかな曲線を想起させる音の動き〉と著者が記す後期図形楽譜のサウンドは、弦楽の中に曲線を置いたクセナキストとの繋がりを、この言葉を介してそのイメージを広げ、フェルドマンが図形楽譜の人という記憶から解放していく。耳のためのカメラを置いたケージ、耳のためのキャンバスを置いたフェルドマン。フェルドマンの音楽が読めることの価値は計り知れないと思う。