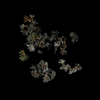英インディー・シーンに新たな台風の目が現る! 静寂と轟音を自在に操る4ピース、デスクラッシュのサウンドに聴こえるUKロックのネクストな潮流とは?
ブラック・ミディやスクイッドと並ぶ英国の新たな世代に属しながら、いわゆる〈ポスト・パンク〉とは明らかに異質なサウンドのフォルム。強いて言うなら〈ポスト・ロック〉や〈スロウコア〉とひとまずず括れそうなスタイルで、フォーキーなテイストを色濃く湛えた力強くコントラストの効いたバンド・アンサンブルを特徴としている――そんなロンドンの4人組、デスクラッシュは、あのブラック・カントリー・ニュー・ロードに音楽的な方向性を与えたグループとしても知られている。
「バンドを始めるにあたっては、コデインやデヴィッド・パホ(スリント)、ダスター、初期のモグワイ、スパークルホースにとても影響を受けた。ヴォーカリストとしてはパフューム・ジーニアスにも。僕とパトリック(・フィッツジェラルド、ベース)はフェイマスとソーリーに一時期在籍していて、そこからも多くのことを学んだんだ」(ティエナン・バンクス、ギター/ヴォーカル)。
2016年にケンブリッジ大学の学生によって結成されたあと、メンバーの変更もありながらウィンドミルでライヴを重ねるなど徐々に頭角を現していったデスクラッシュ。そして数枚のシングルを経て、シーンを代表するプロデューサーのダン・キャリーも〈奇妙でダークなパートナー〉とその存在に一目置くようになった彼らの評価を決定付けたのが、昨年リリースされたデビュー・アルバム『Return』だった。
ライヴ・レコーディングによる生々しい音響とプロダクションのなか、〈ラウド・クワイエット・ラウド〉のマナーに倣い静寂と不協和音を操るダイナミックな4人の合奏。ディストーションが効いたギターと太い残響音を持つドローン風のベースが絡み合い、怒号のようなドゥーム・メタルと内省的なフォークの間を行き来するようにして奥行きのあるサウンドスケープが形作られていく。そして、そんな彼らの音楽のトーンを印象付けるのが、痛みや苦悩、寂寥感について赤裸々な言葉で歌うティエナンの親密でエモーショナルなヴォーカルだ。
「重要なのは、歌詞が自分自身にとって誠実かつ本物であること。ある言葉やメロディーを長く心に留めておくと、それが自分にとって表現する価値があるものかどうかが明確になっていく」(ティエナン)。
そうしたデスクラッシュの魅力は、このたびリリースされたセカンド・アルバム『Less』でさらなる大きな深化を見せている。タイトルが示す通りミニマルな音作りが心がけられ、引き続きライヴ録音ながら、きめ細やかな演奏のアレンジやヴォーカルの繊細なニュアンスを堪能できるのが今作の醍醐味だ。

全体的にメロウでソング・オリエンテッドな側面が際立つ一方、荒削りな“Turn”や重厚なベースを轟かせる“Duffy's”、緊張と解放が押し寄せる“Dead, Crashed”など、本領である起伏に富んだ音のダイナミズムは損なわれていない。なかでも“Empty Heavy”は、ティエナンいわく「アルバムのあらゆる側面を3分でほぼ完璧に表現している」というナンバー。そしてアルバム全体のテーマについてはこう話す。
「他者に寄り添うことの難しさ、他者を失うことの苦しみ、そして失ったことで初めてわかる悲しむべきこと」(ティエナン)。
ちなみに、パトリックは今作について〈Slow-mo(スロウコア+エモ〉と形容している。ちょっとしたジョークのつもりだそうだが、しかしなるほど、今作の性格をキャッチーに言い表しているように思えておもしろい。
「バンド内で〈このアルバムは僕らのエモ・アルバムだ〉とよく笑っていたけど、エモのファンはおそらくその説明にはほとんど同意しないだろうと思う。でもティエナンがキャッチーなメロディーを書いてくれて、それがテイキング・バック・サンデーのようなサウンドに聴こえたので、〈Slow-mo〉って思いついたんだ」(パトリック)。
デスクラッシュの2022年作『Return』(Untitled)
メンバーが在籍したバンドの作品を一部紹介。
左から、フェイマスのEPをカップリングした2022年の編集盤『The Valley/England』(Untitled)、ソーリーの2022年作『Anywhere But Here』(Domino)