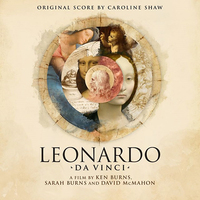天才ダ・ヴィンチに挑む。キャロライン・ショウ、充実の映画音楽
すっかりアメリカの作曲家新世代の顔となったキャロライン・ショウ。新作は、ケン・バーンズ監督による映画「レオナルド・ダ・ヴィンチ」のためのオリジナルスコアだ。
アタッカ・カルテット、ソー・パーカッション、ルームフル・オブ・ティース。キャロラインと共に、アメリカ東海岸のクラシック音楽シーンを盛り上げてきた実力派たちが一堂に揃う。そこへ、ジャズ・ベースの往年の名手ジョン・パティトゥッチも低音を支える。さらには、和太鼓も聴こえる。その響きが尊重されていることに気づく。
一聴すれば、ダ・ヴィンチ存命当時のルネサンス音楽のアカデミックな再現ではないが、まだ未解明な点の多い天才の創造の謎を、キャロラインの筆の力で補うアプローチと言える。
ミニマル・ミュージックを起点として、多様な実験を重ねてきた演奏家たちの演奏は、いつもながら力強さと躍動感がある。弦の響きは溌剌とし、コーラスはワイドなレンジをうまく使用し、透明度の高いアレンジが施されている。そこに注意深く選ばれた打楽器の音色が小気味よく加わる。
こうして、あくまでも自然にスケールの大きい編成は混じりあう。キャロライン作品の特徴である、鮮明な弦のアルペジオ、明るい色調のコーラスと、また今作で再会する。それらが再構成されているのを発見するのも、愉しい作業だろう。
ケン・バーンズはドキュメンタリー映画の大家だ。日本の音楽ファンにはジャズ史のドキュメンタリーでも有名だろう。彼は音楽的なディテールも作品内で尊重する監督だが、全体をオリジナルスコアで構成するのは今回初めての試みとなる。音楽面を信頼し、視聴覚のコラボレーションが行われたことは、想像に難くない。
ダ・ヴィンチによる手書きのスケッチや方程式、解剖学的な図版、機械設計図、「モナ・リザ」などの名画がふんだんに使用された映像に、どう音楽が絡むのか。日本ではまだ未公開の映画を想像しつつ、まず本作を手に取ってみよう。