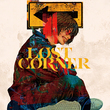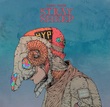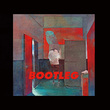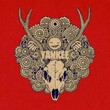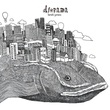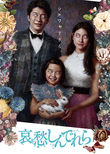現代J-POPを背負う音楽家の驚異的な創作意欲
2025年も四半期が終わり、この3か月間だけでも国内外の音楽シーンで多くの優れた曲やアルバムが届けられたが、とりわけインパクトが大きかったのは米津玄師の2つの新曲だろう。1月20日に配信された“Plazma”と1月27日の“BOW AND ARROW”だ。“Plazma”はBillboard JAPAN Hot 100にて初登場で首位を獲得。直近の4月9日公開のチャートでも“BOW AND ARROW”は9位、“Plazma”は25位で、いずれもアニメのタイアップやミュージックビデオの公開などにより現在に至るまで話題が持続している。
そもそも米津は、2024年8月に20曲も収録した大作『LOST CORNER』を発表、11月には新曲“Azalea”もリリースしたばかり。今年1月9日から2月27日にはツアー〈米津玄師 2025 TOUR / JUNK〉を開催、さらに3月8日から4月6日にはアジアと欧米で〈KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK〉もおこなった。もちろん新曲の制作はそれ以前におこなわれていたのだろうが、そんななかで休みなく作品をリリースするワーカホリックぶりと驚異的な創作意欲には圧倒されるほかない。今回は、そんな名実ともに現代日本のポップミュージックを代表する存在であり、世界的に見ても稀な音楽家の最新の2曲を深掘りしてみよう。
「鶴巻ガンダム」主題歌への並々ならぬ熱意
“Plazma”はアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)」の主題歌として書き下ろされた曲で、1月17日に劇場で先行公開された「機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)-Beginning-」でも大きくフィーチャーされた。満を持して本日4月9日に放送が始まったばかりのテレビアニメでも、もちろん主題歌として本編を飾っている。
タイアップ作品を深く理解し、コアに踏み込んだ解釈をもとに曲を作り上げ、作品の魅力を引き立て、作品のファンも米津のリスナーも毎回驚かせる近年の米津の創作姿勢は、タイアップソングの王者・覇者として高い評価を得ている。“Plazma”についても、スタジオカラーとサンライズが「機動戦士ガンダム」の新作を作るという企画にまず興奮し、また自身が多大な影響を受けた「フリクリ」の鶴巻和哉が監督するとあって、「ジークアクス」という作品にかなり入れ込んで制作したようだ(「フリクリ」については「特にリッケンバッカーを振り回すハル子のキャラクター像は、自分がボカロ曲を作るうえでの土台の1つになっていたと思う。人格形成の大きな礎の1つになっているんじゃないかなという気はします」とまで語っている)。「ガンダム」シリーズへの情熱もあいまって、思いを込めて作曲したことは、「ZIP!」や音楽ナタリーのインタビューでも語られていた。
性急なテンポとボカロ曲的なピアノ
そんな“Plazma”を特徴づけている音楽的な要素は、まず性急な印象を強調するBPM 173という速いテンポ。ビートはキック&スネアのパターンがシンプルに〈ズンタッズンタッ〉と4分の4拍子で刻まれ、時折挿入されるジャージークラブの3連符キックがアクセントになっている。Aメロなどではドラムンベース風のブレイクビートも背景で鳴らされており、様々な音の抜き差しがなされているものの、常に走りつづけているかのようなスピード感が一貫して表現されている。ビートだけでなく細かく切り刻まれたボーカルのサンプルや、スタッカートやシンコペーションを駆使した音価の短い電子音の配置も、その印象を増幅。加えて和声はシンプルでありつつ、マイナー調だが湿っぽくなく、サビでの転調で展開を聴かせる鮮やかさにも加速感がある。
もう一つの大きな特徴は、多くの聴き手がすでに指摘しているとおり、リリースカットピアノの響きだろう。ボーカロイドの曲で一般化・浸透し、YOASOBIのAyaseが多用することによってJ-POPの定番のフォーミュラにまで至ったと言えるリリースカットピアノの特徴的な音色は、今や珍しいものではなくなった。改めて説明しておくと、ピアノの音が鳴り始めた(アタック)あとの余韻の部分(リリース)をDAW上で機械的にバサッと切り落としたものがリリースカットピアノである(ちなみにAyaseはボカロPとして活動を始めた当初、知識や技術がなかったため、リリースを手作業でカットしていたという)。普通、鍵盤を指で押して離せば、音は消えるまで漸減していくわけで、そこをぶつ切りにするリリースカットピアノは基本的に生楽器で出せない人工的な響きを持っている。だからこそ、ボカロという人工的な歌との相性が抜群なのだろう。