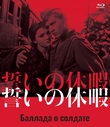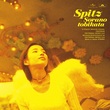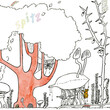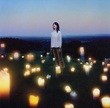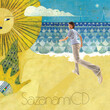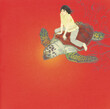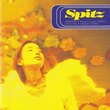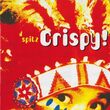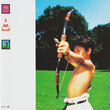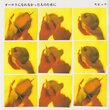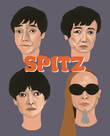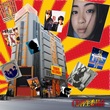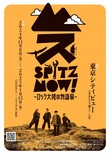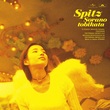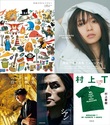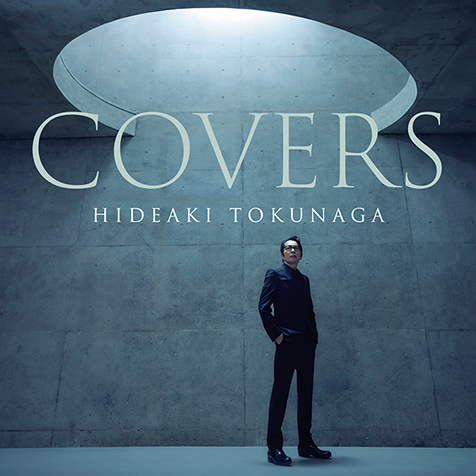1995年9月20日にリリースされたスピッツのアルバム『ハチミツ』。“ロビンソン”“涙がキラリ☆”“愛のことば”といった名曲を収録し、大ヒットしたバンドの転機作にしてファンの間で愛される名盤だ。そんな本作の30周年記念盤『ハチミツ 30th Anniversary Edition』がリリースされた。そこで今回は「スピッツ論 「分裂」するポップ・ミュージック」の著者である批評家・伏見瞬に、本作を論じてもらった。 *Mikiki編集部
“愛のことば”の〈昔あった国の映画で 一度観たような道〉とは
悪魔がはびこる殺伐とした世界の中で、チェンソーの悪魔と合体した少年が活躍するマンガ「チェンソーマン」。その劇場版アニメーション「チェンソーマン レゼ篇」の冒頭近く、主人公デンジと彼が恋している上司(という関係だけではないのですが説明が煩雑なので簡略化します)マキマの二人で、一緒に一日中映画をハシゴして観る場面があります。周りの観客が笑ったり泣いたりする映画に対して退屈していたデンジが、その日の最後に観る映画のワンシーンでふと涙を流す。泣いたことを恥じるデンジが隣を覗くと、マキマの瞳も同じように濡れている。このとき二人が観ている、スカーフを被った中年の女性が若者を抱擁するシーンを有する映画は、ソビエト連邦で1959年に作られた「誓いの休暇」がモデルではないかと言われています。戦地から休暇で故郷に戻ろうとする少年兵が道中様々な困難に遭遇し、女の子との出会いと別れを経験しながら、束の間母親に会ってまた戦地へ戻っていく。そんな物語を持つ映画です。
宮崎駿がフェイバリットに挙げていることでも知られる(ボーイ・ミーツ・ガール的な展開がたしかに彼の映画を想起させる)「誓いの休暇」は、スピッツとも関係しています。2000年に発表された“甘い手”という曲の間奏でサンプリングされている外国語の会話は、この映画から取られたものです。それだけではない。1995年のアルバム『ハチミツ』に収録された“愛のことば”の一節、〈昔あった国の映画で 一度観たような道を行く〉にある〈映画〉は、1995年の時点ではもう存在しないソビエト連邦で作られた「誓いの休暇」のことではないか。
はっきりとした証拠があるわけではありません。ただ、息子が車に乗って離れていくのを母親が見守るラスト近くのシーンに映された曲がりくねった道を映画館で観た時、〈昔あった国の映画で 一度観たような道〉とはこのことだと直感しました。本作における、主人公と仲良くなった女の子が蛇口に顔を近づけて水を飲む時の目や、道の上で息子を待つ母親の瞳を映す画面に溢れる詩的な感覚は、スピッツの音楽に宿るものと同じだとしか思えなかったのです。
『ハチミツ』で歌われる瞳の詩情
ところで、人間の体において目ほど不思議な部位はありません。
人は、他人の感情を目から読み取ろうとする。相手の愛情を瞳の中に見いだそうとする。しかし、じっと見れば見るほど、目は感情を伝える器官としての役割を逸脱し、不気味な物質としての側面を露わにしていく。ずっと見ていると、目はなんだか怖い〈モノ〉になってくるのです。感情と無感情が、コインの表裏のように同居している。その矛盾に惹かれて、支配されそうになる。「チェンソーマン」のマキマの魅力は、円を無限に重ねたような、単純故に底の見えない瞳の形状にありました。瞳が持つ無感情な性質を、その単純さは強調している。マキマは序盤でデンジを助ける存在ですが、同時に強烈に無慈悲な側面も持つ支配的なキャラクターです。そして、優しさと無慈悲さ、感情と無感情が同居する目の詩情を歌っているのが、『ハチミツ』におけるスピッツです。