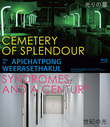映画監督として、現代美術作家として注目を浴びるアーティストの未だ知られざる側面とは?
いまだに忘れられない映画のシーンがある。2016年に公開されたアピチャッポン・ウィーラセタクンの『光りの墓』を観ていた。タイ東北部イサーン地方、かつては学校だったという病院、原因不明の「眠り病」にかかった兵士達がベッドで延々と眠るなか、イットという兵士を看病するジェンという女性を軸に、現実と夢が、現在と過去が交錯する奇妙な物語がくり広げられていた。エンディングまでの二時間近く、延々とつづいていた静謐なムードを覆すかのように、いきなり軽快なメロディのインストの曲が流れ、謎めいたヴォイスオーバーが。その楽曲は女性達が集団で行う健康体操のバックグラウンド・ミュージックだったのだが、地面が凸凹の工事現場で少年達がサッカーボールを追いつづける傍ら、ジェンが瞬きひとつせず驚愕の表情で目を見開くクローズアップのシーンに移りかわる。明らかに、彼女は現実の世界を見ているのでなく、そこにはない別の世界を凝視している。そのシュールな光景とポップな曲調はまるでズレ、拮抗している。何を意味するのかよく解らないのだが、その音使いに頭をハンマーで殴りつけられたかのような衝撃を憶えた。そもそも、この映画は環境音を緻密にデザインしたサウンドスケープで全編が成立していて、いくつかの楽曲は使われても、あくまで映像の描写を背後から説明する役割だった。それが、最後の最後に音楽を前面に浮かび上がらせることによって、映画の中で語られたすべての光景が、重層的な物語のレイヤーが、走馬灯のように脳裏に浮かび上がるドラマティックな仕掛けに取ってかわる。『光りの墓』は、おそらくアピチャッポン映画の最高傑作で、映像や筋書きだけでも語ることはごまんとあるのだが、サウンドの見地からも奥深い作品である。
アピチャッポン作品で使われたサウンド・トラック/環境音をまとめた『Metaphors』

で、このアルバム 『メタファーズ』である。アピチャッポンのこれまでの作品で使われたサウンドトラックから楽曲のみならず環境音も抜き出し、一枚のアルバムにまとめている。映画でも美術でもなく、CDというフォーマットで音楽のコンテキストに持ち込んだゆえか、アピチャッポンならではの音使いを仄めかしつつ、より音楽的なアプローチが取られている。2004年からアピチャッポンの作品でサウンドエディターを務めてきたアックリットチャルーム・カンラヤーナミット(通称:リット)とバンコクを拠点に活動する音楽家の清水宏一が選曲から編集までを手がけている。監督はアドバイザーとして関わるものの、実作業はふたりで行った。清水云く、「ストーリー性を持たせるか、コンセプトはどうするのか、色々考えたんですが、どの素材もすでに各映像作品の一部になっているので、別のストーリーを創り出すことに違和感を感じました。そういう方法でアピチャッポンの世界観に近づけることは不可能だと感じ、あえて各曲を独立させてドキュメンテーション的な作品にすることにしました」。制作過程で、アピチャッポンがこれもこれもと素材を送りつけてきたそうで、それゆえか、2004年の『トロピカル・マラディ』、2010年にカンヌのパルムドールを受賞した『ブンミおじさんの森』、数々の短編にインスタレーション、果ては今年2月にTPAM(国際舞台芸術ミーティング in 横浜)で披露し話題となった舞台作品『フィーバー・ルーム』まで、過去13年間に及ぶサウンドトラックの集大成となっている。
まるで指揮者のよう。アピチャッポン監督が目指すサウンドを表現するために〜
いくつか気になった曲を取り上げてみよう。『ブンミおじさんの森』での《ドーン・オブ・ブンミ》は、撮影現場となったプー・パー・マーン国立公園で録音された環境音をリットがリミックスしている。深い森の虫の音がこの映画の幻想的なムードを作り出す鍵となっていた。このようなフィールドレコーディングを使った曲はすべてリットが担当している。『フィーバー・ルーム』での《ジェンジラーズ・リバー》は、アピチャッポンのアイディアで清水が病院のシーンで使われた医療機器の音をサンプリングしてリズムを刻んでいる。サンプラーやエレクトロニクスで演奏された曲は清水が担当している。彼はアピチャッポンとの共同作業について、「意識していることは、作り込みすぎないことでしょうか。あまり主張しすぎないもの、映像の一部になるようなもの、それでいて独特の個性を感じるものでなければいけないので、そのバランスが難しいところです」 。アルバムの最後は、タイのミュージシャンのジェータモン・マラヨーターがペンギン・ヴィラ名義で演奏する《高所恐怖症》という弾けるようなポップソング。『ブンミおじさんの森』で使われていた。アピチャッポンは、映画のなかで、このような既成のポップソングを意表をつくように放り込むことがある。『光りの墓』のエンディングもその一例だろう。ちなみに、選曲はすべて監督自身が行うという。アルバムを聴き込んでいくと、サウンドデザインとしても、多様なスタイルを交錯させながら、ひとつの世界観を提示していることがわかる。さらにいえば、それは、アピチャッポン特有の複数の(=可視、不可視の)物語を重層的なレーヤーとして提示しながら、映像の、意味の、コンテキストのあり方を複雑に編集していく方法と底流をなしている。清水、リットと話していて気付いたのだが、アピチャッポンは映像のみならずサウンドもかなりの部分でコントロールしている。リット云く、「彼はサウンドの面でも天才的です。指揮者の役割を果たしています。わたしと清水はミュージシャンのように素材を提供するのです。ただ、面白いのは、わたし達は即興的に素材を作り上げることが多く、予期せぬ結果を生み出すことが多い。彼はそれが好きなのです」。清水も、「想定内の音や音楽を渡しても、却下されることがほとんど。自分では想定していなかったものが採用されることが多い。普段録りためている素材や、自分のライヴ音源を聴いてもらうこともあります。『フィーバー・ルーム』で使われた音は、そこから広がっていったものです」。アピチャッポンはフィルムメーカーであり、美術作家であるのだが、コンポーザーとしても類い稀なる才能の持ち主のようだ。しかも、遊び心のある。
アピチャッポン監督が初めて取り組んだ舞台作品『フィーバー・ルーム』
最後に『フィーバー・ルーム』について述べておこう。新たな可能性を示唆しているからだ。韓国、光州のアジア芸術劇場から舞台作品を作らないかと委嘱されたのだが、舞台上に客を座らせて、観客席も含めた劇場全体を使う異色作として完成した。前半はこれまでの映像での試みを踏襲し、舞台上のみを使い、可動式の複数のスクリーンに同時期に作られた『光りの墓』に関連した映像を映し出す。後半になると舞台のカーテンが上がり、暗闇のなかで劇場の全体がむき出しになり、フォグマシーンの煙で何も見えないと思いきや、強烈な光線が客の目の前からオーラを放ち始める。ビデオプロジェクターを光源にビデオの映像を足したものだ。抽象的で複雑なパターンを描きだす光は、劇場全体に配置されたスピーカーとサブウーファーから放たれる立体音響と絡みって、空間全体に広がっていく。もはや映画のフレームは存在しない。わたしも体験してみて、尋常ならざる視聴覚体験に度肝を抜かれた。LSDの幻覚体験に近く、光が網膜に映る画像ではなく、脳内で3Dの映像として描かれる。同時に強烈な低音がボディを揺さぶり、思考はほぼ停止、感覚のみが鋭敏になっていく。フォーマット自体に目新しさはない。美術作家のアンソニー・マッコールが70年代に始めた光による三次元の彫刻に近いし、他にもリファレンスは上げる事ができる(グレッグ・ポープ、ケン・ジェイコブス、それにガイシンのドリーム・マシーンとの類推か)。だが、際立っているのは、それらの効果がメディアの拡張だけへと向うのではなく、アピチャッポンの映像の世界全体とメタフォリカルに結びついていることだろう。プリミティブな人間の生活の営み、それを超えたアニミスティクな精霊の世界へ――見えるものは、聴こえるものは、ずいぶんと遠くまで拡張している。
Apichatpong Weerasethakul(アピチャッポン・ウィーラセタクン )
1970年タイ・バンコク生まれ。コーンケン大学で建築を学んだ後、シカゴ美術館付属シカゴ美術学校で映画制作修士を取得。 1993年に短編映画、ショート・ヴィデオの制作を開始し、2000年に初の長編映画を制作。1999年に「Kick the Machine Films」を設立。既存の映画システムに属さず、実験的でインディペンデントな映画制作を行っている。
寄稿者プロフィール
恩田晃(Aki Onda)
ニューヨーク在住。先月までヨーロッパで『スペース・スタディーズ』というプロジェクトを展開していた。キュレーターとして、作曲家ホセ・マセダのリサーチのため8月からマニラへ。10月には日本へ。その後、サウンドアーティストの鈴木昭男とのデュオで5都市を巡る北米ツアー。ほぼ休みなく大陸間を移動しつづけている。
EHIBITION INFORMATION

撮影:木奥恵三 画像提供:森美術館、東京
『サンシャワー:東南アジアの現代美術展 1980年代から現在まで 』
期間:開催中~10/23(月)まで
会場:国立新美術館 企画展示室2E /森美術館
sunshower2017.jp/
タイを代表するアーティストであり映画監督でもあるアピチャッポン・ウィーラセタクンとアーティストのチャイ・シリが本展のために制作した、白象をモチーフにした体長8メートルの巨大モニュメント、《サンシャワー》(2017年)をはじめ、スーザン・ビクター(シンガポール)、ウダム・チャン・グエン(ベトナム)、やアルベルト・ヨナタン(インドネシア)、ズル・モハメド(シンガポール)の作品など、本展のために作成された新作や未発表作品が多数出典されている。