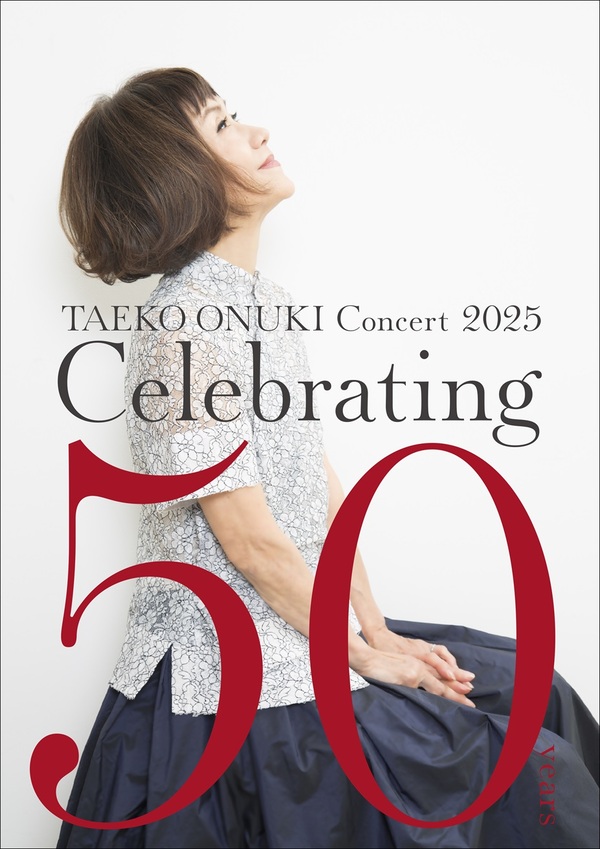8ottoが6年ぶりとなるフル・アルバム『Dawn On』をリリースした。ASIAN KUNG-FU GENERATIONのフロントマン、Gotchこと後藤正文が主宰するレーベル〈only in dreams〉からのリリースとなった同作は、後藤みずからがプロデュースを担当。音作りのスマートさ、グルーヴの多彩さ、楽曲の完成度……あらゆる面でこれまでの彼らの音源を凌駕しており、完全復活を強烈に印象付ける作品になった。Mikikiではメンバーへのロング・インタヴューの掲載を予定しているが、今回はその前に、彼らの足取りと、国内シーンにおける〈異端〉と言うべき独自性について、あらためて振り返っておきたい。なぜ8ottoは唯一無二の存在なのか――その理由を考察した。
強烈なリフの力で独自性を発揮してきた
国内シーンきっての異端バンド
ポップ・ミュージックにおいて、一緒に歌える/シンガロングできるというのは魅力の一つであり、それらに親しむリスナーにとっても喜びの多くを占めている。フェスティヴァルでの大合唱のみならず、寝室で跳ね回りながら、あるいは電車やバスのなかで唇だけをそっと動かしながら、お気に入りの楽曲のフレーズをなぞっていくことの楽しさは、誰もが知っているのではないか。おそらく、その営みにおける多くは、ヴォーカル・パート――いわゆる〈歌メロ〉を口ずさんでいるだろうが、実はポップ史にはヴォーカル・メロディー以上に歌いたくなる〈リフ〉が存在する。2000年代以降のエポックメイキングな楽曲としては、極太のギターによる〈ダーダダダダ・ダーダー〉というイントロ&シンプルな4つ打ちのコンビネーションで、革命的なインパクトをシーンに与えたホワイト・ストライプスの“Seven Nation Army”(2003年)となるだろうが、時代を遡ってもAC/DCの“Back In Black”(80年)やディープ・パープルの“Smoke On The Water”(72年)、さらにローリング・ストーンズやキンクスのビート・ナンバー……ロック・バンドに限らずポップやダンス・ミュージックの文脈でもヴォーカル以上に印象的なリフは枚挙に暇がないはずだ。
その一方で、日本国内のバンド・シーンに目を向けると、いわゆる〈リフで大合唱〉となる楽曲はなかなか見あたらない。それは、録音に際して中音域、主にヴォーカルへとウェイトを置くJ-Pop/Rock的な音作りも関係しているのかもしれないし、歌詞への共感に価値を置くリスナーの感性に依っている面もあるだろう。だが、そうした国内のポップ・シーンにおいて、歌メロ以上に〈リフ〉を打ち出してきた存在が、本稿の主人公である8ottoだ。彼らのリフは必ずしもメロディアスという側面に限定されるものではないが、コードに重層性を持たせたり、リズムのダイナミズムを強化したりと、歌にも増して楽曲の主役となってきた。今回は、先日リリースされた彼らの復活作『Dawn On』のリリースを機に、なによりもその強烈なリフの力で独自性を発揮してきた8ottoの魅力を、ポップ・ミュージックにおけるリフの発展史を簡潔に紹介しながら紐解いていきたい。
歌メロ以上にリフで耳を奪う
J-Rockシーンを震撼させた初作『we do vibration』
まず、彼らの足取りを振り返っておくと、大阪のアンダーグラウンド・シーンで活動してきた8ottoに全国区的な知名度をもたらしたのは、2006年に発表したファースト・アルバム『we do vibration』。フロントマン、マエノソノマサキのドラムス/ヴォーカルという独特なスタイルが与えたインパクトもさることながら、ストロークスの『Room On Fire』(2003年)などに貢献してきたNY拠点のエンジニア・ヨシオカトシカズがプロデューサーを務めていたことでも話題を集め、日本のバンド・シーンに突如登場した異端とでも言うべき存在感を放っていた。
初期の彼らを代表する楽曲と言えば、同作に収録された“0zero”。ベースラインと4つ打ちのキックでスタートする、まさに〈Seven Nation Armyスタイル〉の同曲において最強のフックとなっているのは、TORAの奏でる不穏さ漂うベースリフと、ヨシムラセイエイによる裏打ちのリズム・ギターだ。マエノソノのやさぐれていてボソボソとつぶやくような歌には、ルー・リードやジュリアン・カサブランカスを彷彿とさせるダーティーでクールなカリスマ性が醸されているものの、いわゆるアンセミックな人懐っこさはない。髭(HiGE)やOGRE YOU ASSHOLE、COMEBACK MY DAUGHTERSといったオルタナティヴ志向を持ったバンドの台頭が起きつつも、ASIAN KUNG-FU GENERATIONやGOING UNDER GROUND、BEAT CRUSADERSらフックの効いたメロディー・センスと思春期的なセンスを武器にいわゆるJ-Rock的なサウンドを形作ったバンドがシーンを席巻していた当時において、〈歌メロが前景化していない〉8ottoの独自性は際立っていた。
翌年にリリースしたセカンド・アルバム『Real』は、アンサンブルを整理したことでメロディアスな魅力も増強。その一方、作品の冒頭を飾った“Counter Creation”では、ハード・ロッキンなギターのコンビネーションとミッドテンポのディスコ・ビートを重ねた屈強なダンス・パンクをかますなど、肉食獣のごとき獰猛さも衰えていなかった。
だが、この時期の8ottoにおける最良の産物としては、ファーストとセカンドを橋渡ししたミニ・アルバム『Running PoP'』(2007年)に収録された“Say”を推したい。初期の彼らのディスコグラフィーのなかでは、ひときわメロディー・ラインの立っている楽曲にもかかわらず、それ以上にキャッチーなリフが〈サビ〉の役目を担っており、さらにライヴでは最大の起爆力を持つアンセムとなったというのは、彼らがなにより〈リフのバンド〉だということの証左と言えるだろう。以下のライヴ動画で、その爆発の瞬間を観てほしい。
リンク・レイによる〈リフ〉の誕生
60年代のブリティッシュ・ビートを経て、ロックの顔はギター・ヒーローに
そもそも、〈リフの音楽〉は、どのように発展してきたのか。それは、ロックンロールが誕生してから約10年を経た1958年に起こったと言われる。ギタリストのリンク・レイが、ダイヤモンズのドゥワップ・ソング“The Stroll”にDとEの荒々しいコード・ストロークを乗せた“Rumble”を発表。ディストーションとパワーコードを発明したとして名高い同曲を起点に、ギター・リフは展開していくことになる。
60年代に入ると、数多のブリッティッシュ・ビート勢によって“Rumble”が確立した手法が援用されていく。なかでも、リフの定番と化したのがローリング・ストーンズの“Satisfaction”とキンクスの“You Really Got Me”。特に後者は〈元祖ハード・ロック〉とも言われており、ヴァン・ヘイレンのカヴァーで知った人も多いだろう。以降、ギター・リフはいわゆるロックの代名詞となり、ジミー・ペイジ(レッド・ツェッペリン)やエリック・クラプトン(クリーム)といったギター・ヒーローの誕生に導かれながら、ダウンチューニングとパワーコードを駆使しながら悪魔的なフレーズを奏でるトニー・アイオミ(ブラック・サバス)、スクールボーイ・ルックをまといアイコンとしてもキャッチーだったアンガス・ヤング(AC/DC)ら〈リフ名人〉がその名を轟かしていく。
ポスト・パンク〜グランジ、そして最前線を更新し続けるアークティック・モンキーズ
2010年代はメインストリーム・ポップも〈リフの時代〉へ
パンク~ポスト・パンクの時代に入ると、アンディ・ギル(ギャング・オブ・フォー)、トム・ヴァーレイン&リチャード・ロイド(テレヴィジョン)といったプレイヤーたちが、鋭利なリフでリスナーを痺れさせてきた。またギター以外でも、ジョイ・ディヴィジョン/ニュー・オーダーのピーター・フックが発明した、ルート音を弾かず高音部でリフを弾くベース奏法は、多くのフォロワーを生むことになる。そして、ジェイムズ・ヘットフィールド(メタリカ)やイアン・スコット(アンスラックス)らがギター・カリスマの座をかっさらったメタルの時代を経て、90年代前半にはオルタナティヴが勃興。同ムーヴメントは、80年代に加速したポップ産業化への反動としての、生々しいギター・サウンド復権という側面もあり、なかでもジョン・フルシアンテ(レッド・ホット・チリ・ペッパーズ)やトム・モレロ(レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン)が、ときに非ロック的な意匠を駆使しながら、印象的なリフを作り出していく。
2000年代以降も、ストロークスが牽引したガレージ・ロック・リヴァイバルや、特にリズム・コンビネーションの面で8ottoにも深く影響を与えたポスト・パンクの再興などがありつつ、スタジアム・チャントとして定着するまでとなった件の“Seven Nation Army”や、ブラック・キーズ“Lonely Boy”、フランツ・フェルディナンド“Take Me Out”など〈リフで合唱〉できるロック・アンセムは登場し続けている。“I Bet You Look Food On The Dancefloor”“Do I Wanna Know””といったパワフルな楽曲をたえず送り出しているアークティック・モンキーズは、ブルージーなギター・フレーズと先鋭的なプロダクションを掛け合わせ、作品ごとに〈リフのロック〉の最前線を更新している存在だ。
だが、近年の傾向として着目したいのは、ギター・バンド以上にメインストリームのポップ・シーンにおいて〈リフありき〉の楽曲がチャートを席巻していること。それには、音数が少なく、かつミニマムなループ構造を敷いたトラップ以降のポップにおいてリフの存在感がおのずと高まってきたことも関係しているのだろう。メジャー・レイザーの“Lean On”やジャスティン・ビーバーの“Sorry”といった世界的なヒットソングを思い出してみても、もっとも中毒性が高いのは、メインの歌でなくシンセサイザーのリフと言っていい。また、〈リフ〉ベースのロックとして同時代性を掴んだ成功例と言えば、アラバマ・シェイクスの2015年作『Sound & Color』を挙げたい。ビートとリフの循環でダイナミズムを積み重ねていくという、その方法論はやがてベックの最新作『Colors』の下敷きにもなっていく。
リフのコンビネーション×磨きのかかったソングライティング
理想的な融合で新境地に達した復活作『Dawn On』
では、〈リフのポップ〉が主流となっていった、10年代において8ottoはどう音楽性を発展させていったのか。その答えとなるのが新作『Dawn On』である。このアルバムで彼らが打ち出しているのは、従来のリフを主体としたバンド・サウンドと耳に残るソングライティングという新機軸の理想的な融合。スリリングなコンビネーションを見せる2本のギター、太いグルーヴを作り出すリズム・アンサンブルといった4人の演奏はさらに力強さをとしなやかさを増しつつ、今回それらと同様に、あるいはそれ以上の存在感を発揮しているのがマエノソノマサキの〈歌〉。後藤正文によるメリハリの効いた音作りも貢献してか、過去最高に歌メロを際立たせた作品に仕上がった。マッシヴなダンス・パンク“SRKEEN”や妖艶なニューウェイヴ・ポップ“Mr. David”といったリフが牽引していく楽曲においても、攻撃的なサウンドと流麗なヴォーカル・ラインが見事に溶け合っており、これまでの彼らになかったコクのようなものが、音の隅々にまで拡がっている。
加えて、“Ganges-Fox”の終盤に据えられた、山間から突如姿を現す黄金色に輝く太陽のごときアンセミックな大サビや、“Summer Night”の開放的なコーラスなどが、『Dawn On』=〈歌のアルバム〉であることを印象付けている。余白を活かしたプロダクションやスモーキーな質感のサウンドの真ん中を、マエノソノの歌が堂々と闊歩するさまは、前述のアラバマ・シェイクス最新作ともシンクロしており、その意味ではきわめてモダンなロック・アルバムとも言えるはずだ。
バンドのこうした変化の真相については、本稿後に公開されるメンバーへのインタヴュー記事に譲りたいが、〈リフの時代〉という追い風のなかで、あえて歌の求心力を突き詰めるという前進に賭けた彼らに、まずは賛辞を送りたい。ソングライティングの練磨とサウンドのモダナイズが、リフとメロディーを有機的に結び付け、大きなスケール感と細やかさを備えたアンセムが生まれる。名人芸と言うべきリフを鍛え上げつつ、練磨を重ねたメロディーとの化学反応を引き起こすという進化を遂げた『Dawn On』で、8ottoは新たな〈歌〉を獲得したのだ。
Live Information
2017年11月19日(日)兵庫・神戸 太陽と虎
共演:ASPARAGUS
2017年12月4日(月)大阪・難波Hatch
共演:ASIAN KUNG-FU GENERATION/FEEDER
★詳細やその他のライヴ情報はこちら