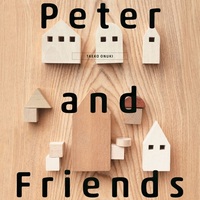1975年4月25日発売のシュガー・ベイブ『SONGS』から、今年でデビュー50周年!
『ピーターと仲間たち』は、大貫妙子のデビュー50周年を祝ってのアルバムだ。昨年7月9日の東京EXシアター六本木でのコンサートを録音したもので、1980年代、1990年代にエレクトロニック・サウンドが彩った曲を中心に構成されている。テクノロジーの進歩もあってステージでも当時のサウンドが再現できるようになったらしい。そしていま、服がしっとり濡れてくるような錯覚さえする“Rain”や、絶妙なテンポを改めて楽しませる“Happy-go-Lucky”などに続いて、“Carnaval”が流れている。彼女が後に振り返って、「自分の声や曲調に対しての手掛かりをいくつも発見することができた」とも、「自分の居場所を見つけることができた」とも自ら記したアルバム『ROMANTIQUE』の幕開けを飾っていた曲だ。
ヨーロッパの空気を加えることで一つの転機を迎えた季節を代表し、編曲に坂本龍一、そして彼を含めたYMOの3人が主にバックをつとめていた。1980年発売だから、27才の彼女の作品ということになる。約45年後に同じ歌を、今回はフェビアン・レザ・パネ、鈴木正人、坂田学、伏見蛍、網守将平たち、気鋭の若いバンドの演奏で歌い、曲の途中でメンバーを紹介している。時間のページを捲りながら聴いていると、音楽が奏でられるとき、時間はどういうかかわりをするのだろう、ふと、そんな思いが脳裏をよぎる。と同時に、50年かあ、と溜め息が出てきそうになったりもする。
大貫妙子の歌声を初めて聴いたのは、もちろん、シュガー・ベイブの頃だ。1970年代半ば、荻窪ロフトをはじめとするライヴ・ハウスが特別な存在のように思え、彼ら以外にも鈴木茂&ハックルバックや久保田麻琴&サンセット等々を聴きに足を運んでいた。毎日が、新しい出会いに満ちていて楽しかった。中には、デビュー・アルバム『SONGS』がまだ出ていないときのライヴもあったと思う。それでも足を運んでいたというのは、インターネットやSNSがない時代でも、それなりに必要な情報はこちらの気持ち次第で手に入れることが出来たということだろう。音楽を楽しむ環境は随分と変わったけれど、それはなにもテクノロジーや時の流れのせいばかりではない、と自戒を込めて思う。
当時の彼女は、キーボードを前にうつむいてばかりのようにみえた。長い髪の隙間からみられる表情は心細げでさえあった。男性、つまり山下達郎と彼女の二人がリード・ヴォーカルを分け合うという、当時のバンドでは珍しかったが、彼女は山下ほどには目立つ存在ではなかった。しかし、「きっとあきらめるわ 今 いまなら 何も無くしたものは ひとつないし」と歌いだされる“いつも通り”などには、胸が爽やかに震えるのを覚えたものだ。都会で生きる若い女性の歌と言えば、パターン化された歌が多かったが、彼女の歌に出てくる女性たちからは、迷ったり、悩んだり、一人一人の息遣いのようなものが伝わってきた。筆でサーっとキャンバスに刷くように描くそのタッチも、彼女の歌声とあってみずみずしかった。
少なくともしばらくの間は、この人の歌は聴き続けるだろう、そんなことを思ったほどだ。ソロ・デビューしたときのアルバム『グレイ・スカイズ』の中の“街”も、そんな思いを強める一つだった。これも、都会で暮らす若い女性の心情を歌ったものだが、広い都会で、毎日のように雑踏を行き交う中で、その女性にこんなフレーズをつぶやかせるのだ。「すれ違う時はいつでも 少し優しくなる私を気付く人はいない」と。また、当時はまだ漠然としたものだったが、歌で表現することがどういうことか、どういうことを歌で表現したいのか、シンガー・ソングライターとしての志のようなものが感じられた。例えば、ぼくの記憶のせいで正確ではないかもしれないけれど、愛してるだとか、好きだとか、当たり前の言葉を使わずに恋愛を歌うというようなことも、その一つだ。しかも、音楽で何かを表現しようとするとき、何が大切で、何が大切でないのか、何が必要で、何が必要でないのか。周囲に振り回されることなく、自分自身で選ぶという、自由とそのための覚悟のようなものを、若くして意識していたような気もする。