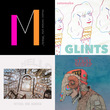その才気を知らしめた前作『Lukewarm』に続いて入江陽をプロデューサーに迎えた新作。入江とのデュエットによる“ばかみたい”ではレゲエ風のフロウを披露し、“Loop”ではTomgggが敷く流麗なビートを巧みに乗りこなすなど、これまでにないグルーヴ重視のアプローチが楽しい。彼女のチャーミングな魅力はそのままに、ソングライティングの新たなヴァリエーションも引き出されている。またしても傑作!
2018年3月リリースの前作『Lukewarm』からちょうど1年で届けられたさとうもかの新作『Merry go round』。牧野桜(MARUTENN BOOKS)のカヴァー・アートが物語るとおり、前作からの連続性と関連性を強く感じさせる。
『Merry go round』は『Lukewarm』から続いて、さとうと同じシンガー・ソングライターである入江陽がプロデュースしている。とはいっても、2人とも〈シンガー・ソングライター〉という枠組みやイメージからは大きくはみ出すユニークな個性の持ち主だ。だからこそ気が合うのだろうし、前作について2人にインタヴューをしたとき、さとうは〈自由にやらせてもらった〉というポイントを強調していた。
そのインタヴューの冒頭で大貫妙子とプロデューサー・小倉エージが噛み合わないままに生まれた『MIGNONNE』(78年)の例を引いたが、『Merry go round』は『Lukewarm』と同様、その真逆を行く結果となっている。つまり、さとうの作家性と入江のディレクションが実にナチュラルに噛み合っているように感じられるのだ。音楽性は(ジャンル的にも)より多彩に、歌声や詞はより伸びやかに、自由に花開いている。
アルバムの音楽面の解説は小鉄の原稿に譲るが、Bullsxxtのメンバーである沼澤成毅とPamによるODOLAが制作した“ばかみたい feat. 入江陽”は、“Loop with Tomggg”と並んでアルバム前半の白眉だろう。ノスタルジックでゆったりとしたメロウR&Bのこの曲には、さとうの個性によってODOLAのポップ・ポテンシャルが引き出されているような感覚もある。また、さとうの節回しもラップ的で、新たな一面を見せている。
入江はよく客演した相手の名前を歌詞に持ち出すのだが、この曲の〈もかチャンの恋バナをきく〉という歌い出しで聴き手は一気にメタな視点へと引っ張りあげられる。例えば、“melt summer”などでは恋愛にまつわる心の揺れ動きがかなりの具体性をもって描かれているが、さとうのラヴソングのリアリティーと虚構性のバランスをグラつかせる入江の歌はかなりスリリングだ。
一方、“雨の日のストール”“友達”“Merry go round”“ケイトウ”といった楽曲はガット・ギターやピアノの弾き語りが中心。さとう自身の多重録音や環境音が入っている点で、彼女のデモに近い感触だ。『Lukewarm』の楽曲もそうだが、どこかプライヴェートな録音を密かに聴いているような気分になる。この、極めて私的な音楽であると同時に開かれたポップ・ミュージックであるという特性は、彼女の優れたSSW的個性だろう。
また、アルバムに豊かさをもたらしているのがいくつかのスキットやインタールード的な作品で、例えば“チケット”では〈大人一枚で〉〈大人なの? 子どもじゃないの?〉といったやりとりが笑い声とともに聴こえてくる。ヘッドホンやイヤホンで聴いていると、心地良さとくすぐったさが同時にやってくるのがASMR的。“チケット”で聴けるような〈大人でも子どもでもない、中間的でグレーな存在であること、その迷い〉というのは、『Lukewarm』に続いて本作の歌詞の通奏低音になっている。
小鉄は本作について〈CD構成〉と書いていたが、こうしたスキットが要所に配置された構成は、どこか90年代のヒップホップ・アルバムのよう。スキットで各楽曲が繋がれることで、『Merry go round』というアルバムは物語性をもって聴き手に語りかけてくる。だが、ジャズからエレクトロ・ポップ、宅録風の弾き語り、ウェルメイドな“melt summer”まで、振れ幅の広すぎる楽曲群をなんとか繋ぎ止める接着剤のような役割もスキットは果たしている。それは音楽性だけでなく、参加ミュージシャンの多彩さ(Tomggg、神戸のTsudio Studio、evening cinemaの原田夏樹、DC/PRGのドラマーでもある秋元修など)、そして、さとうの自室やiPhoneで録音された音源も含む音質的なバラつきも繋ぎ止めている。
僕がさとうの音楽を聴いていて思い出すのは川本真琴だ。もちろん、2人はまったく違う個性を持っているのだが、音楽家としての自由度の高さ(そういえば、川本もピアノとギターを演奏する)やライヴから感じる奔放さ、そしてクリシェを無視してもポップに響くメロディーラインには通じるものを感じる。そして本作を聴くと、さとうの歌はどんどん力が抜けて、自由さを獲得していっているような気がする。このまま力まずに、でも全速力で駆けていってほしい。